
仙台・オンラインで
親や配偶者などの身近な人間関係の悩み相談・解決
アドラー心理学講座
アドラー東北
お電話受付時間 | 平日・9:00~17:00 |
|---|
休日 | 不定休 |
|---|
アドラー東北・高橋の子育て・身近な人間関係お悩みブログ
子育て・親や身近な人間関係のお悩み・こんなことありませんか?
2023・8・23 「どうしてそんなに私を嫌うの?!」 生まれながらの第一子と第二子の攻防

仲のいい兄弟でいられるには
どうしたらいいのか・・
「どうして姉は私を嫌うのだろう?私が一体何をしたっていうんだろう?」
A子さんは、自分の一つ上のお姉さんとの関係でずっと悩んできました。子どものころはそれなりにやれていたのに、大人になってから姉との関係がどんどん悪くなっていきます。
子どものころはもちろんけんかもありましたが、それほど仲の悪い姉妹というわけでもなくそれなりにやってこれたのです。
自分は姉のことを好きだし頼りにしているのに、なんだか突き放されたと感じたり冷たいと感じることがとても多くなってきたのです。
嫌われるようなことをした覚えもありません。それなのになぜかとても姉に嫌われているような気がします。
どうしてなんだろう?と考えてもわかりません。でも姉妹である以上はずっとこれからも付き合っていかなければならない相手です。もしもこれから先どんどん関係が悪くなるようでは困ることも多くなっていきます。
年々歳をとっていく親のこともありますので、どうしたものかと一人で悩んでいました。夫に相談しても「気にしすぎではないか?」と言われるばかりで、気持ちがすっきりすることはありません。誰にも相談できずに悩んでいたのでした。
そんな時にある決定的なことが起きました。
親の世話をしている姉にちょっと意見を言ったところ有無を言わさずに却下されてしまってとても傷ついたのです。まるで自分の意見など必要がなく自分の存在そのものを否定されたように感じてとても悲しくなったのでした。
「どうして私はこんなに嫌われているんだろう?全く聞き入れてもらえないってどういうことなんだろう?」そう思ってご相談にいらしたというわけです。
「そうだったんですね。全然耳を傾けてもらえないのは悲しことですよね。」
「はい、自分の存在など全く必要とされていないと感じました。」
「でしょうねえ。どうしてお姉さんはそういう態度をとったんでしょうね。」
「それが全く分からないんです。親のことであれこれ言ってやってもほとんど受け入れてもらったことはありません。」
「お姉さんの状況はどんな感じですか?」
「自分の親のことだけでなく配偶者の親も抱えていますからとても大変だということはわかります。でもだからって全くこちらの言うことを聞かないというのはどうなのかなとそうも思います。」
「お姉さまの置かれている状況については理解できておられるようですね。まあいずれにしても第一子であるお姉さまと第二子であるA子さんには根本的に相いれないものがあるので、その辺はアドラー心理学で読み解くことは可能です。お聞きになられますか?」
「はい、ぜひお聞きしたいです。なぜどうして姉がああなるのか・・ヒントが欲しいです。」
「わかりました。 ええとね、生まれた時のことから考えてみます。そうするとわかりやすいので。」
「そんなに前のことにヒントがあるんですか?」
「ええ大事なんです。兄弟間がうまくいかないのはこの生まれた時からの状況にあると言っても過言ではありません。最初にお姉さんが生まれた。ですからお姉さんは最初は一人っ子だったわけですよ。そうすると親の愛を一心に受けていたんです。これはわかりますよね。」
「はい、わかります。」
「ところが二番目のA子さんが生まれて親の愛や注目がどうなると思います?」
「私に向くんですよね。」
「そうそう、そうなんです。親の愛と注目がどうしても小さくて手がかかるあなたに行くようになった。そうするとお姉さんはどう感じるでしょうか?」
「親をとられた?とか・・寂しい・・とか悲しい・・とか?ですか?」
「そうね、そうするとあなたのことはどういう存在だと思うと思いますか?」
「親を自分から取り上げた相手だと。。」
「そうだと思います。年の近いご兄弟には多い状況です。ほかにもいろいろ考慮しないといけない点はあるけれど、おおむね最初の子と二番目の子にはそういう確執がもともと起こりやすいってことです。この時に親が第一子にどうかかわるかによってその後は変わっていきますが、ほとんどの親御さんは目の前の子育てに精一杯ですから、そこまで考えが回らないのが普通です。」
「そうなんですね。。だから私が何をしたわけでなくても基本的に姉は私をそういう存在だとして捉えているってことになるんでしょうか。。」
「お互いに大人同士ですからそれまでは表面的にはやれていたとしても、どちらかが気持ちに余裕がなくなったり、何か困った状況に陥ったりした場合にはそういうことが表に出てきやすいと思います。」
「そうなんですね。。なんだかショックです。。姉がそんな風に私のことを思っていたとしたら。。」
「でもそれってお姉さんの捉え方の問題ではないかしらね。あなたには何の落ち度もないと思いますよ。これからどうしていくか、この辺りを踏まえたうえで考えていくことは可能ですから。」
「ありがとうございます。ずっと付き合っていかなければならない相手なのでできればうまくやっていきたいので。」
「わかりました。それではこれからどうしていくかご一緒に考えていきましょうね。」
今までの親子関係は完全にタテであり、家族間にもタテの関係が当然のようにあります。そして兄弟を良かれと思って競わせるといった方法をとっておられる方もおられるでしょう。
しかしながら、基本的には第一子と第二子にはこういうもともとのバックグラウンドがあるのだということを知ったうえでの配慮が必要となるのではないでしょうか?
親が力を失い、介護や見取りの時になってこういう兄弟間の争いごとは表面化することが多いと感じています。もともとあったものが露になるのです。
ご参考になれば幸いです。
2023・7・31 「お前に俺の何がわかるの?!」 男性が一番傷つくこと・・

配偶者にだけは理解してほしい
男性が一番傷つくこと
「主人がすっかり気落ちして口を聞いてくれなくなってしまった。」
そんなご相談でいらした40代の専業主婦のA子さん。それまではそれなりに会話もあり仲のいいどこにでもいる夫婦だったと言います。
コロナになってご主人のお勤めしている会社の業績が悪化。どんどん給料が減り、先行きの不安が家計にも及んできたころにこんなことがあったんだそうです。
「今月も以前より少ないけどよろしく頼む。大丈夫か?」
「大丈夫も何もやるしかないじゃありませんか。あなたにどうにかできるわけでもないでしょ?!」言っても仕方のないこと言われてもねと、お子さんのことで少々イライラしていたこともあり、A子さんはそんな風に言葉を返してしまったと言います。
いつも温厚なご主人が顔をこわばらせて「俺だって頑張ってるんだ。おまえに俺の何かわかるっていうんだ?!」
その言葉を聞いたときにA子さんはもしかしたら自分は言ってはいけないことを言ってしまったのかもしれないという大きな不安に駆られたとおっしゃいました。
その日を境にご主人はA子さんと目を合わせようとしないばかりか口を聞かなくなり、家に帰ってきても自室にこもり、ほとんど家庭内別居状態に。。
私はそんなにひどいことを言ってしまったんだろうか?少し感情的ではあったけど、事実だし、別に悪気があったわけではないし。
なぜご主人がかたくなにA子さんを避けるようになったのか、わからないまま、どうしたらいいのかご相談にいらしたというわけでした。
「なるほど、一緒に住んでいらしてそういう状況だとお辛いですよね。以前のように仲良くしたいのですね。」
「はい、そうなれればうれしいと思っていますが、なぜ主人がああなってしまったのかわかりませんし、彼の気持ちがわからなければどうしたらいいのかもわかりません。」
「そうですよね。ご相談にいらしていただいてありがとうございます。お気づきのようですが、つい言ってしまった言葉ですが。。」
「ああ、そうですね。あなたにどうにかできるわけでもないでしょう?って言葉ですよね。」
「たとえば・・ですね。あなたが何か誰かに頼まれて一生懸命やっていたと考えてみてください。ところが結果があまり良くなかった。自分でもがっかりしているところにある人に、仕方がないでしょう、あなたにどうにかできるわけでもない、と言われたらどういう気持ちになりますか?」
「あ~、へこみますね。自分のそれまでを否定されたような気持になります。」
「プラス男性特有のある傾向についても知っておいたほうがいいかもしれません。」
「というと・・?」
「男性は女性に比べて社会的に自分がどうかということが自分の価値とイコールになる傾向が高いということです。」
「社会的にどうかというのは、地位とか給料とかの評価の部分ですか?」
「そうです。ですからその部分が危うくなると自分の存在価値そのものにかかわるような危機感を持つ恐れもあると思います。」
「そこを私は突いてしまったんですね。あ~どうしよう。」
「そのことについてまだ何もご主人とお話していらっしゃらないようですが。。」
「ええ、相手の気持ちがわからないのに、下手なことをいえばもっと関係が悪くなるかもしれませんし、怖くて言い出せなかったんです。」
「そうだったんですね。いずれにしてもあなたはご主人と元通り仲良くしたいんですよね?」
「はい、そうしたいです。」
「それならまずそのことをご主人に伝えましょう。」
「仲良くしたいってですか?」
「そうね、前みたいに仲良くしたいって。面と向かって言えなかったら、LINEでもいいでしょう?」
「返してくれるでしょうか?」
「返してくれるかどうかはわからないけど、今のままで行動しなければ何も変わらないことは確かですよね。できることから始めてみるのはどうでしょうか?」
「わかりました。後はチャンスがあれば、あの言葉について謝ったほうがいいのかしら。」
「謝れるなら、心からそうしたいならしたらいいと思います。傷つけるつもりはなかった。感謝していることもね。ご主人様を愛していらっしゃるのね。素敵なことだと思いますよ。」
「ありがとうございます。なんとかなるかどうかわからないけど、頑張って働きかけてみます。」
男性は外へ出かけていき実りを家庭に持ち帰る。女性は居場所を作り帰りを待つ。男女の本能的な役割がここにあります。人類が生まれてからこのかたその基本的なスタンスはあまり変わっていないように思えます。
外からの持ち帰りの実りを足りないと言って批判されれば男性は深く自分の能力について自信がなくなり傷つくのです。
いずれにしてもお互いを認め合い理解し合い、その努力を惜しまずすること。双方が「仲良くしたい」と思っていればゴールへ向かって協力することはできるはずで、今回のケースではご主人がA子さん同様に仲良くしたいという気持ちがまだ残っているかどうががカギになるのではないかと思っています。
ご夫婦のご相談も相談会で承っております。個別相談もありますのでどうぞご利用くださいませ。
2023・7・30 「自分のことは自分でやってよ!!」 手がかかるのは・・手をかけているから

なぜ自分はこんなに忙しい?
普段から手のかかるお子さんたち。
それなのに夏休みにはさらに忙しくなり、あなたがしてくれるのを待っているお子さんたちを前に思わず「自分のことは自分でやってよ!」と言いたくなっていませんか?
A子さんは、三人の小学生のお子さんをお持ちのお母さんです。夏休みや冬休みなど、三人のお世話でいっぱいいっぱいになります。
親として子どもたちにしてやれることはしたい、それが親の務めだと思って一生懸命やってきましたが、さすがに長いお休み期間中にはなんどか自分でやってよ!と思うことが何度もあるようになりました。
もう小学校の高学年になったお兄ちゃんですら、自分のことはお母さんがしてくれるものだと何もしません。
それでも頑張っていたA子さんでしたが、ある日こんなことが起きました。うっかりしてその日の午後の予定を長男に伝え忘れていて、楽しみにしていた月一回不定期のゲームの集いにお兄ちゃんが行けないという事態になったのです。
長男はすっかり怒ってしまってこういいます。「お母さんのせいだ。僕はすごく楽しみにしていたのに。お母さんがしっかりしてないから。どうしてくれる?!」
悪かったなあと思い「ごめんなさい。ごめんなさい。」と長男に謝りながらも、怒りをどんどんエスカレートさせる長男にA子さんも思わずこう言いました。
「だって、もともとはあなたのことでしょう?!あなたがわかっていなきゃならないことじゃないの?!」と。
「それなら最初からなぜ僕に任せてくれなかったの?お母さんがやりますからあなたは勉強だけしててね、ってなんでもかんでも自分で手を出しておいて、ミスしたら逆切れ?そりゃあないよ!!」
その時になってA子さんは、自分のしてきたことに初めて変だと気が付いたのです。
子どもためと思ってやってきたけれど・・どうやら何かが違っていたらしい。そう思いました。
それでご相談にいらしたというわけです。
「何が違っていたと思いますか?何かお気づきのことがありましたらお教えいただけますか?」
「長男に言われた一言が引っかかっています。最初からなぜ僕に任せてくれなかったのか?という言葉です。」
「ああ、いいところに気が付かれましたね。任せればよかったとそうお思いになりました?」
「任せてできなくて失敗するよりはと思っていましたけど、本人は自分でできるとやりたいと思っていたのかもしれません。任せられなかったのは私の問題だったのかもしれないです。」
「失敗させたくない。そのお気持ちはすごくよくわかりますよ。でも私たちだって最初から何でもできていたわけではないと思いませんか?」
「そうですよね。自分で失敗してもやって、それでできるようになっていくのですものね。自分が責められてとがめられて初めて気が付きました。任せられることはどんどん子どもに任せればいいんだと。」
「もしかしてそれがご自分のお仕事だと思っておられたのではないかと思うのですが、今回のことはとてもいいきっかけになりましたよね。」
「自分がどうしてこんなに忙しいのかもわかりました。任せることができないばかりに全部子どもをことを自分が引き受けていたからなんですね。」
「これからどうしていかれますか?」
「少しずつでも子どもたちに自分のことは自分でやるよう任せていくことをしていきたいと思います。」
「そうですか。それでは任せて行ってみましょう。自分のことを自分でできるようになるとお子さんはどう思うようになるでしょう?」
「自分のことが自分でやれるって自信につながるかもしれません。人のせいにしたりしないで自分のことを引き受けるって大事なことですものね。自分の抱えていた荷物を下ろせそうでホッとしています。最近ずっと重くて苦しかったんです。なんで自分はこんなにたくさん抱えているんだろう?って思っていましたし。」
「そうでしたか?三人もの子育てですもの大変ですよね。少しは気持ちが楽になられたのでしたらよかったです。」
さて、いかがでしたでしょうか?今まで自分がしてきたことをお子さん自身の手に任せる、お子さんに任せるのは勇気がいることかもしれませんが、任せてやらせてみなければやれるのか、どう助けることができるのかもわかりませんよね。なにより任せなければお子さんが自分でできるようにはなりません。
自分のことを自分でできる、やれるって本当はとても大事なことではないでしょうか?大人になればできるわけではないのです。
子どものころからそうしてこなければ大人になっても自分のことなのに人任せ・・になる可能性はあります。一番苦労するのは本人です。
変だ・・と思ったときが考え時変え時なのです。お気軽にご相談くださいね。
2023・7・29 「お義母さんと比べないで欲しい・・」 愛のタスクのからくりを読み解く

いつも姑と比較されて・・
どうして?
お中元を贈った夫側の叔母から嫌みを言われたA子さん。
「0さん(義母)に聞いてないの?うちはこれ食べないのよ。0さんならちゃんとやるのに。」
夫には「ちゃんとうちの母に聞いてからやればいいのに。。母なら外したりしないよ。」
実家の母には「お姑さんにちゃんと聞いてからやるものよ。お義母さんなら失敗しなかったでしょうに。」
あっちでもこっちでも同じことを言われて、なんだかとてもがっくり来てしまいました。
「お義母さん、お義母さんって。。みんなが口をそろえて同じことを言う。私には私の考えがあるし、自分がしたいようにしたい。それなのにみんなが「お義母さんにきけばいいのに。お義母さんなら失敗しないのに。」って、私をダメな嫁だという。お義母さんと比べられるのはまっぴらよ。
「そういえば夫は何かって言うと、母はこうしたああした、と。食事の味付け、洗濯物のたたみかた、ありとあらゆることを義母と同じようにすることを要求してくる。それならお義母さんと結婚すればよかったのに。。」
A子さんは怒りもありながら自分がなんだかとても価値のない人間のように思えて悲しくなってしまったのでした。
「嫌な気持ちになられましたね。人と比較されるのはとてもつらいことだと思います。ましてご主人のお母さまと比べられたのでは、A子さんの立場もありませんものね。」
「ありがとうございます。なんだかあれもこれもすっかり自信がなくなってしまって、こんなことなら自分で考えないで最初から姑に指示してもらって動いたほうが楽って思ってしまいました。」
「ええ、そうだと思います。まあ、いずれにしても今回のことをきっかけに何をまず改善したいかからお聞きしたいのですが、比較をやめてもらうこと?もしくは姑さんと同じようにすることを要求すること?あたりでしょうか?」
「はい、そうですね。でもまず先生にお聞きしたいのは、どうして主人がこういうことをするのか、ということです。私と姑をいちいち比較してですね、ああだのこうだの言うのはどうしてなんでしょう?」
「なるほど、その辺が知りたいのですね?」
「はい、もしアドラー心理学で説明できるのであればお願いしたいです。」
「わかりました。知ることができたら自分で対処もできるというわけですね。」
「ええ、もしかしたら自分でできるかもしれませんし、納得したらそれはそれでいいやと受け入れることも可能かなと思いまして。」
「なるほど、理解できれば受け入れることも可能ってことなんですね。」
「はい、それなりに理由があると思うので納得できれば、許せる範囲のことは容認したいと思っています。」
「ええと、それじゃちょっと思いついたことがあるので、それで説明してみますね。ジェンダー指針っていうのがあるんです。男性とは~なものだ、とか女性とは~なものだ、といったような、それぞれの人が持っている男性像、女性像です。
その自分の持っている男性像や女性像と目の前の男性、女性が違うと、それって男としてどうなんだとか女性だったらこうあるべきだとか、その指針をもってして相手を裁いてしまう状態になります。
ご主人様の場合には、お母さまが女性像の指針ですから、お母さまとあなたを比較して、ああだのこうだの言うということになってしまっているんだと思います。」
「そういうことなんですか?」
「もちろんそれはあなたにも男性像というのがあって、それでもってしてご主人を裁いている可能性もあるのでどっちもどっちなんですけどね。」
「ちょっと主人が細かいなあって感じるときがあって、男の人がそんなに細かいことを気にするのは嫌だなと思っていたんですけど、確かにうちの父は割と大雑把というかおおらかな人で、その父をモデルにしていたとすると主人を私も裁いていたんですね。」
「よくお分かりになりましたね。ですからお互い様なんですけど、そうやって双方で相手を自分のジェンダー指針でもってして裁いていると仲良くできるかどうか・・・ですよね。」
「はい、先生にアドラーを教えていただいて、夫婦なんだから仲良くするっていうゴールは一致しているので、この話を主人としてお互いに改善するようにしていきたいと思います。」
「はい、そうしてみてください。ご相談いただいて大変私も考えさせられることが多かったですし、復習にもなりました。ありがとうございました。」
男性像、女性像に限ったことではありませんが、自分がもっている価値観や理想をもってして相手を測ったり裁いたりすることは、相手との距離を遠ざけることはあっても近づけることはできません。
ご自分がもしそういう場面に直面しておられるなどの状況がおありになる場合にはご参考になさってみてくださいね。
2023・7・28 「自分のイライラを家族にぶつけないで!」 夫の機嫌が悪いときの神対応

夫の機嫌次第で・・
いつも気を使ってピリピリの我が家
あ、主人が帰ってきた・・。はやくご飯の準備しなきゃ。。お風呂は大丈夫だし。。
今日の機嫌はどうだろう?いいといいけど。。こんな時に限って主人の好きな晩酌のお酒が足りないかもしれない。走って買いに行ったほうがいいかな。。
今日は機嫌がいいみたい。よかった・・。
それがA子さんの日常でした。お子さんが小さくて自分で働くことができませんので、ご主人の機嫌が悪くても我慢するしかないと思っていました。
ある日友人のB子さんと久しぶりに会ってついご主人のことを話したところB子さんからこんなことを言われました。
「それっておかしくない?夫婦なのに、どうしてあなたがご主人に気を使ってばかりいて生活しているの?役割が違うだけで夫と妻は対等だと思うけど。」
「言いたいことはわかるけど、養ってもらってることは事実だし。。」
「家族を養う、お金を出す人がえらいの?あなたに経済力がないから卑屈になっていても仕方がない?」
言われてみればそうだなと思ったA子さんは、自分でも考えてみることにしました。
子どものころからそういえば自分は我慢ばかりしてきたような気もします。それが当たり前になっていて主人との関係でもそうなっていたのかもしれないと思いました。でもどうしたらいいのかわかりません。
やっぱり我慢するしかないのかな・・そう思いながら、過ごしていたところ、ある日度を越したご主人の不機嫌さをぶつけられて、さすがのA子さんも「これじゃだめだ。」と思ったのでした。
ご相談に来られたA子さんは起こった出来事と今までの対応、夫婦関係について話してくださいました。
「今までお話していただいたことを私なりに考えてみたけれども、あなたは何も悪くないですよね。」
その言葉を聞いたA子さんの目から大きな涙がこぼれました。
「自分にも悪いところがあるかもしれない。」とずっと思っていたと言います。
「あなたに悪いところがもしあったとしても言葉で伝えてもらえればいいので、不機嫌という方法を使ってあなたを動かそうとするのはあまりいい方法だとは思わないです。」
「ありがとうございます。」
「一つお聞きしますけど、何かご主人に対して引け目を感じることがあなたにおありですか?」
「引け目はたくさんあります。学歴も違いますし、経済的には主人にすべて負うていますし、いずれはうちの両親のことも見てもらうことになっています。私は一人娘なので。。」
「ああ、そう、そういうことがあったのですね。でもね、それはそれ、これはこれ。いろいろご主人に助けてもらわないといけないことがあったとしても、夫婦としては対等でしょう?今の関係はあなた一人が我慢している状態なので決していいことだとは思えないんですよね。」
「わかります。だからご相談に来ました。何とか出来るなら何とかしたいと思って。。」
「どんな時に機嫌が悪くてそれをあなたにぶつけるの?」
「たぶん会社で嫌なことがあった時にだと思います。それを私でストレス解消してるんだなって。」
「そう、そしてそういう時はあなたはどうしているの?」
「じっと我慢しています。何か反論したり言い訳したりすれば倍になって返ってきてますますひどくなります。」
「そう、それじゃね・・。こういってごらんなさい。」と言ってA子さんに提案した言葉はこんな言葉でした。
「そんなにお仕事つらいの?大変なの?」
試してみて結果を報告してもらうことにしてその日の相談はそれで終わりになりました。
そうしましたらその言葉を言われたご主人が「ギョっつ」として矛先を緩めたと。。
それでは次にまた同様のことが起こったら「お仕事大変なのね。つらさを受け持って上げられなくてごめんね。」って言ってみてとアドバイスを送りました。
それ以来ご主人が不機嫌をA子さんにぶつけることはすっかりなくなったと言います。
普通は不機嫌をぶつけられたらそれに不機嫌で対応することでしょう。でも今回は相手を思いやる勇気づけの言葉で返しています。
それがご主人を変えたたのです。勇気づけの神対応が功を奏したケースでした。
こういうご相談は相談会で承っております。自分では考えつかないことでも必ず突破口が見つかると思います。勇気をもってご相談くださいね。
2023・7・26 「夏休みのイライラは・・すでにMAX」 毎年繰り返される親子戦争を終結したい

朝からイライラ
怒鳴りっぱなし・・を何とかしたい
「まだ夏休みがはじまったばっかりなのに・・・もう疲れてヘロヘロ。。」
2023・7・21 「もう少し・・って焦って走っても電車に乗り遅れる」繰り返し見る夢はライフスタイルの反映

アドラー派の夢分析
2023・7・20 「もしかして・・わざとやってる??」 自分の嫌がることばかりする子ども

主導権争いか?復讐か?
「なんか最近わざと私の嫌がることやってない?」そう中学3年になるお子さんに対してそう感じることの多くなったというA子さん。
「困らせてやる。」そんな子どもの意図を感じるようになりました。
以前はきちんとした子だったのに、やたらとルーズになり、「ちゃんとしなさい。」といってもどこ吹く風で、まったく聞く耳を持ちません。
中学生になり思春期に入っていることはわかっていますが、いくら反抗期といっても平気な顔をして何か言う自分に対して「あなたの言うことなんか聞かない。」という冷たい目を見ると恐ろしいという気持ちになったりもします。
自分の子どもなのに自分の知らない人がそこにいて、冷たい目で私を見ているような感覚に陥ることもあり、親としての自分の存在価値そのものが揺らいでいるような所在のない頼りなさを覚えるようになりました。
自分の親としての価値が危うくなっているというような感覚です。ただの思春期・反抗期とは割り切れない何かがそこにあるような気がします。
そして決定的なことが起こりました。ルーズな格好をしている子どもに「なんなの?その格好は?!」と思わず声を荒げたA子さんに対して、中学生の娘は「にやり」と不敵な笑顔を返したと言います。
「ゾッとしました。。」ご相談にいらしたA子さんは、そんな風にお気持ちをお話してくださいました。
「そうでしたか。。ゾッとされたんですね?」
「ええ、そうなんです。我が子ながら、怖いと感じました。何を考えているのかわからないことが、最近本当に多くて、そんな中でのとても冷たい馬鹿にしたような顔で笑ったんです。」
「ショックだったでしょうね。どうしてそういう顔で自分を見るの?って思われたのではないでしょうか?」
「はい、私は私なりに一生懸命子どものためと思ってやってきましたから。それを全部否定されたような、というか自分という存在というか、親という存在というかを全部否定されたような気がしました。傷つきました。。すごく傷つきました。。」
「わかりました。傷ついたと感じられたんですね、ちょっとアドラー心理学で今起こっている出来事を説明してみますね。
<親の反応・感情で子どもの行動のねらい・目的を見る>
アドラー心理学ではお子さんの不適切な行動、この場合には親の言うことを全く聞かずにわざと嫌がることをする、冷笑を向ける、といったようなことが該当、についてみるときに、その行動を見て親がどう感じたのかを目安にお子さんの目的「狙いは何か?」といったことを推し量っていきます。
たとえばお子さんの不適切な行動を見て、親がイライラするのであれば、お子さんの行動の狙いは「注目を得ること」であるという風にです。
「打ち負かされた」と感じれば「主導権争い」ですし、「傷ついた」と感じれば「復讐」、そして「もうお手上げだ」と感じれば「無気力の誇示」になると考えます。
これは段階を経て勇気をくじかれている度合いが深いという見立てをします。A子さんの場合には「傷ついた」と感じておられるので、お子さんの不適切な行動の目的は「復讐」になるかもしれないという見立てになります。
それだけ「勇気をくじかれている」という解釈になりますので逆の対応「勇気づける」対応に変えていくしかありません。
勇気をくじかれた子どもは親との関係のみならず自分の人生に対しても破壊的な方向に行くことが多いのです。そして自分が一番傷つきます。傷つく方法を採ってしまうのが子どもです。
それを助けてやれるのは身近な親の勇気づけしかないのです。
<勇気づける親になる>
説明を聞いたA子さんは、自分の対応を振り返ってこうおっしゃいました。
「良かれと思っての指摘があの子の勇気をくじいていたのですね。考えてみればできていないところばかりつついて指摘して指導しようとしていたような気がします。」
「もうA子さんのお子さんぐらいの年齢になると自分で考えて自分の思い通りにしたいと思っているのですよね。ところが親は小さいころからの対応を変えないでそのまましているので、それが今になってA子さんが傷ついたという反応になって返ってきていると言えばいいかなと思うんです。お子さんの成長に合わせて親も対応を変えていく、この発想がなかなか難しいと感じています。」
「そうなんですね。子どもが成長してるのに親はいつまでも子どもの頃のままの対応していたら子どもだっていやですものね。アドラー心理学ってずいぶんシンプルに考えるんですね。」
「ええ、わかりやすくていいと思っています。どんなにこんがらがった事象もするすると紐がほどけるように説明できるんです。
勇気をくじかれてそうなっているんだから勇気づけるんだという、とても対応もシンプルです。でも一口に勇気づけるって言っても深くてこれが身につくのはなかなか大変なんですけどね。やってごらんになりますか?」
「はい、自分の置かれている状況もはっきりと説明していただきましたし、すべきことやれることがあるというのはとてもうれしかったです。ぜひ勇気づけを学んでやってみたいです。」
「お子さんとお子さんの能力を信じて挑戦していきましょう。必ず関係は変わりますから。。」
「はい、ありがとうございます。」
真っ暗なトンネルからその先に希望の光を見出したA子さんは、少しほっとして明るい顔になり、ご相談からお帰りになりました。
「勇気をくじかれてそうなっている。」お子さんの不適切な行動はこの理由につきます。シンプルでありながらとても理にかなっていると私自身は感じております。
アドラー子育て法を通して「勇気づける親」にあなたもなりませんか?
2023・5・9 「みんなと同じでなければ私はダメな人間なの?」

どうせ帰省したって・・・。
GWとうとう故郷へ帰らないという選択をしてしまったA子さん。
職場の不測自体の待機組に自分から名乗りを上げて、実家への帰省をしなくて済むようにしたのでした。
どうせ帰ったって・・・とそんな気持ちでいます。
わたしだけが結婚もしないで仕事をしている、ほかの兄弟はすでに子どももいるというのに。。
普段から実家の母親から頻繁に、結婚についての促しやら、ため息交じりの「なんでおまえだけ。。」といった愚痴やらを電話で散々聞かされているのだから、コロナ明けで帰れば、今度は直に言われるだろう。
最近は電話にも出なくて済むように残業も増やしています。今回の帰省見合わせも他の兄弟の前でそれを言われるのはたまらない、そう思ったので帰らないという決断をしたのでした。
言われるたびに思います。
「私は誰にも迷惑をかけずに一人でちゃんと生活している。結婚しないことがそんなに悪いこと?普通に一人の人間としてすべきことをして生きているだけなのに、」
お前はダメだダメだと言われているようで、腹が立つやら悲しいやら。。
でもそれを母に言ったところで母は言うのをやめないだろうし、親の言うことを聞かないなんてと逆に怒られてしまう。
ますます嫌な気持ちになる。。
だから距離を取ろう。。。そう考えるようになりました。
これ以上自分はダメな人間で価値がない人間でと思うのは耐えられないと感じたからです。
そしてこうも思います。「人と同じでないことはそんなにいけないことなんだろうか?」と。
まるで罪人のように感じることすらあります。とA子さんは苦笑いをしながらお話をしてくださいました。
「あなたのお話をうかがっていて人生の決まったレール・・なんていう言葉を思い浮かべました。」
「あ、先生そうそうそんな感じです。レールに乗せたい親と乗りたくない私ですよね。」
「そうそう、すごくよくわかります。私も乗りたくなくてね。」
「そうだったんですか?」
「ええ、反抗ばかりしていました。」
「でも今は親御さんと仲良くされているんですよね?」
「仲良くっていうか、それなりに嫌な気持ちにならずに付き合えるようになったって感じです。」
「どうしてそうなれたんですか?」
「う~ん、親に悪気がないってことと、親は変わらないってこと、あとは過干渉っていう子どもへの関わり方・方法が良くないだけだ、って思えるようになったからでしょうか。」
「そんなものでしょうか。。」
「いや、時間はすごくかかりましたよ。最後の行為と行為者を分けるって方法なんですけど、これがなかなかね。」
「行為と行為者を分ける、ですか?」
「ええ、アドラー先生のお弟子さんでドライカースというアドラー心理学者が著作の中で提唱しているんですけど、方法は良くないけど、人としての価値は変わらないのだから、行為と行為者、方法と方法を使っている人を分けて考えましょうって言っているんです。」
「へえ、そんな方法があるんですねえ。できるかなあ。。」
「たとえば職場で嫌な人がいませんか?」
「います、います。すぐ怒鳴る上司とか。。」
「怒鳴るって方法はあまり良くないですよね。私たちって怒鳴る人って考えがちだけど、でも怒鳴るっていう方法を使っているって考えるんです。その方が怒鳴るときってどんな時で怒鳴るとどうなります?」
「仕事がうまくいっていないときに、社員のお尻を叩く感じです。」
「そうすると社員に仕事をうまくいくようにやってもらいたくて怒鳴るって方法を使うわけね。」
「あ、なるほど、そう考えるんですね。。」
「怒鳴る以外の方法使ってくれないかなあって思いません?たとえば頑張ってくれてるのはわかるが、もう少しプラス頑張ってくれないか?みたいな言い方だとどうでしょう?」
「はい、そう思います。そうしてくれれば頑張れるのに。。」
「方法さえ変えてもらえれば上司の方だってそんなに嫌じゃないでしょう?親も方法代えてくれるといいんだけどね。」
「あ~、親のこともそういう風に考えていけばいいんですね。」
「まあ、徐々にだけども、そういう風に分けて考えられるようになるとほぼほぼ誰かや何かに腹が立つってこともなくなるんですよね。一つの選択肢としてやってみる価値はあるかもしれないです。」
「ありがとうございます。考えてみますね。親を嫌ったままでいたくないので、やってみたいです。」
「あなたは優しいですよね。あなたの「嫌いたくない」って気持ちが親御さんに通じるといいんだけど。。まあ時間はかかるかもしれませんが、いついつまでに答えを出さなきゃいけないっていう問題でもないのでやってみたらいいと思います。」
突破口のヒントをもらったA子さんは、なんだかとてもうれしそうに見えました。
行為と行為者を分けるということは日本の故事成語にもあります。「罪を憎んで人を憎まず」
逆の意味ですと「坊主憎けりゃ袈裟まで」でしょうか。
一つの考え方のヒントとして採用してみるといいかもしれませんね。
2023・5・3 「かわいそう‥って言わないで」見下しの心理

タテ関係から生じる
見下し
よく耳にする「かわいそう」という言葉。今回はその言葉の意味について書いていきます。
A子さんは、お仕事が大好きで毎日充実した生活をしていました。結婚して5年になりますが、結婚してすぐに婦人科の病気をしたことでお子さんが授かりません。
子どもがいなければいないなりに自分の生活には十分満足しておられましたし、仕事もつい最近役職に抜擢されたりやりがいを感じてさらにステップアップしていこうと思っていた矢先、同僚にこんな言葉をかけられました。
同僚とは同期入社ですが、結婚出産を機に彼女は入社当時とは置かれた立場も違ってしまい、会う機会があまりなかったのですが、久しぶりにランチの場で一緒の席に座ることになりました。
「ひさしぶりね。同期で最初に女性で役職に就いたのはすごいわねえ。。」
「うれしいしやりがいもあるけど、まだこれからの頑張り次第かなって思ってる。。」
「ところで、どう?子どもまだ?」
またその話・・・会う人会う人にその質問を聞かれて、うんざりとは思いましたが、
「ええ、婦人科の病気をしたこともあるから別に持てなくてもいいかなって思ってるの。。」
「持たないの?なんで?」
なんで・・・って、そんなこと聞かないでよ、困るなあ。。なんて返事しようと思っていたところ突然こんな言葉が彼女に降りかかってきたのです。
「かわいそうに。。。」
ギョッとしたA子さん。。。言葉を失ってしまいました。。
かわいそう?私はかわいそうなの?子どもを持てないから?
何だろうこの嫌な気持ちは。。。そう自分の気持ちを量りかねている間にそれは怒りに変わっていきました。
「別にわたしはかわいそうなんかじゃありませんけど?!」と強い言葉が彼女の口から出ました。
「いや、別にそれならいいんだけど。。。」と口をモゴモゴさせながら「じゃ、またね。」と気まずさを感じた同僚はランチ途中でそそくさと席を立ってしまいました。
嫌な気持ちだけが残りました。
どうしてだろう?どうしてこんなに嫌な気持ちなんだろう?そして相手との関係もこれまでとは違った距離を感じてしまったのです。
もう以前のような関係とは別のものになってしまったと思ったのです。かわいそう・・・というたった一言で。。
「彼女はあなたに勝ちたかったのよ。。」
「そうなんですか?」
「仕事ではあなたが上。だけど子どもを持てたことは自分が上。自分が全部あなたの下にいるわけじゃないことで自分のプライドを守りたかったのだと思うの。。」
「プライドですか?」
「そうね、対他者で失いたくないものがプライドですからね。同期で入社して対他者で全部自分が下って思うのは嫌だったんじゃないのかな。。」
「そんなものなんですかね。。」
「他者と自分を比較して劣等感を感じて生きているとそういうことは結構起こり得ると思うの。できれば劣等感は対自分で持てて自分を高めるために使えればいいのだけれど。。」
「それじゃ私は低められた・・ってことになるんですね。。」
「うん、そうすると相手は相対的に上がりますから。単純な構図、シンプルな方法でしょうね。嫌な気持ちだったと思うけど、相手は自分があなたより下だと感じて部分的にでもあなたを下げることで自分を上げたかった。。ってこと。」
「そっかあ、、、。わかってみれば理解できないこともないかなとは思います。嫌な気持ちになったのは自分が下げられたと感じたからなんですね。上から見下されたというか。。」
「かわいそうって言葉は意外と使っている方おられるけれど、相手を引き下げて自分が優位に立つ言葉だから気を付けたほうがいいでしょうね。」
「なんだかすっきりしました。そっか、それで嫌な気持ちだったんですね。。」
「その方のこと理解できれば、多少なりとも今まで通りに振舞えるかな?」
「はい、大丈夫だと思います。ますます仕事頑張ります。」
陰性感情を手掛かりにその状況を読み解くことで自分のことや他者のことが見えてくることは多いものです。
陰性感情は他者関係に有益に使うことができます。
持っていけないのではなく、どう解釈しどう使うかが大事です。
今回のように、アドラー心理学を使って読み解くことができればそれはこれからどうすればいいのかの手掛かりにもなります。
あなたの中に沸き起こる感情に役に立たないものはないのです。
2023・4・27 「どうせ自分なんか‥いてもいなくても同じ」 不登校相談・居場所があるという感覚の意味

自分には居場所がある
価値がある、能力があるという感覚を持てているかどうかが大事
お子さんが学校へ行かなくなり、ほぼ1年が過ぎたころ、あれこれ手を尽くしたけれどもなんともならずうちへご相談にいらしたA子さん。
「お友達に協力してもらったり、学校の先生にも一生懸命やっていただきましたし、スクールカウンセラーの方にもたくさんご相談に乗っていただきました。でもやっぱり子どもは学校へ行こうとしません。
その間毎日今日は行くか明日は行くかと期待と失望の繰り返しの日々を送ってきました。でも明日は行くと言ってもその日の朝になると起きてこないんです。
無理強いをしてもダメだということはわかっています。なのに焦って何とかしようとする自分がいて、自分の気持ちの持って行き場がなくなりました。
行かなくてもいい、そう思えれば楽なのに、そう思えず子どもに期待してしまう自分がいて苦しくてたまりません。」
「そうですよね。親としてはほかのお子さんと同様に進んでもらいたい、そう思うのは当然だと思います。なぜうちの子が他の子と違うのか、もしかしてご自分を責めていらっしゃるのではありませんか?」
「親として失格ではないか。。という気持ちになることはあります。自分だけが親の世界からはじき出された気持ちです。」
「親の世界からはじき出された気持ちですか?」
「はい、ほかの親御さんのご家庭はちゃんと子育てをしていて、お子さんはみな普通に学校へ行っています。その中からはじかれた気持ちがします。」
「はじかれるという感覚はどういう感じがしますか?」
「自分の居場所がない感じです。自分には価値がない、親としてすべきことができていない、そんな感じです。」
「もしも親というグループがそこにあるとすれば自分の居場所がそこにない感じですかね?」
「はい、いる資格がない、というか。。だから親の集まりにも行けないでいます。」
「それねえ、お子さんに当てはめて考えてみると、同じ状況かなと思うんです。」
「同じ状況ですか?」
「親の集まりに行けないと感じているあなたと、学校へ行けないでいるお子さん。そう考えてみるとお子さんの気持ちが少しはわかるかもしれませんね。」
「学校に居場所がない、自分には価値がない、学生としてすべきことができていない、と。。子どももそう感じているってことですか。」
「そうかもしれません。あくまで推測ですけどね。居場所がないって感覚って自分の存在価値にかかわる結構大事な問題なんです。」
「そうなんですね。。初めて実感しました。」
「そうすると居場所がある、自分には価値があると思ってもらえればいい、ってことになるかな。。。」
「どうすればいいんでしょう。」
「やれることはたくさんあるんです。まず今のご家庭をお子さんに自分の居場所だと思ってもらうことが先決です。今のご家庭がお子さんにとって居場所だと感じるところになっているかどうか。。についてはどうですか。。安心しておうちでは過ごせているんでしょうか。何でも話せて仲よくやれていますか?」
「つい学校についいて聞いてしまったりしているので決して心から安心というわけではなかったかもしれません。。」
「学校に居場所がないと感じて学校へ行かなくなった。家庭でも居場所がない状態というお子さんが増えていてね。いわば心のホームレスな状態というか。。これはとてもつらいことでね。実は私は仮面登校の生徒だったので。学校にも家庭にも居場所がないと感じて、どこにも行くところがなくて仕方なく学校に行くしかなかったという状況が何年か続いたことがあります。お子さんに居場所を作ってあげたいと私は思うんですけど、どうでしょう?ご家庭の居場所つくりからまず一緒にやってみませんか?」
「居場所つくりが今のあの子には必要なんですね。。」
「そう、自分にはちゃんと居場所があって価値があるんだと、感じてもらいたいと私は思っています。」
心のホームレス。今回のケースに限らず誰でも陥る可能性はあるのです。大人でもそうです。会社で社会で居場所がない。家庭内ですら居場所と思えない。
居場所があるという感覚を持てていることはそれほど私たちにとっては大事なことでもあります。
今ご自分にはいくつ居場所がありますか?
誰もが居場所を持てるそういう環境を作っていくことも私たち大人ができることの一つではないかとそう感じているこの頃です。
2023・4・25 「せっかく~してあげたのに。。」親の世話好き・善意の押し付けをかわす方法

親との関係を悪くせずに
緩やかに介入を減らしてもらう
「せっかく言ってあげたのになんで言うとおりにしないの?」
「せっかくやってあげたのに、なんでお礼も言わないの?」
こんな風に言われたことはありませんか?
「~してあげたのに。」という言葉の響きをどう感じられるでしょうか?
「善人はなぜ周りの人を不幸にするのか?」確かにあの人はいい人なんだけど。。
という曽野綾子さんの本を読んだ時のことを思い出しました。
今回は善意をどう捉え、善意の人にどう対処していけばいいのかについて考えていきます。
Aさんは結婚して2年になるまだまだ新婚さんのご主人です。
結婚当初から自分の母親が自分たち夫婦に対してあれこれと口を出すのに困っていました。
結婚前はあれこれ世話を焼いてもらって助かると感じたことが多かったと言いますが、もうすっかり二人の生活に慣れたこともあり、自分たちのペースでやりたいと思いつつ、結婚前と変わらない自分の母親の態度がうるさく感じられるようになったそうです。
奥様も姑に言われれば無下に無視もできず、かといって最初のころはAさんに文句を言うのも自分の親を悪く言われたくないだろうと思って言えず困っていたと言います。
ところが、先週になって母親がこんなことを言い出したと。
「早く子どもを作りなさい。いつまで待たせるの?いい病院があるから紹介するから行ってきなさい。連絡しておくから。」と言われたことをきっかけに、これは何とかしないとと思うようになったそうです。
Aさんご夫婦には結婚当初から二人で考えているプランがあり、子どもを持つことについても夫婦でいろいろ話し合っているので、いきなりのその発言には面食らったと言います。
どう対処していいのか迷ったこともあって言われたことをとりあえずスルーしていたところ、母親はどんどん「まだ?まだ行かないの?」とエスカレートし、最後には怒り出したんだそうです。
なんで言われた通りにしないの?
せっかく先方の先生にも連絡を入れたのに。。
なんでお礼も言わないの?
本当に失礼ね。
「困ってしまって。。」とAさんは頭を抱えておられました。
「なるほど、せっかくの二人の生活をかき回されている感じですか?」
「はい、全くその通りです。世話好きで悪い人じゃないんですけど、ちょっと度が過ぎていると思うんです。」
「でしょうね。奥様もお困りでしょう。」
「はい、自分がなんとかしないとと思いました。自分の親のことですから。このままでは妻との関係も悪くなりかねません。」
「奥様はとてもお優しい方のようですね。奥様とのご関係はご心配はしなくてもいいような気がしますが、よくご自分で、とお考えになられましたね。」
「はい、僕たちの生活を守りたいと思いました。」
「わかりました。それではどうなるといいと思っておられますか?」
「虫がいいようですが、母との関係はできるだけ悪くしないようにしつつ、介入を控えてもらえる方法があればと思います。」
「だとするとアドラーのやり方だと緩やかに課題を分けていくという方法がいいかなと思います。」
「緩やかに課題を分けていくのですか?」
「はい、そうです。今10の介入があってそれを、9に8にと少しずつ減らしていかれるようにしていけばいいのではないでしょうか。」
「そんなことができるのでしょうか?」
「お2人の生活にお母さまが介入してくるのは、同居されているわけではないので課題分けからするとルール違反です。課題に踏み込むほう、踏み込ませるほう、双方に問題があります。お母さまは変えられないという前提で、こちらから課題に踏み込ませないように少しずつしていけばいいのです。」
「踏み込ませない。。」
「でもやんわりとやればいいのですよね。たとえば何か電話で言ってきてああしろこうしろと言われたときにどうしましょうか?」
「できない、したくない。。だと、相手が傷つくし怒りますよね。」
「そうですね、いったん受け入れる言葉を入れてみたらどうですか?」
「ああわかったよ、みたいなですか?」
「そうです。母さんの意見はわかったよ、ですね。そのうえであとは自分たちで考えて決めるから。連絡くれてありがとう。でしょうか。」
「なるほど。それでその通りにしなくて文句を言われたら?」
「私なら、自分たちで決めたことなので意に沿えなくて申し訳ないが意見としてはありがたかった、というような言い方をしますかね。」
「なるほど、そういうことを繰り返していくのですね。」
「そうです。その繰り返しでしばらく対応していけば、自分が何を言っても若い二人が自分たちで決めることが相手に伝わります。自分の思い通りにならないこともわかっていくでしょう。やってみられますか?少し時間はかかりますが。」
「はい、それぐらいの感じならできそうです。助かりました。また経過を見てご相談させていただくかもしれません。」
「あなたは奥様思いの方ですし、お母さま思いの方ですね。双方のお気持ちをどうしたら傷つけないで済むかとお考えになられるところなどはなかなかできることではありませんもの。素敵なご主人さまであり、素敵なお子さんでいらっしゃる、のですね。こちらもとてもいい勉強をさせていただきました。ありがとうございます。」
課題を分ける、そして運用する際に大事なのは、どの程度の介入が現在あり、どう分けていくかです。それは一人一人違います。
共同に課題にするのも一人一人状況に応じて運用していかなければなりません。
課題に踏み込んでこられて嫌だという方には、緩やかな分離がお勧めです。分けることで相手を傷つけてしまってはアドラー心理学の実践としては本末転倒になります。
個々の実情に合わせての臨機応変な対応が求められるところです。方法に困っておられる場合にはサポート会や個別相談をご利用くださいね。
2023・4・24 「この人に何を言っても無駄!!」夫へのあきらめ・ それでいいの?

どうせ言ったって・・
って思っていませんか?
ご主人に対して「何を言っても無駄!」と、お感じになられている奥様のご相談です。
配偶者に対して特に結婚生活が長くなればなるほどこういう状況に陥る方は結構おられるようです。
聞く耳を持ってもらえないと思っておられるのですね。
あまり主張が得意でない方は、一度言ってもうまく行かなくて、たとえば逆に言われてしまったとか、うまく伝わらなくて喧嘩になってしまったとか、嫌な経験が積み重なると、嫌な思いをしたくなくて言わないという選択肢をとられてしまいます。
主張をすると嫌な思いをするかもしれないという恐れがセットになっているのです。
こういう状況になると言わないでおこうというサイクルに陥ってしまいます。
「何か言うと睨まれているような気がするんです。委縮してしまって言えなくなります。」
ご相談者のA子さんはこうお話を切り出しました。
「この間もちょっとお金の入用があって言おうかなと思ったけど、何に使うの?とかいろいろ聞かれたり説明するのが嫌で自分で出してしまいました。」
「ご主人はお金にどちらかというとシビアな方?」
「いえ、そうではないです。割と自由にさせてくれています。でも言い出せない自分がいて、言ったらどう思われるだろうとか、なんていえばいいかとか考えるとそれだけで疲れちゃうんです。」
「あ~、なるほど、考えすぎてしまうんですね。」
「はい、そうなんです。あまり主張が得意でないから、何ていおうってすごくかんがえてしまいます。」
「我慢は体に毒だわね。」
「そうなんです。先生のようにさらっと言えたらどんなにいいかといつも思います。」
「私だって初めからこうだったわけじゃないんですよ。誰に対しても言っても無駄だから言わないでおこうって長いことそう思っていました。」
「そうなんですか?」
「ええ、子どものころ親に対しての主張をあきらめていた自分がいて、でも今私の周りにいる人たちは親とは別の人たちで、いえばわかってくれる人もいるんだなあって気が付いたから言えるようになったんです。」
「あ~、私もそういうことあるかも。。親に何か言ってもピシャっと閉じられちゃったり、耳を傾けてもらえなかったりって結構あったので。。」
「言っても無駄って思ってる?」
「はい、言っても無駄って思う自分と言いたい自分がいて、でも考えすぎて疲れて言わない方を選択してるかなってそう思うんです。」
「言っても無駄って思っていると、言ってもダメだったっていう経験ばかりを記憶に残すんです。私たちの脳ってそういう風にできてるからね。そうするとうまく行かなかった記憶ばかりが蓄積されていく。そうしてますます言わないという選択をとるようになるんです。」
「そうなんですね。」
「だから言っても必ずしもうまくいかないことばかりじゃない、ってぐらいに変えていければいいですよね。たとえば、今までうまく主張ができないなりにご主人にお願いしたことがたくさんあったと思うけど、全滅でしたか?」
「全滅・・・ではありません。」
「ですよね。うまくいかなかったことだけ記憶しているはずです。うまくいったことは記憶に残らないってだけのことです。」
「なんか、自信がわいてきました。あのお、一つ以前から主人に言いたくて言えないでいることがあるんですけど、一緒に考えてくださいますか?」
「はい、もちろん、喜んで。。」
その後二人でいろいろアイデアを出し合い工夫を重ねてやってみる気になられたA子さんは、とても楽しそうなお顔をされていらっしゃいました。
無駄だと思い何もしなければ傷つくことはありませんが、何も変わりません。
無駄かどうかはやってみなければわからないのです。一人に対して無駄だからと言ってほかの人にも無駄だとは限らないのですから。
チャレンジのお手伝いはいつでもしたいと思っております。ご相談にいらした時点でもうチャレンジの気持ちは持っていると私はいつも考えております。
2023・4・20 「不安なの。不安でたまらないの。」不安という感情は自分を守る方法

自己流で対応できないわけ
「私、不安なの。。不安で不安でたまらない。。」
不安を訴える母親、その目的とどう対応すればいいのかについてお伝えしていきます。
A子さんはすでにご家庭を持ち優しいご主人と二人暮らしをしています。
最近になって実家の母親が頻繁に電話をかけてくるようになりました。
そしてしきりに不安を訴えると言います。
「何が不安なの?」と聞いては見ても、本人もさっぱりわからないんだとか。父にも、「子どもたちだって立派に皆が自立して問題もないし、経済的にも何も問題ないのに何がそんなに不安なんだ?」と言われて、でも本人はしきりに不安を訴えて辛そうだと言います。
困り果ててご相談に来られました。
「どうしたらいいでしょうか?」開口一番A子さんはそう切り出されました。
「そうですね。どうするかの前に目的を考えてみましょうか。」
「目的ですか?」
「そうです。アドラー心理学で考えると感情は何らかの目的があって使われると考えます。自分を操作するためか他者を操作するためです。自分を何らかに動かそうとするために不安を使っているのか、他者を何らかに動かそうとするために不安を使っているのかです。どちらだと思われますか?」
「そうだとすると自分…ではないと思うんです。他者かもしれません。」
「他者ですか。。。なるほど、誰を動かそうとしているんでしょう。」
「誰ですかね、私か父か。。」
「そう、そのどちらかでしょうね。何かお母さまは身近に問題を抱えておられますか?思い当たることは?」
「そういえば母の実の弟がずっと入院していて危篤の状態が続いていて長くないようです。」
「お母さまの弟さん、ですね。弟さんとお母さまの関係はどうなんでしょう?」
「母は実家をとても大切に考えています。それは子どものころからそうでした。自分の家を放り出しても実家のことを優先するような人でした。実家で以前金銭トラブルがあって存続が危なくなった時も心ここにあらずといったような精神的におかしくなったぐらいです。」
「そう、そうすると弟さんがこのままなくなってしまうと、実家がなくなってしまう、大事な居場所を失うということにお母さまはなられますよね。そこかなと思うんです。」
「あ~、あるかもしれませんね。母のプライドの拠り所みたいなところがあるので。」
「だけれども、自分では何もできないと感じて、誰かに何とかしてくれと、その辺あたりかなと。。」
「そんなこと言われてもどうしようもありませんよね。」
「そうなんですよね。自分で課題に取り組まない人が不安という感情を使って他者を動かし何とかしてもらって自分を守ろうとすることはよくあるんですが、今回は誰もどうしようもない。。だけれども不安を使い続けることでしか自分を守れないと感じているかもしれません。」
「自分を守るため?なんですね。」
「そうです。守るために不安という感情を使っている可能性があります。さて、いずれにしてもこのままではご自分の感情にお母さまがつぶされてしまう可能性があるので、さしあたって心療内科の受診を勧めて見られてはどうでしょうか?」
「はい、以前から何度か勧めたのですけど、本人がその気にならなかったのです。でも、最近になってつらすぎるので行きたいと言い出したところです。」
「そう、それならそれで様子を見ましょうか。お薬の処方で不安そのものはだいぶ抑えられると思います。A子さんも大変でしょうけど。」
「これから先も介護を含めて母とは付き合っていかなければなりませんから、長い目で見て今はその方法をとることでいったん落ち着いてもらえればいいかと思っています。」
「A子さんがお子さんのころからお母さまは不安を訴える方でしたか?」
「不安についてはあまり覚えていないのですけど、先ほど先生がおっしゃった自分が動かずに他者を動かす、については思い当たる節があります。子どものころ、なんでこんなことを私にやらせるの?と思ったことが何度かありました。自分でやればいいのに、って。」
「それは本来はご自分がすべきことをあなたにやらせるということですか?」
「はい、そうです。自分でやればいいのにって思うことを私がやらされたことが何度かありました。」
「今あなたはそばにおられないからねえ。かといってプライドが傷つくのは嫌で自分を守りたいだろうし。不安を使うしかないのかな。いずれご自分に自信がなくて、課題に取り組めないと感じていることは確かなようですね。でも今からお母さまを変えるわけにはいかないことはご理解できますよね?」
「はい、もう80ですしね。母は母のままでと思っております。今回はほんとうに助かりました、ありがとうございました。」
「こちらこそお母さま思いのあなたに大変勇気づけられました。ご相談いただきありがとうございます。」
課題に取り組めない、自分にはその能力がない、誰かにしてもらわなければならないと感じている方は、不安以外にも様々な方法を使っていることが多いです。
勇気づけという方法は、あなたには自分でできます、ということを伝えるメッセージの役目もあります。不安という感情はそれを教えてくれる大事なサインです。
目的が何にせよ、私たちに起こることに意味のないことは一つとしてありません。ご自分の心に向き合うことで自分を楽にすることができるのです。今回は当事者ご自身のことではありませんでしたが、自分で自分の感情と付き合えることがアドラー心理学を学ぶことの一つの大きなメリットでもあるのではないでしょうか。
2023・4・9 子育てに悩む人の共通の思い 「今のやり方では駄目だということはわかる。 でも、どうしたらいいのかがわからない。」

自己流で対応できないわけ
「ここにこう書いてあるのに、なんでうまくいかないの?!」
「やってもやってもかえって悪くなっていくような気がする?」
「ほんとにこれでいいの?大丈夫なの?」
子育ての本を片手にそう思っておられませんか?
アドラーの子育て本のみならずあらゆる子育ての本を探して読んで一生懸命やっているのにうまくいかないという方は多いです。
書いている通りにやっているのにどうしてうまくいかないのか、それどころかかえって悪くなっていくような気がする。
2023・1・12 「なんでもっと早く出さないの?!」ぎりぎりになって提出物を差し出す子どもにイライラ

もうっつ!いつもこうなんだから・・
からの卒業
Aさんは、いつもいつもぎりぎりになってから提出物を差し出してくる子どもさんに今朝も怒ってしまいました。
「お母さん、これ今日までだった。もう出かけるから親の記入するところだけでいいから早く書いて。」
「ええっつ?こんな大事なものなんでもっと早く出さないの?すぐになんか書けませんよ。」
「いいじゃん、適当に書いてさ、持ってくから早くしてよ。」
「適当でいいとか言わないでよ。学校に出すものなんだからちゃんと目を通して書かないと、でしょ。ママだってもう出かけなきゃならないんだから、いつもいつも肝心なものをぎりぎりになって出してきていい加減にしてよ。」
「じゃいいよもう。書いてくれなくてもそのまま出すから。俺も遅れるからもう出かける。先生には親が書くのを拒否しましたって言ってやる。」
「しょうがないわね。ちょっと待ってなさい。」と言ってAさんはその場でかけるだけ書いてお子さんに持たせましたが、いつもいつもこの手で押し切られる自分と自分をごり押しして思うようにする子どもに腹の虫がおさまりませんでした。
親には親の都合があるにも関わらずそれを理解しようとせず自分の都合を押し付けてきて最後には脅しまでかけて要求を通そうとする子ども、が浮かび上がってきます。
自分の都合でごり押しすれば要求は通ると学んでしまっていますね。
相手への配慮・他者への関心が欠けている状態にもなっていると言えます。
有無を言わせないぎりぎりになってというのも困ってしまいますよね。
もともとその提出物は本人の課題ですから、親に受け持ってもらう分共同の課題にしてもらわなければならないのですが、その手順がなく勝手に押し付けていることが問題になるでしょう。
これは普段から課題を分けることと共同の課題にすること、その手順に沿って物事が進められていないから起こることでもあります。
簡単に言うと「協力とはどういうことなのか?」が家族間でできていない状態になります。
実際にお話をお聞きすると課題分けと共同の課題にすることはもちろんですが、協力ということが行われていないことがわかりましたので、分け方と共同の課題にする方法、家族間の協力とはどういうことなのか?をお伝えして日々の細かいところから実践していただくことでこういう事態も解消されていきました。
お子さんに限らずご家族の中で誰かが自分の都合だけで自分の要求を通そうとする場合、誰かの我慢や犠牲が生じている可能性があります。
その際には家族間の協力とはどういうことなのかについて話し合うことも必要になってくるでしょう。
協力とはゴールが明確でそこへ向かってグループの皆ができることをしていくこと。
リスクを等分にメンバーが受け持つこと。
その辺を考えながらやっていかれるといいのではないかと思います。
その際にはくれぐれも原因論に陥って「悪者探し」「犯人捜し」「追及」にならないことも大事です。
ご参考になれば幸いです。
2023・1・6 「親だって傷ついている」

笑顔を取り戻すお手伝い
疲れ切って悲しい顔をしてしかもはじめていらっしゃるときには緊張をして私のところへご相談に来る方がほとんどです。
お子さんのことやご夫婦の事、ご自分の親との関係など人間関係の悩みは誰にでも起こってあることなのですが、まずその問題を何とかしようとしがちですけれど、その前にご自分が深く傷ついていることに気が付いて欲しい、今回はそういうお話です。
A子さんは、お子さんの不登校や引きこもり、暴言などで悩んでご相談にいらっしゃいました。
疲れ切ったお顔をしてもうどうしていいのかわからない、打つ手がない、藁にもすがる気持ちで来ましたとそうおっしゃいました。
なんとかしようとするほど事態は悪化していく、でも何かしないではいられないんだと。
ダメだと思いながらつい声を荒げて子どもとけんかになってしまう。その繰り返しで疲れてしまっていると、そうおっしゃいました。
どこへ相談しても「様子を見ましょう。」と最後には言われる。様子を見るって?このままでいいの?親として何もしなくていいの?と焦りばかりが募っていく。
苦しさを語るその姿は親であるゆえに深く傷ついている一人の人間を見せられた思いがしました。
「お疲れになりましたでしょう。でもよくいらしてくださいましたね。」
労りの言葉など想像だにしなかったA子さんの目から涙がこぼれ落ちました。
「怒ると自分も疲れますよね。よくわかります。でも何とかしたくて怒るんですものね。」
「怒ってもいいんですか?怒ってばかりの私でもいいんでしょうか?」
「ええ、それしか方法がなければだれでもそうしてしまうと思います。ほかの方法をお教えしますのでそれに徐々に変えていけばいいので、まずは自分は自分なりに一生懸命やってきてしかもそのことで深く傷ついているんだということを自分に認めてあげたいですね。」
「うれしいです。そういっていただけると。母親のお前が悪いんだと両親や主人から責められるばっかりで自分はダメな親かもしれないけど、自分一人が悪いのかと、そんなに私はダメなのかと、そう思ってきました。」
「そんなことはありませんよ。悪くしようと思ってする人はおりません。本来ならば家族みなで協力して取り組むべきことを一人だけが悪者になって余計お辛かったですね。」
「ええ、誰も誰も私を批判はしても助けてくれようとはしませんでした。理解してくれようともしませんでした。私は一人でした。独りぼっちだったんです。」
「もう大丈夫ですよ。これからは一緒に歩んでいきましょう。あなたには親としてお子さんにできることがたくさんあるんです。さて何からやりましょうか。」
会場を後にするA子さんの希望が見えて少しだけでも明るく軽くなったお顔。それはいつも相談会で見る方たちのお顔でもあります。
今年もそういうお顔を一人でも多くの方に得てほしいとそう思っております。
2022・12・28 「繰り返し何度も同じことを言われて・・しつこい!」と思ったときの対処法

どうストップをかける?
何度も何度も同じことを言われる。しつこいと感じてとても嫌な気分になる。
そんな時どうしたらいいのか、について書いていきます。
姑のBさんが何度も何度もしつこく同じことを言うので「またか?」とうんざりしてしまうお嫁さんA子さん。
「何度も何度も同じことを繰り返し言うんですよね。先日もつい勝手口のカギをし忘れたのですが、風で開いていたのに姑が気が付いて、それ以来、自分が閉めた、開けておくのはダメだ、鍵はちゃんと閉めなきゃだめだって。。」
「何度も言われるとどういう気持ちになりますか?」
「なんだかすごく自分がダメ人間のように感じます。そんなに何度も言わなくてもわかるし、たった一回の失敗をそんなに指摘され続けると、うんざりするんです。まだいう?って感じですね。」
「そうですよね。どうしてもらえればいいですか?」
「一回言えばわかるから一度でいいから、ってわかってもらいたいです。」
「そうですか。実はねうちの主人も同じことを何度も繰り返して言う癖があるんです。」
「え、そうなんですか?」
「そうそう、若いころからね。また同じこと言うの?って感じでした。」
「で、どうされたんですか?」
「それ以前聞きました。って言いました。」
「そうしたら?」
「一度言ったかもしれないけど、って前置きしてから言うようになりました。だからどうやら同じことを言っているという自覚がないみたいなのよね。」
「ああ、そうなんですね。で、いまだに何度も繰り返してます?」
「ううん、次第にその繰り返しをしていたら言わなくなりましたよ。」
「そうだったんですか、それじゃ言ってみようかな。」
「そうね、お姑さんだから何ていったらいいかしらね。普段は割と会話があるほうですか?」
「ええ、一緒に住んでいるわけではないから、会ったときにはできるだけ話はするようにしています。」
「そう、それならその延長でさらっと言えるといいですね。」
「はい、お義母さんそれ一回聞きましたよ。とか?」
「そうね、そんな感じですかね。」
「それにしても自覚がないんだってちょっとびっくりしてしまいました。」
「人って割と自分のことってわかってないのかもしれません。私も結構何度も同じこと言ってるなってあとで気が付くことありますもの。」
「ってことは私も・・ですかね。」
「それはわかりませんが。。」
「割と子どもに対しては自分もしつこいかも、って思ってしまいました。そっかあ、みんな程度の違いはあれあるのかもしれませんね。」
さて、会話の習慣とは気が付きにくいものですが、周りが気が付いてもなかなか指摘しにくいものです。
指摘したいときには「事実だけ伝える」が原則です。前後にあれこれ感情をくっつけないこと。
今回の場合には「それ以前聞きました。」「それ一回聞きました。」ですね。
その際には感情的に伝えないことも大事です。できればさらっとです。
そうすると相手は自分の行動を自覚しますし、お互いに嫌な気持ちになることもありません。
ご参考になれば幸いです。
2022・12・20 「だから言ったじゃないの!」言われてむかつく心理

自分のことぐらい自分でやりますから、
って気持ちになる。
「だから言ったじゃない。」そんな言葉を投げかけられてムッとしたことはありませんか?
言われたときは「だって・・自分ではそうしたくなかったし、自分でやりたかったし。自分のことは自分で決めたいんだ。」
そう思ってむかついたのではありませんか?
先日ある受講生とお話ししていて「何かっていうと実家の母が、だから言ったじゃないって私に言うんです。確かに母の言うことはもっともだけど、その通りにすればうまくいったのかもしれないけど、なんだかむかつくんですよね。」
というお話。
「だから言ったじゃない。って言葉の後ろにはどんな言葉が続くかしらね?」
「そうですねえ、だから言うとおりにすればいいのよ。ですかね。」
「そうよね。」
「あと、私の言うことは黙って聞けばいいのよ。もあるかな。。」
「なるほどねえ。黙って私の言うとおりにしろって。」
「そうなんですよね。だからそれじゃ私の考えは?私が自分で考えてやっちゃいけないの?って思ってしまうんです。」
「自分のことは自分で考えてやりたい?」
「ええ、そうです。だって自分のことだし、自分で考えてやったことならうまくいかなくてもいいし、次どうするか考えればいいし、いちいち指導するなよって感じです。」
「指導ね。。」
「そうそう、指導とか指示とか。上下なんですよね。上から目線で。。あなたに指導されなくても自分で考えられるし自分でやれますって、そんな気持ちです。これってアドラー的にはどうなんでしょう?」
「アドラー心理学で考えると何が問題なのかわかる?」
「ええっと、まず今言った上下関係が一つありますよね。上からの物言いだからむかつく。あとは結局何をどうするかは自分の課題なので、ずかずかと踏み込まれてそれ見たことか‥みたいな感じ。後は何があるかなあ。。。まだありますか?」
「アドラーの子育ての目標に自分には能力があるって思ってもらうことがあるけど、その視点だとどう?」
「ああ、そうですよね。だから言ったじゃない、って言葉には、あなたには考える力がない、能力がない、だから自分の言うとおりにしろって。そうしないから失敗するんだ、うまくいかないんだってニュアンスがありますね。そうか、だからむかつくんですね。自分の能力を認めてもらっていない、って言葉の響きがありますものね。」
「そうそう、勇気くじきの三点セット。」
「そうか、それでむかつくのかあ。。」
「で、次からどうする?」
「ええっと、そういわれたら、ですよね。どうしようかな、、いちいち自分の事あれこれ言わないほうが無難かな。。必要な時だけ意見を求めるようにするとか。」
「そうね、そのほうがいいかも。。ところでだから言ったじゃないっていいたくなるお母さまの気持ちはわかる?」
「だから言ったじゃない、の気持ちですか?そうですね、きっと心配なんだろうなとは思います。」
「そう、その辺がわかっていれば大丈夫ね。」
さて、いかがでしたでしょうか?
親が心配して良かれと思っての言葉が実は相手の勇気をくじいている、よくあることだと思います。
自分のかけた言葉と相手の反応を見て、検証を繰り返す。こういわれたら相手はどう思うのか、感じるのか、それならどういえばいいのか、日々実践していただきたいことです。
特にお子さんがいらっしゃる方は「自分の能力を信じそれを育てられるような言葉かけ」をしていきたいですね。
自分と自分の能力を信じ活かせる勇気づけの対応を心掛けたいものです。
2022・12・8 「あれしろこれしろと強要する姑」嫁は使用人? なんとかしたい

「来れば要求ばかり一方的」
上手に断りたい
同居しているならまだしも、わざわざお嫁さんのところへ出かけてきて「あれこれ指示を出す姑」
困ってしまってご相談に来られた方のお話です。
「近所に住む姑がなんやかんやとあれしてくれこれしてくれ」と言ってくるので本当に困っているんだとA子さん。
「どんなことを頼まれるのですか?」
「仕事に出かけたついでに銀行でこれ払ってきてくれとか、00を買ってきてくれとか、です。」
「お姑さんはご自分でできない環境なんでしょうか?」
「いいえ、舅もいますし車も運転しますし、自分でやれるんです。それなのにわざわざ私のところへ来てあれこれ頼んでいきます。」
「それでつい引き受けるのですね。」
「はい、突然来てこちらの心の準備が出来ていないうちに自分の要求だけバーッと突き付けて帰っていくので、気が付いたら引き受けちゃってた、って感じです。」
「ああ、なるほど、そんな感じなんですね。」
「はい、頼む方はこれぐらいと思って頼むんでしょうけど、仕事に出たついでといっても結構面倒なんです。」
「ですよね。で、どうなればいいですか?」
「自分のことは自分でやってもらえればいいし、断りたいので断れるといいかなと思います。」
「断れないのは勢いに押されちゃうからかな?」
「ええ、つい何ていおうって考えているうちに押されちゃってたって感じです。」
「それじゃ、一呼吸おきたいですね。何か一言言えればいいんだけれど、何か考え付きます?」
「ちょっと待ってくださいとかですか?」
「それいいですね。その一呼吸でそのあとどうしましょう?」
「仕事が忙しくて時間の余裕がないのですみませんができません。でしょうか。」
「言えますか?」
「一呼吸置けば何とか言えるかもしれません。」
「それじゃそれでやってみましょうか?ご主人はこのことなんて言ってるの?」
「自分が頼まれるわけじゃないからあんまり気にしてないみたいです。」
「そのことについては話し合ったことは?」
「ないです。でも一度話し合って向うに伝えたほうがいいのかな?」
「そうね、そうできれば今後のことを考えるとそのほうがいいかもしれませんね。」
共同の課題にするかどうかは引き受ける側に決定権があります。勝手に共同の課題にはならないのです。
今回A子さんはとても不愉快だと感じていたのですが、それは姑が自分の課題を当然のようにA子さんに投げていたから不愉快だったのです。
課題分けは自分が陰性感情を感じたときの一つの目安になります。
踏み込まれていないか、勝手に課題を丸投げされていないか、踏み込ませているのではないか?など判断の目安となると思います。
検証にもお使いいただければ幸いです。
2022・12・6 「外面のいい母親に嫌悪感」 家族の方が大事なんじゃないの?と思っている自分は間違っているのか?

世話をしているのは子どもの私なのに
お礼を言うのは配偶者に対してばかり
「なんだか母に対して頭に来てしまって。」とご相談にいらしたA子さん。
「もう介護の状態になっているんですけど、実際に世話をしているのは娘の私なのに、私より主人にばかりお礼を言って私には言ってくれないんです。まず主人にお礼を言わなきゃと思っているみたいで。なんだか腹が立つんです。」
とおっしゃいます。
「実際にやっているのは私なのに、配偶者にばかりお礼を言う」のが腹が立つのですね。
「そうなんです。実の子どもだから言わなくてもわかるでしょう?って思っているのか、親の世話をするのは子どもとして当然だから言う必要がないとでも思っているんでしょうか?でも主人には言うんですよね。それがなんだか頭に来ます。」
「それってどういう感情なのですかね?」
「悲しいっていうか、寂しいっていうか、もっと自分の頑張りを認めてほしいっていうか、認めて私にもありがとうって言ってよ、って気持ちです。」
「ご主人に言うだけでなくあなたにも言ってもらえばいいのですか?」
「いえ、主人はうちの母の介護には関与していませんから、私にだけ言って欲しいんです。」
「自分にだけ?ですか。」
「ええ、だって実際にやってない人にお礼を言う必要がないでしょ?それなのに私の目の前で私を差し置いて主人にお礼を言うから頭に来るんです。まず私を一番大事にしてくれないとって思っちゃいます。昔から外面委のいい人だったので。」
「そうですか、そうするとあなたにだけお母様がお礼を言えばいいんですね。」
「ええ、そうです。だってやっているのは自分だけなんだから。。」
「なるほど、わかりました。どうしてお母様がご主人にありがとうっていうのか、考えたことはありますか?」
「そうですね、自分の家をほったらかして娘が介護にかかりきりになっているのでごめんなさいねということがあるのかなと、そう思います。」
「迷惑をかけてしまっていると?」
「だと思います。でもその辺は主人は気にしない人だからいいんだと思うんだけれど。。」
「それじゃ、A子さんがお母様の立場だったらと考えて見ましょうか。あなたがもしも歳をとって車いす生活になったとして、娘さんが嫁ぎ先をほったらかしてあなたの介護に携わったとしましょう。かかりきりになっているところへ娘さんのご主人が来たとします、何て言いますか?」
「助かってます。ありがとう。でしょうね。。そうか、そういうことなんだ。。」
「そういうことってどういうことですか?」
「娘を寄こしてくれてありがとう、なんですね。だから主人に言うのですよね。主人がそういう人でなければ介護もしてもらえないわけだから。」
「どうですか?直接お母様があなたにお礼を言わないことについていくらか気持ちが変化しましたか?やっぱり外面がいいって思います?」
「いいえ、いくらかわかる気持ちになりました。最初よりは腹も立たないし、まあいいかって気持ちになりました。理解してくれて協力してくれる夫がいるから、それでいいかなって。」
「そうですか、それはよかったですね。」
気持ちを順に整理していくと、すっきりするということはよくあることです。外面のいい母のことだからと最初に決めつけていたA子さんでしたが、どうやらそうではないんだな、違うんだなとわかって、親や起こった出来事の別の側面が見えてきたようです。
人に話すということは勇気がいりますが、自分の起こった出来事を整理したり感情に丁寧に向き合ったりすることで問題としていたことが問題にならなくなるというケースは結構あるものなんですよね。
2022・12・3 「気に入らないと口をきかない・無視する・・」 言葉で言わないと伝わらないのが他者である

言葉というツールを
使わない人
A子さんがご主人のことでご相談にいらしたのは、ずいぶん長い間我慢したうえでのことだったと言います。
自分が悪いんじゃないか、自分が主人の期待に応えないからではないかと悩み続けてきたそうですが、でも何かすっきりしない。
自分の気持ちを整理したくていらっしゃいました。
「ご主人のどういうところがあなたの悩みになっていますか?」
「実は気に入らないことがあると黙ってしまって無視するんです。それがしばらく続いて口をきいてくれないので家の中がとてもピリピリした感じなります。そういう状態が続くとつらいし自分の人格を否定されたような気持になるので、つい相手の機嫌を取ってしまうんですけど、そういう自分も嫌なんです。」
「そうですか、口を利かなくなるんですね。黙って無視という方法をとるということですね。それはご一緒に暮らしておられてお辛いでしょうね。」
「ええ、いつも相手の機嫌を見ている、そういう関係ってフェアーじゃないし、なんだか自分のほうがいつも相手に合わせているようで主従関係っていうか自分のほうが劣っているような感覚になります。」
「ご主人はたぶんねえどなたかからその方法を採用されたと思うのですけど、ご主人の身近にそういう方法、気に入らないと口を利かないとか無視をするとかいう方法ですね、それを使う方がおられますか?」
「そうですねえ・・・・あ、舅がそうです。姑に気に入らないことがあると口を利かないで無視するんです。」
「そうですか、そうするとご主人は自分のお父様からその方法を採用したってことでしょうね。口を利かないで相手にわからせようっていうのはとても楽で簡単な方法ですからね。」
「なるほど、そういう風に考えるんですね。」
「ええ、ですからこれから先方法を言葉で伝える、気持ちを伝えるという風に変えてもらう必要があるかと思うのです。言葉で何がどう気に入らないのか言ってもらったほうがいいでしょう?」
「ええ、もちろんです。無視なんて方法を使われるより言葉でちゃんと伝えてもらえればこちらも考えられますし、できることできないことも言えますから。」
「ですよね。それじゃ、なんて言いましょうか?」
「口を利かないっていう方法じゃなくて言葉で伝えてもらえませんか?でしょうか?」
「そうですね、それでいいと思います。それでも口を利かないのであれば、言ってもらえないと理解できませんから改善も望めません、がプラスかな。。」
「なるほど、やってみます。もう主人の機嫌を取るのはまっぴらなので。。」
「そうですよね。ご主人様が方法を変えて仲良く暮らせるといいですね。」
「ありがとうございます。ご相談してよかったです。」
態度でわかってもらいたい、態度でわからせようとするのはあまり現実的ではありません。なぜなら自分と相手は別の人間ですから言葉で伝えあわないと到底分かり合えないのです。
何も言わずに「わかれ!」というのは家族間・夫婦間などの身近な関係に起きがちです。身近だからこそきちんと伝えあう。そういう方法を採りたいものです。
こういうご相談は相談会で受けております。どうぞご利用くださいね。
2022・11・30 「素直になれないひねくれた自分・・」 使い方さえ変えればひねくれた視点はもっていていい

ひねくれも
使いよう
2022・11・29 「嫁の自分さえ我慢すれば・・」親の介護をめぐって

当事者とそうでない人と
課題分けがカギになる
2022・11・22 「私がいないとこの人はダメになる・・」共依存夫婦のバランスが崩れた時

対等のパートナーとして
夫婦関係の再構築を
2022・11・21 「人前に出ると過度に緊張してしまう」リラックスが苦手な人でもすぐできる方法

失敗しても大丈夫
過度に人前に出ると緊張してしまう。そういうお悩みで来られる方もいらっしゃいます。
先日のこと「会社でお客様にお茶をお出ししようとしてこぼしてしまったんです。上司にひどく叱責されて、それ以来、いやその前からですけどなんだか手が震えてしまったりして、人前に出ると余計緊張するようになってしまいました。どうしたらいいんでしょう。」
「ご自分ではどうお考えになりますか?」
「緊張さえしなければと思うのですけれど。失敗したらどうしようとか、どう思われるだろうとか、そんなことを考えてしまって、だから余計手が震えたりするんだと思います。」
「そうですか。そこまでお分かりなのであれば、ご説明しますね。アドラー心理学では心と体のつながりについても矛盾がないというように考えますから、それに基づいて考えると今のあなたの症状もきっとあなたへのメッセージですよね。」
「メッセージですか?」
「そうです。言葉にして言えないことを体の症状を使って言っているとも言えます。何が言いたいんでしょうね。」
「失敗したらまたひどく叱られるかもしれないからやりたくない、ですか?」
「そうかもしれません。でも社会人としてそれは言えませんものね。ですから体の症状として出して、わかって!って言ってるのかもしれないです。」
「ああ、そういうことなんですね。それならほんとは失敗するかもしれないからやりたくない。が私の本心?」
「どうですか?」
「あるかもしれません。女性だからってお客様が来るたびにお茶出しをさせられて不満もありました。イヤイヤやっていたこともあります。でも仕方がないなっても思っていました。」
「そうだったんですね。ご自分の気持ちいろいろお茶出し一つとってもあったんですね。」
「ええ、今気が付きました。なんだか気持ちがすっきりしました。」
「あとは何か気が付いたことがありますか?」
「失敗してはならない、も強いですし、失敗すると責められるから失敗しないで済むように他者を必要以上に寄せ付けない壁みたいなものも自分の中にはあるかもしれません。」
「そうすると周りはあなたにとって安心できる味方ではない?」
「そうですね、自分が失敗すれば周りは自分を攻撃、または責めると捉えていますから少なくても味方だとは思えていないんでしょうね、だから緊張するんでしょうか。構えちゃう。」
「そうですね。失敗しないようにいつも気を張ってないといけない状態になっていますから。これでは心が緩むことはないかもしれません。」
「そうですよね。」
「あなたを叱責する人ってそんなに多いですか?よく考えてみてくださいますか?」
「そうですね、よくよく考えれば上司ぐらいかな、あとはそんなことは気にしなくていいとか優しい人が多いように思います。」
「それなら全部に構えなくてもいいのでは?」
「そうですよね。なんだか体の力が抜けそうです。」
「もしかしてリラックスが苦手では?」
「はい、苦手です。」
「一つか二つでいいので緊張したときに使えるツールを身に着けるという方法もありますよ。」
そんなお話の流れからリラックスの方法をお伝えしてその日は笑顔でお帰りになられました。
<自分で簡単にリラックスできる方法>
一番簡単にリラックスでき体の力を抜く方法はやはり呼吸法や瞑想でしょう。これらを身に着けることで自分で多少なりとも和らげることができると思います。
呼吸法は吸うよりも吐く方が大事です。
できるだけゆっくり時間をかけて息を吐いていきます。20秒から30秒かけてゆっくり吐きます。
意識は体の中に入ってくる息と吐きだす息の流れに集中します。
これが継続してできるようになると自然に瞑想の状態に入っていくことができるようになります。
人によっては場合には緊張から来る手の震えだけでなく筋骨格系の痛みも出ることがあります。これも心が緊張していることに端を発していると考えられます。
心と体のつながりについて理解できていないと「緊張しているからだよ。」と言っても理解できません。
たとえ理解できたとしてもそれではどうしたら緊張を緩めることができるのかがわからないでしょう。
リラックスは人それぞれ合うものが違いますし、合うものを見つけることも過度に緊張しがちな方には必要です。
緊張がダメなのではありません。緊張は必要なのです。緊張しても取り組んでいる自分にOKを出しましょう。自分は緊張してしまうけど人よりちょっと強いだけだ、と。
リラックスの方法をいくつか挙げておきますので自分でできそうなことがありましたら取り組んでみてくださいね。緊張をゼロにすることを目指すのではなく軽くすることを目指していくのが大事です。
ゼロにはなりません。人前に出ると緊張するのは誰でもあることです。緊張した後に緩めることに意識を向けましょう。緊張したら緩めればいいという発想です。
副交感神経が優位になる腹式呼吸 ーおなかに手を当てておなかが出たり引っ込んだりに意識を向けます。
辛いときや忙しいときは意識的に笑顔を作る ー口角がちょっと上がるぐらいでOK
お昼休憩などで仮眠を取り入れる ー目をつぶって呼吸に意識を向けるぐらい
観葉植物をじっと見る ー空を見あげるなどもいいでしょう。雲を見るなど下を向きがちな視線を上に向けます。
簡単なマッサージを行う ーテニスボールぐらいの固さのものを背中に当ててぐりぐり転がしてみましょう。
寒くなって来て体のこわばり、心のこわばりが出始める時期でもあります。上手に自分の心と体に付き合っていきたいものです。
アドラー東北では子育てや人間関係のお悩みのほかにご自分のことについてのご相談もお話しをうかがっております。
いつでもどなたでも参加できますのでどうぞ積極的にご利用くださいね。日程等は下記でご覧いただけます。
2022・11・18 「私が悪いんです。。」それって本当に必要ですか?自責感情の強さから脱却する方法

その問題は
誰の人生に起きていることですか?
お子さんやご主人に問題が起きると「私が悪かったから。」とか「私にも問題があったから。」とご自分を責めてしまう方は結構おられます。
お子さんが問題を起こした。
「自分がもっと気にかけてやれば」「愛情が足りなかったから」
親である自分の責任と考えてしまいます。
ご主人に問題があれば「そういう人にしてしまったのは自分にも問題があるからじゃないか。」とか「そういう人と巡り合う自分が悪いんだ。」といったようにです。
こういう自責感情は本当に必要なのでしょうか?
A子さんはご主人の女性関係に悩んでご相談に来られました。
「妻として私がいたらないばかりにこうなってしまったのではないか」とご自分を責めてしまっていました。
「どうしてそう思われるのですか?」
「子どものことばかりにかまけて主人のことを放っておいたかもしれませんし、どんどん身なりも構わなくなって妻としても魅力的ではなかったかもしれません。いずれにしても自分にも問題があったと思うのです。」
「なるほど、そう思われるんですね。そうするとご主人さまに丁寧に接していたり、きれいにしている奥さんがおられる方は女性問題を起こさないってことになりますが、いかがですか?」
「あ、そうか、そうですね。」
「あなたに問題はないと思いますよ。あくまでご主人の問題だと思います。あなたは何も悪くない。」
「そうでしょうか。」
「ご主人の人生に起きていること、ご主人が自分の意志でしていることについてあなたが責任を感じる必要はありません。」
「そういっていただけるとほっとします。うれしいです。」
「もしかしてお子さんに対してもそういう思考なさることがおありになりませんか?」
「あ、はい、あります。子どもに問題が起きると自分が親として至らなかったんじゃないかとか考えてしまいます。」
「あなたのように接している親御さんはたくさんいるけれども同じような問題が必ずしも起きるわけではありませんよね。」
「ええ、そうですね。主人に対してと同じように考えてしまっていました。」
「家族であっても、自分以外の人に関して必要以上に責任を感じて自分を責めるのは、あまり自分に優しいとは言えませんから、そういう思考になったら、そこは分けて考えられるといいと思うんです。この問題は誰の人生に起きていることなのか?ってね。」
「わかりました。そうしてみます。」
「あとはご主人とこれから先あなたがどうしたいかを考えていけばいいのです。次回はその辺をお話ししましょうね。」
「そうですよね。なんでそう思ってきたんだろうって?言われてみればそうです。それは主人の問題で私の責任じゃないんですものね。気持ちがとても楽になりました。これからのことを考えてきてみます。」
自分の子どもだからといって、自分の配偶者だからと言って、起こった出来事をなんでもかんでも自分が責任を感じる。
これでは「自分が好き」にはなれそうもありません。まずは自分の人生と他者の人生を分けて考えられるようになることが大事ではないでしょうか?
必要以上に他者の問題を抱え込まない、これができるだけでも自分の精神的な負担が減り、気持ちが楽になるように感じています。
ご相談は「子育て・人間関係相談会」で受け付けております。子育てや人間関係に関することでしたら何でも相談できます。どうぞご利用ください。
2022・11・16
「ぬれ落ち葉症候群」退職後が心配
仕事だけでは精神的な自立はできない

お互いに精神的に自立したうえでの
対等なパートナーであることが夫婦でも必要
「なんだか主人が休みの日に家にといると重いんです。」とおっしゃるA子さん。どういうことかというと
「すべて管理されているみたいで、一緒にいるときには何から何まで自分とセットじゃないとダメとか、とっても気づまりなんです。」
どういう感覚かというと「自由を束縛されている感じ」とおっしゃいます。
自分を優先にしてほしい、一緒にいてほしい、自分のことだけ見てほしい、そんな感じですと。
今はまだ仕事に行っていますから休日だけ我慢すればいいのですけど、退職後を考えるとへばりつかれて自分がますます身動きが取れなくなりそうなんです。
ご自分はやりたいことがたくさんあってご主人がお仕事の時にはそれなりに充実してやれているのだけれども、お休みの日になると途端に気を使わなければならなくなり、ご主人にも仕事以外の何かを持ってほしいと感じているんだそうです。
「ご心配もあるんですよね?」そうお聞きしましたら「そうなんですよね。」というお答えでした。
仕事人間にありがちです。日本ではいまだにこういう方がたくさんおられます。仕事を辞めたとたんに居場所を失くしたと感じて奥様にへばりつくことで居場所感覚を持とうとされるのです。
自分の世界を持つということが大事なのですが、家族優先主義にありがちな傾向です。お子さんが自立するまではそれも致し方ありませんが、それでも「自分軸」を持っている方はこうはなりません。
夫婦でも夫は夫の世界を持ち、妻は妻の世界を持っている、そのうえで必要があれば協力し合うというのが精神的に自立した大人同士の関係ということになるのではないでしょうか。
そういう意味ではお休みの日に家族を放置して自分の趣味に没頭しているご主人というのは、自分の世界を持っておられて自分を大事にしておられるということですから、退職後に妻にへばりついたりはなさそうです。
できるだけ早い段階で何か「個人の趣味」「没頭できること」を見つけてもらえればこうはなりません。仕事以外、家族以外の世界を持っているということは本当はとても大事なことなのです。
それぞれの世界を持っていながらも家族でいることは可能です。自分の世界が持てなくて家族にへばりつくしかないことのほうがご本人にとっても家族にとっても不幸なことになりかねません。
仕事だけの価値観はもうこれから先は通用しないのです。女性も精神的に自立している人が増えている今、男性の価値観も変わっていかなければおいていかれるだけになります。ご夫婦での話し合いが求められます。
2022・11・15
「言わなくてもわかれ!って無理だから・・」
機嫌・不機嫌ー他者操作

家族だからこそ、大事だからこそ
言葉で気持ちを伝えあう
今回は態度でわかってもらおうとする人について書いていきます。
機嫌が悪いとドアをバタンバタン。物をがしゃがしゃ。
ポーンとものを投げてよこすなど、行動で自分の気持ちをわかってもらいたいとする人がおられます。
言葉で言ってくれればいいのに。そう感じることはありませんか?
察してほしいのです。そうされたほうはそうするしかなくなります。
ですから態度でわかってもらおうとする人の目的は「察してほしい」です。
察しないとさらに行動が過激になります。でも周りはびくびくしてしまいます。
そしてほかの人たちに対しても敏感な子どもになります。相手の顔色を窺い、相手の反応に過敏な子供になります。
「何かあってもそうやってものに当たったり態度でわかってもらおうとするんです。」
A子さんはご同居する父親の態度に困ってご相談に来られました。
「主人も私も常に父の態度に気を配らなきゃならなくて、家にいても神経が休まらないんです。」
「そうでしょうね。それは大変ですね。」
「傷つけたくないし、どうしたらいいものかと。。」
「相手の目的は察してほしいですから、察してあなた方が行動すれば目的を達成させることになります。ですから達成させるのはまずいですよね。どうしてほしいですか?」
「言いたいこと、してほしいことは言葉で言ってほしいです。」
「いつもいつもそうなんでしょうか?」
「いえ、何か気に入らないことがあった時だけです。言葉で伝えてくれることもあるんですけど。」
「それじゃ言葉で伝えてくれた時に、言ってくれてうれしい、って伝えてみましょうか。
態度の時にはできるならスルーしたほうがいいです。」
「でもスルーするとどんどん態度がエスカレートするんですけど。」
「怖いですか?あなたはもう立派な自立した大人ですから、親に従うしかなかった子供ではないのではないでしょうか。」
「あ、そうですね。子どもころは父がそうすると怖かったけど、今はそうではないのですものね。」
「そうです。自立した大人同士の関係で、言葉で伝えあうようにしていきましょう。どうしてもの時は、言葉で言ってくださいませんか?って伝えてみてもいいでしょう。」
「わかりました。やってみます。」
うちは夫婦でそうだったなあと思います。
まず私が言葉で伝えるようになり、それを主人にもお願いして徐々に改善していきました。
今は態度でわかってもらおうとすることは二人ともほとんどありません。
周りにも「してほしいことわかってほしいことがあったら言葉で言ってもらわないとわかりませんよ。」と繰り返し伝えてきました。
家族なのに相手の気持ちを察して動く、こういう気の使い方をしなければならないのでは一緒にいるのも気疲れしてしまいます。
お心当たりのあるかはどうぞご相談くださいね。
2022・11・12
「親の価値観を押し付けないで!」結婚・自立した子どもへの介入もほどほどに

お互いに自立した大人同士として
尊敬しあう
おはようございます。
子育てにしても人間関係にしても「これはどうしたらいいの?」と考えてしまうことが多々あると思うのですが、特に自分の親との関係については距離が近い分どうしても難しい側面が出てくるようです。
今回はそんな一つのケースについて取り上げます。
A子さんは、娘さんのBさんの嫁ぎ先を久しぶりに訪問したくなり、「行くからね」と事前に連絡をして出かけていきました。
そうしましたら、娘さんは朝からお友達と出かけていて、夫である婿さんのC男さんがお子さんを抱っこしながら出てきました。
エプロンをかけて台所に立っていたらしく「お義母さんいらっしゃい。今お好み焼きを午後のおやつに焼いているので一緒にどうですか?」と言います。
「Bはどうしたの?朝から出かけていないって?あなた一人に子どもを任せてどういうこと?」
わが娘ながら恥ずかしさと怒りが込み上げてきたA子さん。帰宅したBさんに早速それをぶつけてしまいました。
久しぶりの友人との楽しい時間を過ごしてご機嫌でかえってきたBさんには、冷や水を浴びせられたような気持になり、当然のことながら親子げんかになったのです。
「それって母親としてどうなの?ダメでしょうが?!」というA子さん。「久しぶりに外出して息抜きして何が悪いの?!私だって毎日仕事と育児とちゃんとやってるんだから。」というBさん。
間に入るに入れず困った顔をしてその場にいるしかない風のC男さん。
5歳の孫が間に入って「ばあばとママはけんかしちゃダメ~。」と言ったのでその場はそれで話はやめになりましたが、どうにもモヤモヤが双方に残ってしまったのでした。
A子さんは「私は間違ってない。母親としてこうあるべきという正しいことを言っただけ。それなのになんで言うことを聞かないの?」と感じてしまったようです。
「自分の価値観」が若い人にはもう通用しないのかといった寂しさもありました。
さて、このケースは何が問題でどう対応すればいいのでしょう。
A子さんの立場で考えてみますと、私ならまず「夫婦間で合意の上でなされていることかどうか」を確かめます。
夫婦でお互いに納得してそうしていることなら口をはさむ筋合いのことではないからです。
夫婦で納得していることに口を出せばただの「価値観の押し付け」になってしまいます。
もしもC男さんの口から「不満」が出た場合には「ちゃんとBと話し合うよう」にC男さんに勧めるかもしれませんが、直接Bさんには言わないという方法をとるでしょう。
夫婦の問題は夫婦で解決したほうがいいので、ここでBさんに言えば「課題に踏み込まれた」と感じたBさんは多分聞く耳を持たず、その後夫婦で話し合ったとしてもうまくいかない可能性があるからです。
Bさんの立場でいえば「課題にずかずかと踏み込まれた」と感じて不愉快を感じたということになるかと思います。
ですので「夫婦で合意の上であること」を伝えるか、C男さんと話し合って自分たちで決めるのでお母さんの意見は意見として聞いておきますぐらいの対応が望ましいでしょう。
子どもが家庭をもって自立した後も「ああしろこうしろ」と親が価値観を押し付け続ければ双方が嫌な気持ちになるだけです。
必要な時に助言を求められたらというスタンスでかかわるぐらいでちょうどいいのではないかと私自身は感じています。
今子育て中のママたちにも自分の親や配偶者の親との関係で何が問題であるのか。「課題分け」「夫婦の合意」といったあたりが解決のヒントになるかもしれませんね。
2022・11・9
「罰は効果があるのか?」子育てでつい使いがちだけど、効果のほどは?

いうこと聞かないと罰を使いがち
でも効果は??
今日はたまたま目にした親子の会話からヒントを得て、罰について書いていこうかなとそう思います。
昨日いつものスーパーに買い物に行って、レジのところでお会計の済んでいないお菓子を開けようとした子どもの手を母親がピシャっとたたきました。
その前に「お金を払ってからでないと開けてはだめよ。」と言っていたようでしたけど、言うことを聞かない子供に実力行使に出たということになるかと思ってみておりました。
子どもはびっくりして、恐る恐るその場を離れてしまいました。母親は黙ってムッとしたまま会計を済ませて子どもに声をかけることはありませんでした。
さて手をピシャっとたたくことで、母親が子どもにわかってほしいことが伝わったでしょうか?
「ダメだ。」とか「いけない」ということは伝わったかもしれませんが、「なぜ」「どうして」は子どもはわからないかもしれません。
母親がわかってほしかったのは「お金を払って初めてそのお菓子はあなたのものになるのだから、あなたはお金の支払いが終わるまではあなたのものではありません。だからそれを開けてはいけないのよ。それが社会のルールなんですよ。」
ですよね。
ピシャっと手をたたいたのは「罰」になるかなと思います。罰っていうのは、合理的であれば効きますが、合理的でないと効きません。
この場合の合理的な罰ということは「子どもが欲しいもの・お菓子が手に入らない状態」になるでしょう。
罰でやりがちなのが関連性のない事柄を罰として使ってしまうことです。
「宿題をしないとおやつをあげませんよ」とか「忘れ物をしたんだから立ってなさい」とかです。
宿題とおやつ、忘れ物と立たされることに関連性は全くありません。
とにかく「いけないんだ」ということはわかりますが、その理由は伝わらないのです。
「宿題をしないと自分が困るんですよ。」「忘れ物をすると自分が困るんですよ。」という結末の体験につながりません。
アドラーの育児ではもちろん「罰」は百害あって一利なしとして使わないようにします。
罰の弊害は、場当たり的、その場しのぎになりがちで感情的に親がなってしまうので「本当にわかってほしいこと」「どうすればいいのか」が伝わらないということ、子どもが親の顔色を窺うようになることなど、たくさんあります。
私ならこういう場合にどうするかというと、「お金を払って初めて自分のものになる」という社会のルールを説明したうえで「それでもお菓子を開けようとするならば買ってあげられないなあ。どうしますか?どちらでも自分で決めていいんですよ。」と言うかなと思います。
こういう対応をするのは数秒しかかからないのですから、普段からのトレーニングがものをいうことは言うまでもないことです。
とっさに出てこないという方はサポート会や相談会で練習を積んで対応の場数を踏んでいきたいものですね。
今回もお読みいただきありがとうございます。
11月のサポート会、相談会、個別相談のご案内はこちらからどうぞ。
https://www.adoratohoku-main.jp/16286245016673
2022・11・4
「性格の不一致」は、夫婦離婚の決定因になるのか?

価値観の違い・性格の不一致は
相手との関係の決定要因にはならない
近年離婚が増えていることは「女性の自立」と相まって当然のことのように思われています。
原因は性格の不一致だとか、価値観の違い・・だとか、理解してもらえないとかいろいろあるようです。
中でも性格の不一致という言葉は夫婦離婚の理由としてはよく出てきますよね。
性格が違うので相手とはうまくやれない、どうせ理解してもらえない、ということのようです。
さてこれはどう考えたらいいのでしょう?
「夫と別れようと思っているんです。」A子さんは思いつめたように話し始めました。
「それはどういうことでしょうか?」
「私の事を理解してくれようとしないんです。性格も合わないし、なんだかとってもちぐはぐな感じになってしまって。一緒にいても楽しくないし、いっそ別れようかなって。。」
「ちぐはぐな感じというのは?」
「そうですねえ、私が何か話すと全然違う答えが返ってくるんです。」
「それは以前からそうだったんですか?」
「いえ、結婚前は一生懸命聞いてくれていたような気がします。最近はお前の話はさっぱり分からんといった風なんで、何でもいいから答えておけばいいって感じの適当な返事が返ってきてるような気がするんです。」
「そうですか。理解してもらえていない、わかってくれようとしていないって感じておられるのですかね?」
「そうですね。」
「それはお辛いですね。」
「はい、なんか彼にとって自分なんかいてもいなくてもいいんじゃないかって、そう感じることもあります。」
「そうなんですね。一つ確認しておきたいのですが、実際に離婚するかどうかはともかく、あなたの気持ちとしては離婚したいのですか、それとも本当は離婚したくないのですか?」
「離婚したくないです。できるなら何とか立て直したいです。」
「わかりました。それでは一つご提案があります。」
「何でしょうか?」
「あなたはご主人と離婚したくないのですから、仲良く暮らしたいのですよね?」
「はい、そうです。」
「それをご主人に伝えてみませんか?」
「仲良くしたいってですか?」
「ええ、できますか?」
「それぐらいならできそうですけど。。」
「そのうえで、相手がいい加減な返事をしたなと感じたら、その返事だと仲良くしたいって私は思えないんだけど。って、ご主人の対応について仲良くできそうとか仲良くできなさそうとか伝えてみることは可能ですか?」
「ああ、そういう風にしていけばいいんですね。」
「ええ、仲良くするっていうゴールが一致しているとお互いに歩み寄りしやすいんです。共通の目標がありますからね。」
「なるほど、わかりました。やってみます。」
「性格が違うのは人としては当然なので、違うとつい合わないとか別れるとか、争うっていう話になっちゃうんですけど、仲良しになるっていうゴールを一緒に目指すって感じでやってもらえればきっとうまくいきますよ。」
このように、合わないと争う、別れるになりがちな夫婦関係ですが、そういう結末に向かっているときにはゴール設定が「相手に勝つ」とか「相手の上に立つ」になっている可能性が高いです。
このゴールの設定を変えてもらったケースです。仲良くするという「ゴール」さえきっちり夫婦で共有できていれば「そのためにお互いに協力する」ということは可能です。
2022・11・1
「あなたにわたしの何がわかるの?」人格が否定されたとき
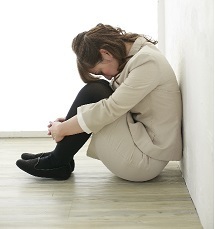
「わかってほしい」でも「わかろうともしてくれない」その悲しみが怒りとなる
「あなたに私の何がわかるっていうの?」
そんな風に感じたことがありませんか?
理解してほしい、わかってほしい、それなのに理解しようとさえしない相手に対する腹立ち。
今日はそんな経験をした方のお話です。
10代のころからなんとなく体の調子が悪いなと感じていたA子さん。
大病はしないまでもいつも何らかの不調を抱えていることが多かったと言います。
それでも配偶者に出会い結婚して幸せな生活をスタートし、いくらか落ち着いたころ、ご近所の奥さんにこんなことを言われました。
その日は朝から何となく体調が悪く、ご主人の出勤を見送って、少し休もうかなと思ったところお隣に住む奥さんが声をかけてきたのです。
自分と比べて健康優良児のようなその方をA子さんは少し苦手だと感じていました。
「うちに来てお茶でも飲んでかない?」
「あ、すみません。あんまり今日は体調がよくないので少し休もうと思ってるんです。」
「あら、そうなの?体調が悪いって?」
「ええ、ちょっと貧血気味な感じなんです。」
「へえ、あなたってまだ若いのに結構あっちこっち具合が悪いって多いわね。」
「あまり丈夫じゃないので。。」
そう言って家の中に入ろうとしたときその奥さんからの一言がA子さんの怒りに火をつけました。
「ふ~ん、あなたって・・・ひとっつもいいところないんじゃないの?」
その一言でA子さんの中の何かが切れました。思わずキッとなってこういい返したのです。
「ずいぶんひどいこと言うのね。いったいあなたに私の何がわかるの?!言っていいことと悪いことがあるでしょうが。なんであなたにそこまで言われなきゃならないの?!」
普段にこにことおとなしいA子さんからの反撃にたじたじとなったお隣の奥さんは「ごめんなさい。」と言って逃げるように家の中に走りこんでしまいました。
「許せない。いったい何の権利があってそんなひどいことが言えるの?!あなたはたまたま親から健康な体をもらったというだけのことじゃない。体が弱いからってまるで存在価値がないみたいな言い方。ほんと頭にくるわ。」
A子さんの怒りは収まりませんでした。時間がたっても思い出すたびに怒りはふつふつと湧いてくるばかりです。
さて、A子さんが怒ったのはなぜなんでしょう?
そうです。人格を否定されたと感じたからです。自分という存在そのものを否定されたと感じたから怒ったのです。
その底には「私のことを理解して呉れようともしない相手」に対する「悲しみ」があったのではないでしょうか。
その日の夜になってご主人に伴われたお隣の奥さんが泣きながら謝りに来たので「みんあがあなたと同じように健康で元気なわけではない。」とだけ言って、それはそれで終わったのですが、それ以来なんとなくその方とは距離ができてしまいました。
お隣なのに気まずい状況になってしまったのです。
あの時私はどうすればよかったのか?といまだにA子さんは思っています。
さて、皆さんならどうされますか?
A子さんの気持ちはよくわかりますよね。まるで自分という人間をすべて否定されたかのように感じます。
怒るのは当然ではないでしょうか。
問題はその気持ちのままに怒りの感情の噴火を相手にぶつけてしまったことでしょう。
私ならいったんその場を去るなり、深呼吸をして落ち着いてからこう伝えるかなと思います。
「あなたは思ったこととただ口に出したかもしれない。でもそういう言い方をされると私という人間が全部だめだというように私には聞こえたの。だから私はとても悲しい。」
相手理解+他者の行動+自分の気持ち
あとは相手がどう感じるか、どう行動するかにゆだねるということになるでしょう。
少なくとも相手に怒りをそのままぶつけたり、言わずに我慢して伝えないという選択肢は取らなくなります。
感情をぶつけてしまってお互いに嫌な気持ちのまま壊れた関係が、私にもたくさんありました。
そういう経験はもうすることはないかと思いますし、少しの工夫で他者との衝突は最小限に抑えられるということを知っておいていただければと思っております。
2022・10・29
「攻撃してくる人に対する究極の対応とは?」

「攻撃」という行動で相手は何を
得ようとしているのか
2022・10・28
「私を傷つけたあの人に仕返ししたい」傷ついた心の立て直し方

裏切られたと感じた時
心の傷はどうすれば癒えるのか
今回は「傷ついた心の癒し方」について書いていきます。
対人関係で「傷ついた」「傷つけられた」と感じる場面、どなたでも経験がおありではないでしょうか。
心の傷があまりに深いと時にそれは相手への復讐心となってしまうことがあります。
相手が憎い、仕返ししたい、復讐したい、とまでいってしまうのです。
でもきっと理性でそれを踏みとどまらせることが私たちはできているのではないでしょうか。
ところが理性で踏みとどまったとしても、その負の感情をどうしたら解消できるのかが悩みどころなのだと思います。自分の中で解消できなければいつまでもその気持ちは自分の中で湧き上がって自分を苦しめることになります。
今回はそんなケースです。
A子さんは親友だと思っていたB子さんにひどく傷つけられたと言います。
「私は彼女がとても好きだったんです。子供のころからずっと学校も一緒で親友だと思っていました。でも最近になってあっちこっちで私の悪口を言っていることがわかって、とても傷つきました。」
「そうでしたか、お辛い経験でしたね。どんなお気持ちになられたのか、今どういうお気持ちなのかお話ししていただけませんか?」
「それがわかった時は頭が真っ白になりました。何をどうして家に帰ってきたのか覚えていないほどです。彼女が私を裏切っていたなんて信じられない信じたくないという気持ちでした。それほど長い付き合いでしたから。
今は許せないという気持ちのほうが強い気がします。」
「そうですか、許せないんですね。」
「はい、許せないです。」
「もしできるならどうしたいですか?」
「私が傷ついた分彼女にも傷ついてもらいたい気持ちです。」
「たとえば?どういう方法で?ですか?」
「こちらも相手の悪口を言いふらすとか、面と向かって相手を罵倒するとか、です。」
「できますか?」
「はい、私はできると思います。」
「わかりました。それではもしそうしたとしたらどうなるか考えてみましょうか。どうなるでしょうね?」
「お互いに傷つきあい続けてどちらも際限なくやり続けることになると思います。私も彼女もボロボロになるかもしれません。」
「そうなったときの自分を考えてみてくださいますか?イメージできます?」
「はい、やってみます。」
しばらくして私はこう彼女に言いました。
「それをやり続けたいですか?」
「ダメです。やり続けると自分が壊れるかもしれません。」
「そうですよね。」
「それじゃどうしたらいいんでしょう?」
「あなたのお話をうかがっていてあなたはとても聡明な方だと私は感じましたので、一つだけ方法があります。お聞きになりたいですか?」
「そんなことできるんですか?聞きたいです。」
「簡単ですよ。それはね、あなたが幸せになることです。」
「ええ?!幸せになるんですか?」
「そう、あなたが幸せになればいい。幸せを感じながら暮らすことです。」
「だって・・・そんなことできるかしら。。」
「幸せになるって、傷ついたままの今の自分では居続けない。そう決めてごらんなさい。
そうするとどうなるかイメージできますか?」
「やってみます。」
「どうでしょう?」
「はい、イメージできそうです。」
「どういう気持ちですか?」
「なんだかとってもいい気分です。」
「最初の気持ちと今の気持ち、どちらの自分でいたい?」
「今の自分のほうがいいかな。」
「そうですか。それじゃそうすることにしますか?」
「そうですね。できればそうしたいです。」
「さて、ところでですが、そういうあなたを見て彼女はどう思うかしらね?」
「あ~、そういうことですか。。。なるほど・・です。」
「それじゃ、まず何をしましょうか?」
「今朝行きつけの美容院からセットの割引はがきが来てたので行ってきたいです。」
「そうですか、きれいになってどこへ行かれます?」
「新しくオープンしたレストランにほかのお友達を誘っていこうと思います。ランチがおいしそうなんです。なんかこういうことを考えるとワクワクしてきますね。なんだか気持ちがすっかり楽になりました。」
「そうでしたか、楽しんできてくださいね」
もともと理性的で行動力のあるA子さん。こういう方が来られたとしたら私ならきっとこういう対応をするかなということで書いてみました。きっと立ち直っていかれると思いますよね。
マイナスの感情にきちんと向き合うということを出発点に自分がどう行動するのか、それもご自分で決めることができます。
ご自分が幸せになる選択をされるようお手伝いをすることは可能です。相談会等ご利用くださいね。
まずはメルマガから読んでみませんか?LINE登録はこちらから パソコン・スマホから読みたい方はバナーをクリックしてくださいね。
2022・10・21
「自分だけ向いてほしい?」チクる人の心理

チクる人の心理とは?
チクるという行動をされる方、皆さんの身近にもいらっしゃるのではないでしょうか。
Aさんはある日久しぶりに友人のBさんと会うことにしました。
たくさん話をしておいしいものを食べてすごく楽しかったのですが、帰り際にBさんがこんなことを言ったのです。
「そういえばね、この間Cさんがあなたの事悪く言ってたよ。」
Aさんは一瞬ギョッとしましたが、動揺を隠して「そうなの?」と流そうとしました。でも、Bさんはその様子を話し始めました。
その後なんでもないように笑顔で別れたものの何とも言えない嫌な気持ちになっています。
「う~ん、Cさんがどうこう言うよりも、Bさんのほうが嫌だな。」と思ったと言います。
この辺はCさんに怒りが向く方もおられるでしょうが、Aさんの場合にはBさんへの嫌悪感が強かったようです。
「どういうことを考えられましたか?」
「う~ん、私のためを思って言ってくれたのかもしれないけどわざわざCさんのことを伝えて私を嫌な気持ちにさせることに何の意味があるのかしら、と思ったんです。」
「なるほど、何の意味があるのか?と思ったんですね。その辺はどうお考えですか?」
「あなたのためよと言いながら私の気分を悪くさせるってなんか違うんだよなあって。」
「そうですよね。どうしてほしかったですか?」
「いいことなら伝えてくれるのはうれしいけど、そうじゃないなら別に聞きたくないと思います。」
「Cさんについてはどうお考えですか?」
「そうですね、機会があったらちょっと確かめようかなって気持ちになっています。」
「Bさんについては少し距離を取ろうかと思います。以前もこういうことあったような気がするんです。二度目じゃないかな。。」
「Bさんはどういう気持ちだったんでしょうね。」
「そうですねえ、私はあなたの味方よ、だから教えてあげる。みたいなね。。」
「そうかもしれませんね。ほかに気が付いたことがありますか?」
「それを伝えることで私とCさんを離したいのかなあ、とも思います。」
「離すとどうなるのでしょうね?」
「どっちも自分にとってオンリーワンになるってことなのかなあ・・」
「ああ、そうかもしれないですね。自分が目の前の相手にとって特別になりたいのですかね。」
「ええ、そんな気がします。」
「相手がそう思うほどあなたが特別な人だということにもなるかもしれませんが。」
「まあそういわれるとそんなに悪い気持ちはしないですけどね。」
対人関係論で人間関係を見ていくと実に様々な局面の可能性が出てきます。
悪口を言ったというCさんに対してよりも、それを伝えたBさんのほうが嫌われてしまったようです。
今回は目的は何かをもとに解説してみましたが、人によって目的はいろいろ考えられます。関係性や何を得たいのかはひとそれぞれなのです。
人と人とは社会の枠組みの中で様々な関係性でつながっているのですから、相手の目的を見ながら、より良い方向へ発展していける人間関係を築いていきたいものです。
今回もお読みいただきありがとうございました。
2022・10・20
第三者が加わると人格変わる?職場の先輩の不思議

二人だといい人なのに
第三者が入ると途端に意地悪になる
人間関係には不思議だなと感じることが起きます。
2022・10・18
「自分の大事なプライベート領域にずかずかと踏み込まれたとき」友人関係トラブル

自分の課題・領域に
他者を踏み込ませない
意外と難しいのが友人関係です。学生時代と違って、それぞれが大人になり、抱えている事情が違うと感覚もどんどん違ってきますよね。
今日はそんなお話です。
A子さんは久しぶりに小学校時代からのお付き合いのあるB子さんと会いたくなり自宅へ来てもらうことになりました。
ところが約束した時間になっても待てど暮らせどB子さんは来ません。
携帯に連絡したところ、悪びれる様子もなく「これから行くから。Cさんも一緒に行きたいっていうから連れていくね。」
と言います。
A子さんはびっくりしてしまいました。「なんでCさんが一緒なの?あの人一人で話して、しかも自慢ばっかりするから、やだなあ。。」
そんな気持ちとともに
「時間に遅れてるのに、待ってるのに。それにあなたとだけ会いたかったのに。」そんな気持ちもプラスされたこともあり、がっかりした気分になってしまいました。
それでも気を取り直して約束から2時間遅れてきた二人を出迎え、その日は過ごしたのですが、B子さんとCさんは、お子さんのお勉強をCさんに見てもらっている関係もあり、先生と生徒の保護者なので、Cさんはいつにもましてさらに自分が中心に終始話をし続け、最後にはあまりにも自慢ばかりするCさんにA子さんが不機嫌を隠せなくなってしまいました。
二人が帰った時には疲れ切ってしまいました。しかも何となくもやもやが収まりません。
Cさんの前では言えないこと、聞きたいこともたくさんあったのに、なんであの人勝手に来るの?とそう思ってすっきりしないのです。
それでB子さんに電話をして「あなた一人で来てほしかったこと」を伝えました。B子さんは「話のついでにあなたに会うことをCさんに話したら自分も行くと言い出して断れなかった。だってうちの子の先生だし。」と言います。
その後A子さんはCさんとは何となく疎遠になってしまいました。
A子さんの中にCさんへの怒りがあったのです。
「私とB子さんとの関係に私への何の断りもなくずかずかと入ってきて。」という怒りです。
なんだか大事な自分のエリアを土足でべたべたと踏み荒らされた気持ちがしました。
帰り際になんとなくA子さんの不機嫌さを感じたCさんから、その年明けの年賀状に「言いたいことがあるならはっきり言ったらいいと思う。」という内容の一言が書いてありそれっきりになりました。
自分は何をどう間違ったんだろう?とA子さんは思っています。
「先生ならどうされますか?」
そうね、とっさには「あなた一人で来てほしい」って言い出せないかもしれませんね。でも、言えたのでしたらそのほうがよかったでしょうね。
「でも二人の約束に自分も知っているからっていう理由でずかずかと入ってくるほうが問題じゃないですか?」
「そうね、そうかもしれない。あなたにとってはとても嫌な気持ちになったと思うし。どうすればよかったと思う?」
「認めなければよかった、のかしら。。。あ、そうか、私が認めなきゃいいんだ、ってことは私・・なのかしら。。」
「次からこういう時どうしますか?」
「あらかじめはっきりと、あなた一人で来てくれないかなとそう伝えたいと思います。」
「そうね、Cさんにはどうします?」
「今回は遠慮してもらいたいと伝えればいいんですよね。」
「そうね、できるならそのほうがいいかもしれないです。」
「言えるかなあ。。」
「言わないとどうなるかしら?」
「あ、ですよね。。」
自分の課題に踏み込まれたとき、NOを言える人のほうが少ないと思います。それでも勇気をもって言わないと、いつまでもこういう状態は続きます。
うまくいかなかったときというのはじぶんひとりではなかなか状況の把握は難しいです。一人で抱え込まずにぜひ身近などなたかにご相談してみてくださいね。お話をすることで事態が明確になりすっきりすると思います。
アドラー東北ではご相談会でこういうお話もお聞きしております。機会がありましたらご利用ください。
2022・10・12
「上の子可愛くない症候群」その原因は赤ちゃん返りにヒントあり、そしてその対処法

「お姉ちゃんなんだから・・」が
子どもの劣等感を膨らませる
「お姉ちゃんなんだから、もっとしっかりしてよ。」
「お兄ちゃんなんだから下の子を可愛がりなさい。」
「なんでもできるでしょ?自分のことは自分でしてよ。」
下のお子さんがまだ小さいとある程度成長された上のお子さんの方にイライラしてしまう「上の子可愛くない症候群」に陥っておられるかもいらっしゃると思います。
下の子に手がかかる分上のお子さんには手が回りませんから、つい「もっとちゃんとやって。お姉ちゃんなんだから」とイライラしてそれをぶつけてしまうのです。
小さいほうのお子さんは何をしても許せるのに、上の子に対しては厳しくしてしまう。上の子が時に憎いと感じるほど嫌いだと思ってしまう。
同じように接することのできない自分は親としてダメなんじゃないか、失格なんじゃないか、上の子にイライラして、まるであたっているかのような自分はダメな親だよなあ、とそんな風に感じてしまうようです。
少しでも先に生まれたんだからもうちょっとできてもいいんじゃない?そう思うお気持ちすごくよくわかります。だから期待してしまうのですよね。そしてその通りにならなくてがっかりし、それが怒りに変わってしまう。
さて、こんな時お子さんは実際どうなのでしょう。赤ちゃん返りで考えて見ましょう。赤ちゃん返りというのはその言葉通りに下のお子さんがうまれたことをきっかけに上のお子さんがまるで赤ちゃんのように戻ってしまう。やれることもしないでやってもらおうとする、以前より手がかかるという状態です。
どうしてこうなるかというと、下のお子さんにあなたをとられまいとしています。これが赤ちゃん返りの目的です。お子さんが小さければ小さいほどお子さんの行動の目的は親の愛、注目を得ることです。ですから生まれてきた赤ちゃんに親の愛をとられると感じて、自分も何もできない赤ちゃんに戻ればまた以前と同じように同じぐらいの愛をもらえるのではないか、愛されるのではないかと感じています。
かといって小さいお子さんに手がかかるのですから、同じように上のお子さんに手をかけるのは限界がありますよね。
こんな時どうするかというと上のお子さんにお手伝いという形でそばにいてもらうことができるのではないかと思います。
簡単なことでいいのですから「おむつ持ってきてもらえるかな?」ー「ありがとう。助かるよ。」
「赤ちゃんにミルク飲ませるのちょっとやってみる?」ー「上手にできたね。ありがとう、助かるよ。」と
「赤ちゃんのお着換えをしたいんだけどどの服がいいと思う?」と選んでもらう。「それを選んでくれたの?可愛いわね。素敵。」などなどお子さんの年齢に応じて育児に参加してもらながら声をかけていきます。
そうするともちろん親の愛、注目してもらえているという満足感も湧きますし、手伝って役に立つことで自分もとても役に立っているという感覚をお子さんが持てると思います。
また母親と一緒に赤ちゃんに関わることで一緒に育児をした感覚になり手をかけた分「可愛い妹(弟)」と感じるようにもなるでしょう。
上の子どもにも育児に参加してもらう。こんなに小さいのに無理よとお感じになるかもしれませんが、歩ける、口を聞けるのであればやってもらえることは可能です。「お姉ちゃんだから」という言葉で赤ちゃん返りされるよりも、ずっとお子さんが素直にお母さんの方を向いてくれるきっかけになると思います。
どうぞお試しくださいね。
2022・10・8 「ねちねちねちねち」モラハラに潜む背景とその乗り切り方

「相手の意表を突く」
というやり方
「ねちねちと同じことを何度も繰り返し繰り返し嫌みを言われるんです。」
ご家庭でご主人からこういう扱いを受けていませんか?
「私の話は聞いてくれないし、ああしろこうしろばっかりで、挙句にできてないじゃないかとねちねち責められてすごくつらいんです。」
まるで自分という人格を否定されたような気持になってしまうとそう感じられるようです。
いたたまれなくなった奥様の側が離婚を切り出したり、社会的・精神的な自立を目指されていく、そういうケースが多いかなとお見受けします。
さてどうしてこういう態度をご主人は取るのでしょうね。
これは一つのケースとしての考察ですが、イヤなことがあってむしゃくしゃするとか、自分に自信がないとか仕事がうまくいっていないとか、そのイライラを身近で一番弱い存在にぶつけることがあるかと思います。
自分はダメだと思いたくない、認めてくれ、イライラを解消したい、仕事がうまくいかないうっ憤を晴らしたい。
などの目的がありそうです。目的そのものは悪くないのですが、いかんせんその目的を達成する方法が悪すぎます。
奥様にあたるのは、迷惑な行為です。とても傷つくことですよね。していいことにはなりません。
ですからいつかそのことに直面してもらえるように奥様もいろいろ考えておくことが必要になってくるでしょう。我慢し続ける必要はないのですから。モラハラを受けているあなたが悪いわけではありません。
そういうことを考えたそのうえで、一時的な方法として「意表を突く」という対応ができるかなと思います。
モラハラ発言をされると、たぶん言われたほうが黙ってしまうのではないでしょうか。そうすると相手はいつまでもやめないのです。黙っているのをいいことに言いたい放題になります。
また言い返す際でもたぶん「反抗的」な言葉を投げかけてしまうかもしれません。そうすると相手はますますヒートアップしていきます。
どちらも逆効果です。
ですので「意表を突く」一言で相手の怒りを収めるという方法でしのいでみてください。これはあくまで一時しのぎです。
相手が予想だにしなかった言葉です。たとえば「そんなに嫌なことがあったの?」「そんなにつらいの?」「そんなに仕事が大変なの?」
相手が驚いた顔をしたらしめたものです。たぶんその矛先の鋭さが緩むと思います。
自分がひどい言葉を投げかけたら妻が思いやりの言葉を自分に投げ返してきた。この対処は試してみる価値があると思います。少なくとも「ねちねちと」は、その場は止まる可能性が高いです。
そのうえで一度ご相談ください。あなたの状況をお聞きした上でこれから先どうするかについてご支援できると思います。
モラハラまで行かなくても夫の言動がひどいなあと感じることのある方は、どうぞ一度お話にいらしてください。
2022・10・6 「休日に出かけようとする妻に、俺の昼めしは?という夫」依存傾向の強い夫に自立してもらうには?

できることを少しずつやってもらえるように働きかけていく
2022・10・5 「どうせ僕なんか・・・」その言葉がお子さんから 出てきたら、劣等感の使い方を考えたい

自信を取り戻して課題に取り組めるよう
勇気づけよう
2022・10・4 「謝ってほしいわけじゃない・どうしたらいいのか考えてもらいたいんだ。」その場しのぎの謝罪が相手からでたら変えたいこと。

「謝るよりもこれからのことを考えてほしいな。」そう思っていませんか?
2022・10・3 「親が嫌いな自分が認められない、許せないと感じてしまう」毒親に悩む自分とおさらばする方法

「親は嫌ってはならない」
そう思っていませんか?
「私は親が嫌いです。」そうはっきり言いきれる人はほとんどおられません。
なぜなら「親を嫌うこと」は道徳的に許されないという日本人特有の価値観が根強くあるからです。
そして親のほうもまさか自分が嫌われているなんて思いもしません。
ですから子どもだけが親のことで苦しみ続けるという現実があります。
「自分は親が嫌いだ。でもそれは許されないことで、そう感じる自分はダメな人間なんじゃないか。」と自分を責めている方がたくさんおられます。
そして口を閉ざして自分一人が我慢をする、し続ける、そういうケースをたくさん見てきました。私自身も親が嫌いで、でもそれは本当にそう思っていいことなのかを考え続けてきました。
でもどう考えても嫌いなものは嫌いなのです。そう思ってはいけないという自分はいったいどこから来たのか。
周りにどう思われるのか、ということを気にする自分もいたと思います。また自分が親という存在をどうとらえれば自分が楽になれるのかとも考えました。
そんな自分ですが、ようやく親のことも楽に考えられるようになりました。今回は「親を嫌いだと思いながら嫌いになれない、なってはいけないという考えにとらわれて苦しんでいる方へ」少しでも気持ちが軽くなる方法について書いていきたいと思っています。
<親を嫌ってはならないという価値観はどこから来たのか?>
日本人が持つ多くの価値観はおおむね大陸から来たものに由来しています。その中でも特に5世紀に日本に入ってきた「儒教」の影響が大きいです。
その儒教は江戸時代に為政者によって「人民への価値観の刷り込み」という形で幕府存続のために行われました。儒教の中の朱子学という学問が民間に広められたのです。朱子学は上下関係の中で上の人にとって都合のいい側面がある学問です。為政者にとって都合のいい思想や価値観を人民に植え込むことで人民が為政者に逆らわない土壌を作りたかったのだと思います。
その中には「師を仰げ」といったことや「親孝行しなさい。親を大事にしなさい」といったことも含まれています。上の立場である人にとって都合のいい思想・価値観とはそういうことです。
その価値観の刷り込みが今の私たちを苦しめる要因になっているのです。師に逆らってはいけない、親に逆らってはいけない、罰が当たると、私たちは思い込まされてきました。
今は皆が平等な民主主義の時代なのに、私たちが持っている価値観はいまだ上下関係に基づいたものが続いているのです。これが私たちを苦しめている価値観の実態ではないでしょうか。
<民主主義の世の中での親子関係はどうあるべきなのか?>
日本国憲法に記載されているように私たちはみな平等です。年齢・性別・信条・職業によって差別されることなく皆が等しく一人の人間として尊重されなければなりません。
これはタテの関係ではなくヨコの関係ということになります。そうすると当然のことながら親子関係もタテではなくヨコの関係であるということになります。
親と子が対等であるとすれば、親が子どもにしている教育は子どもを尊敬し信頼してというスタンスに基づいたものでなければなりません。
ところがいまだに親のほうが上で子どものほうが下であるという感覚で子育てが行われているのです。そのことに何の疑問も感じていない方のほうが多いようです。
「子どもは教育をするもの」と考え、指示をしたり自分の思い通りにしたり、暴力や暴言、怒りの感情を使って子どもを思い通りにする親は後を絶ちません。
このことによって子どもは親を嫌いになっていきます。自分が尊敬されている、一人の人間として大事にされているとは感じられないからです。
ところが先に挙げた価値観の刷り込みがありますから、そういう自分はダメだとか、人として許されないと子どものほうが感じてしまうのです。
対等な人間として子どもという存在を認めることが親のほうでできないのであれば、それは子どもが嫌うのは当然ではないでしょうか。
ですのでご相談に見えられた方には「親が子どもが嫌がることをすれば嫌われるのは自然の理です。」という風にお伝えしています。そのことでホッとされ、初めて自分の気持ちを受け入れてもらったと感じる方は多いです。
<親との関係を自分が楽になるように捉えなおす方法・1>
それでは実際に親との関係に悩み続ける自分とどうやったらおさらばできるのか、について書いていきます。
まず一つは「親は親になる準備をして親になる勉強をして立派な親になれそうだから親になった、というわけではない」ということです。
誰もが親になるために何が必要でどうあればいいのかをわからないまま親になっているのです。親も不完全であるということです。
ところが私たちは「親だからこうあるべきだ」という理想を親に対して期待してしまいます。親になる方法を誰も教えていないのですから、親も未熟なのです。
子どもとして過度に親に期待していないかどうか、その辺を検証してみることも必要だと思います。私自身は「親だからと言って一人の人間であることに変わりはないのだから、できないこと、わからないこと、かけていることがあるのは仕方がないんだ。」と考えられるようになってから、少しずつ親に対する憎しみの気持ちが薄れていったように感じています。
<親との関係を自分が楽になるように捉えなおす方法・2>
次に「行為と行為者を分ける」という考え方で親をとらえなおすという方法があります。私たちは相手の行為イコール相手の人格と考えがちです。
自分の「親の~なところが苦手だ」と感じる部分はあくまで相手が時に使う対人関係の方法であって、またそれは親の一部分であり、その方法が人格とイコールではないと考える捉え方です。
アドラー心理学は方法論ですから、相手のよろしくない行動について「目的があって相手役に対してその行動を使っている」ととらえます。
その考え方で行くとたとえば子どもに対する暴力・暴言についてはどうなるかというと「相手を自分の思い通りにしようとして子どもという相手役に対して暴力・暴言という方法を使っている」という解釈になります。
これですと、あくまで方法が悪いので、相手が悪いということにはつながりません。
私の親で考えると、私という子どもを親は愛してくれていたし大事に思ってくれていたが、子どもに対して使っていた方法がそうではなかった、私にその気持ちが伝わる方法を使っていなかったのだという解釈ができます。
この二つの方法で私自身は親についてのこだわりを手放すことができました。これらの方法についてはご相談会等でお話をお聞きして方法をお伝えすることもできるかと思います。動画でも毒親について先日対談をしております。メルマガ読者限定ですのでまずはメルマガのご購読ご登録をお願いいたしたいと思っています。
2022・9・28 「欠点ばかりの自分に自信がない」 実は欠点が多い人ほど幸せに生きられるという視点

欠点はなくさなくていい
欠点こそ伸びしろだという発想
ご自分の長所についてお聴きすると全く出てこず、欠点ばかりが出てくるというのは、アドラー心理学を学び始めた時にはよくあることです。
「欠点ばっかりで自信が持てないんです。こんな自分でいいんでしょうか。」
「自分にはいいところが一つもありません。あ~あ、自分ってこんなにダメなんだなあ。こんな自分には価値がないんです。私なんかいないほうがいいんです。」
「探してもいいところなんか見つかりません。自分でもびっくりしてしまいます。悪いところだらけです。」
ほんの少しの長所とずらずらと出てくる欠点。皆さんがびっくりされます。そしてどうしてこういうことになるのかと不思議にさえ感じられる方もおられます。
自分の中のよくないところにばかり目が行っていますのでこれでは自分が好きになれないのは当然だと思われるようです。
自分が好きだと思えてこそ本当はお子さんや他者も好きになれるのですが、かつて私もほとんど自分の良きところに目がいかず、自分のよくないところや出来ていないところにばかり目が行っていました。ですので、驚かれる気持ちや落ち込む気持ち、自分が好きになれない気持ちはよくわかります。
ところがこのたくさんの欠点こそ、実は自分を好きになるポイントでもあるのです。今日はその辺を解説とどうとらえていくのかについて書いていきます。
「物事は裏と表で成り立っている・欠点と長所も表と裏である」
何事も表と裏は一体です。表があるということは裏もあるのです。同様に物事はある視点から見るといいことでも別の視点から見るとよろしくないこともあります。
一方からばかり見ているとそれが見えなくなります。何事も両方の側面を持ち合わせているのです。それはご自分の持っている性格特性も同様です。
あなたの持っている性格は一つの側面からだけで捉えるのではなく、別の角度・二つの側面から捉えることができるのです。
欠点と長所も裏と表です。そうすると欠点は別の視点でとらえると長所にもなります。欠点が多い人は長所になる資質をたくさん持っているということにもなるのです。
アドラー心理学は「持っているものをどう使うか」という使用の心理学です。ですから今「欠点」として捉えているあなたの特性は、使い方次第で「長所」にもなるということになります。
たとえば「人見知り」という欠点は、「他者に対して慎重である」という使い方に変えれば長所になりますし、「頑固」であるという欠点は「自分の大事にしている価値観をしっかり持っている」という長所になります。
ですから欠点を無くす必要もありませんし、使い方さえ変えればあなたの長所はたくさんあり、かけがえのない大事な素質であるということになるのです。
欠点ばかりのあなたは、実は長所として使える資質をたくさん持っているということになります。捉え方の視点とその資質の使い方を変えるだけです。
今欠点だらけで自分が好きになれないと思っておられたとしても、それがあなたの長所として活かせて、よりよく生きるための伸びしろとして使えるとしたら、あなたは今よりも自分を好きになれるのではないでしょうか。
自分に自信がないという方ほど、一度ご相談いただければと思っております。
2022・9・27
「わかってほしい」「私を理解してほしい」
夫婦のきずなを取り戻す最初にすべきこと

夫婦のきずなを取り戻すには
まず話してみること
「自分のことを理解してくれないんです。夫も家族も親さえも。」
そんな風に感じて自分の存在そのものが危うく感じたり、まるでないもののように思っておられる方は、最後にこうおっしゃいます。
「自分なんかいてもいなくても同じなんです。どうしたって理解してもらえない、わかってもらえないんだから、どうせ自分なんかいいんです。」
こういうご相談を受けると私はとても心が痛みます。なぜならかつて自分もこうだったからです。
誰も私を理解してくれない。私は一人だ孤独だとそう感じていました。ですからそういう気持ちになるのはとてもよくわかります。
誰も自分のことになんか関心を示してくれず、私の話に耳を傾けてくれず、理解なんてしてくれることなどないと思い込んでいました。
「どうしてそう思われますか?」そうお聞きしてみると「話を聞いてもらえない」「相手にしてもらえない」ことが多いと思うのだそうです。
特にどなたとの関係を改善していきたいかお聞きすると大体ご主人との関係とおっしゃることが多いです。
「子どもはいつか離れていきますが、夫婦二人で家にいる人生が長いことを考えるとご主人との関係をなんとかできれば、というお気持ちがあるようです。
「ご主人はどういう方ですか?」
「あまりしゃべらない人で、仕事が忙しくいつも疲れていて、話をしようとすると困った顔をするので、つい言葉を飲み込んでしまうんです。」
ご自分から働きかけることをあきらめてしまっておられると感じました。
「確かめたことはありますか?」とお聞きしましたら「いえ、そういうことを言ったらどうなるか怖くて。」
「怖い?んですね。ご主人が怖いのですね。怒ったりする方ですか?」
「いいえ、めったに怒ったりしません。でも話さないので何を考えているかわからないので。」
「ご主人とお話しできるタイミングはありますか?」
「はい、休日の昼とか平日だと帰宅してから寝るまでの間とか。」
「確認したいんですが、ご主人と仲良くなりたいですか?」
「はい、出会ったころのように何でも話せるようになりたいです。」
「あら、出会ったころはいろんなお話をなさっていたんですね。」
「ええ、あの頃は若かったし、いろんな話をしました。」
「そう、今は若くないからできない?」
「あ、そうか、共通の話題がないからかもしれませんね。子供の手も離れつつあって別に話さなければ話さなくてもいいわけですし。」
「共通の話題はお子さんとのことだけでしたか?」
「そうですね、今まではそうでした。」
「何気ない事で構わないので、話したいということを伝えてみませんか?もし可能ならあなたの気持ちも。」
「今までそんなことをしたことがないし言ったことがないので、できるかなあ。」
「でも始めて見ないと今の状態は変わりませんから、ダメもとで話しかけてみてはいかがでしょうか?」
「どんなふうに言えばいいでしょうか。」
「そうですね。どんな言葉だったらかけられそうですか?」
「う~ん、今日あったこととか、ですかね。」「そうですね。あとはねぎらいの言葉から言ってみるという方法もありかなと思うんです。」
「ねぎらいですか?」
「ええ、今日もお仕事お疲れ様、とかね。」「恥ずかしいなあ。。」
「でもきっとうれしいと思いますよ。お話聞いてもいいかなってそんな気持ちになってくれるかもしれません。」
「わかりました。とにかくやってみようと思います。」
今までお子さんのことが中心に回っていたご夫婦が、いずれ二人だけになる日は誰にでも来るのです。その時になって夫婦の会話がなく関係が危うくなっていたというのはどなたにも起こりえます。
できることはとにかく話をすること。それで最初のうちはぶつかるかもしれませんし、うまくいかないかもしれませんが、あきらめないで続けていくことがコミュニケーションを上手にするコツです。うまくいったときのことを繰り返していけば、今からでも夫婦の関係は改善が可能です。
双方が「関係を修復したい」と思いながら、何をどうしていいのかわからない、そんな方は多いのかもしれませんが、必ず方法はあります。あきらめずにご相談いただければと思います。
2022・9・23
「お母さんのせい!」親への責任転嫁のなぜ?どうする?

子どもが自分のことを自分で
できるようになることが大事
「お母さんのせいだ。お母さんが悪い。お母さんのせいで僕が怒られたじゃないか!」
お子さんがそんな言葉を発してることはありませんか?
この言葉を聞いたときたぶんこんな気持ちになったのではないでしょうか。
「え?!私が悪いの??なんで?だってもともとはあなたの問題でしょうが?」
あれこれ手を尽くしてしてあげているのに、なんでこんなこと言われなきゃならないの?
そんな気持ちになってしまうことでしょう。
忘れものが多いという小学校4年生のA君。学校の先生から何度か電話が入りお母さんは忘れ物をしないようにと声をかけあれ入れてこれ入れてと一緒に次の日の準備をしておりました。
それでしばらくは忘れ物の件で先生から連絡が入ることはなくなりましたが、そんなある日たまたま一つだけ入れ忘れてしまったものがありました。
帰宅したA君はものすごく怒っています。自分が叱られたのはお母さんのせいで、学校の先生にも「また忘れたのか?」と久しぶりに厳しく言われてしまったようです。
A君とお母さんは大げんかになってしまいました。
「もとはといえば自分のことでしょうが?自分でやれないからママが手伝ってたのに、たまたま一つ忘れたからってママのことを悪く言うなんて信じられない。ひどい子ね。」
「別に頼んでない。お母さんが勝手にしゃしゃり出てやってたからやってもらってただけだ。自分から手を出しておいて間違うってなんだよ。俺、みんなの前で怒られて恥かかされたんだぞ。」
自分が悪いなんて全く思っていないわが子にあきれてしまい話にならないと感じたお母さんは、「もうあなたの事なんか知りません。」と言って、買い物に出かけてしまいました。
なんだか歩いているうちにとても悲しい気持ちになってきます。「あなたのためってやってたのに、なんで?どうして?こうなるの?」涙があふれそうになります。
いつも買い物をするスーパーへ行く途中の公園にはベンチがあり、そこへ腰かけてしばらく気持ちを落ち着かせることにしました。
だんだん気持ちが落ち着いてきたところで「やっぱり変だ。何がが違うんだ。でも何がどう違うのかがわからない。」と思いいたります。
変だという自分の気持ちを納得させたくて、起こっている事態をすっきり理解したくてご相談に来られる方もおられるのです。
「なんか変だなって感じたんです。それでお聞きしたいと思って。」と相談会へいらしたりメールやお電話をくださる方もおられます。
さて何がどうなってこういうことが起きるのでしょう?
お母さんは、忘れ物をしないようにすることはお子さんの課題だとわかっておられます。でもその課題をお子さん自身にやってもらうのではなくて自分が指示してやってしまっていました。
そうしたら自分のせいにされてしまったのです。
お母さんにお子さんにどうなってもらえればいいと思っていますか?ということをお聞きしましたら、私が手をかけなくても自分でやれるようになってくれればいいと思いますとお答えになりました。
それでお母さんがメインになってお子さんの課題を片付けていると自分でできるようにはならないこと、お母さんをあてにしてしまい期待してしまい、自分で何をもっていけばいいか考える必要がないので考えなくなってしまうこと、人任せの子どもになってしまっていることなどをご説明しました。
「でも全部一人でやらせると間違って忘れ物をしてしまうのでは?」とおっしゃるので、ご心配でしたらこうおっしゃったらいかがですか?とご提案しました。
「もし一人でできているかどうか不安だったらお母さんに声かけてね。」
これですと「別に頼んでない。勝手にやった」とは言われません。いずれにしてもお子さんはお母さんのせいにすることはできなくなります。
皆さんお分かりの通り課題を分けた後で共同の課題にする方法の応用ですね。
課題分けに抵抗を感じる方も、いろいろな工夫、たとえば提案の仕方などで共同の課題にすることは可能ですし、徐々に本人ができるようになってきたら本人に全部任せて手を離せばいいので安心できると思います。
課題を分けてそれは子どもの課題だからと言って全く介入しないのは場合によっては放任になりかねません。お子さんの様子を見ながら緩やかに臨機応変に適応していくのが望ましいと言えと思います。
いずれにしても「お母さんのせい」と言われたら今一度今のご自分の対応がお子さんが自分でできるようになることにつながるのかどうか考えて見られることをお勧めします。
2022・9・22
「私だけが悪いの?」子供の問題の責任を全部妻に押し付ける夫に対してどう働きかければいいのか

子どもの問題が起きた時にこそ
普段の夫婦関係が問われる
お子さんに問題が起きたとき、あなたはご主人からこんな風に言われたことがありませんか?
「お前がしっかりしつけをしないからだ。」
「親としてあまいんじゃないのか?!」
「育て方間違ったんじゃないのか?」
「お前のせいだからお前が何とかしろ!」
こんな言葉をかけられて、こう思われたのではないでしょうか。
「全部私の責任って・・ずいぶんひどいことを言うのね。私だけが親なわけではありませんよ。あなたは何をしてくれたの?子供のことを全部私にやらせて、いざ問題が起きれば全部私のせいにするってずるくない?」
そうですよね、あなたの考えていることはよく理解できます。お子さんのことを丸投げして自分は仕事だと言えば何でも通ると思い、家のことも何もしない夫。
いまだにそういうご主人がいるのは驚きでもあり残念でもあります。
こういうことがあると一人の人間として傷つきますし、親としての自信を失ったりすることにつながってしまいます。
その結果として「言われないようにしよう」と思うあまりに過度に子どもに対して介入が増えたり、ご自分に対してもお子さんに対してもさらに厳しくなってしまうことも起こるのです。
そうするとお子さんは反抗的になりますます問題行動を起こすという悪循環が起きてしまいます。
その根底には「言われたくない」「ちゃんとした子どもに育てないと」という思いがあるのではないでしょうか。
さて、こういう場合にはどうしたらいいのかについて書いていきます。
まず夫婦のコミュニケーションが普段疎かになってしまっていることが浮き彫りになるかなとそう思うんです。
自分がやったほうが楽であるとか、自分がやったほうが早く済むとか、いちいちご主人に話すのは面倒だとか、家事や子育てに忙しいとそうなってしまいがちですが、普段の夫婦関係がどうであるかがこういう時に問われるのは確かだと感じています。
普段からご主人様にも子育てにかかわってもらう、お子さんとの触れ合いを機会を設けて持ってもらうなどの工夫をして、ご主人にも育児にかかわっているという感覚を持ってもらえればあなた一人に責任を押し付けるといった言動は取れなくなるはずです。
もともとが子育てはどちらか片方がするものではなく、夫婦ともに取り組む問題なのですから、ご主人にかかわってもらうことで当事者意識を持ってもらうしかないと思います。
また自分一人が悪者にされたという感覚が許せないと感じておられることもあるでしょう。頻繁にこういう事態が起きるのであれば、それは「父親としての責任放棄」であることは伝えるべきです。
こういうケースで結論から言えば「あなただけが悪いわけではありません。」多少の影響因はあるかもしれませんが、かといって起こった出来事の責任がすべてあなたにあるというのはかなり論理的に飛躍した決めつけだと思います。
アドラー心理学で考えると問題を起こしたのはお子さんですから、本来ならお子さんが解決しなければならない問題なのですが、それを親だからと言って母親一人の責任にしてしまうのは筋違いではないでしょうか。
お子さんの起こった事態に狼狽している中での上記の「お前が悪い」といったご主人の言葉で、とっさに何も言い返せず抱えてしまい、そのことで長い間苦しむ奥様は多いです。
問題を起こしたのはいったい誰なのか?誰が責任をとるべきなのか、は明確で、それは子どもがすべきことです。こういう勘違いの責任追及は夫婦関係に大きな亀裂を生みます。
「言っても無駄」という気持ちになる前に一度ご相談いただければと思います。
親だからと言って子どものすべてに責任を負わせる必要があるのか、親と子は血のつながりはあっても別の人間ですからそんなことは不可能です。またその必要はありません。
あなたはあなたを責める必要はありません。「お前のせい」と言われてもあなたがそれで傷つく必要はないのです。それは誤った指摘以外のなにものでもないからです。
2022・9・17
家庭内暴力をする子供に対して私には居場所がない、親として価値がないと感じていませんか?

暴力の目的は何か?
から考えていくアドラー心理学対応
意外と多いにも関わらず表面化しにくいのが親子間の暴力です。親が子供に対して、が一般的な認識かもしれませんが、子どもが親に、というのもうちの場合には結構あります。
相談会でお話をお聞きする場合もありますし、オンラインで個人的にお話をお聞きする場合もあります。
ある方は子どもが不登校になり、学校へ行かないことを巡って親子で争っているうちに子どもが母親に暴力をふるいだした。
殴る蹴る、いったん始まるとその暴力はエスカレートする一方で、その方は黙って耐えるしかなくなった。
話を聞いている会場の参加者は皆言葉を失うほどの壮絶な日常がそこにはありました。
「一人になりたい。」その方が最初に言った一言です。
親としての自信を完全に失ってしまっています。
「あなたが暴力を振るわれている時にご主人はいったい何しているの?」
「お前が悪いんだから当然だと。今単身赴任中で家にいないんです。だから自分には責任がない。すべてお前のせいだと言われます。」
ひどいな。。。。まるで子どもの責任は母親一人にあるような無責任な態度に唖然としました。
「わたしが悪いんだから仕方がないんです。でも今家の中にいるのが辛くて辛くて、一人になりたくて、でも誰かに受け止めてほしくてわかってほしくてここに来ました。」
「うん、よく来てくれたね。来てくれてありがとう。」
「辛いことを思い返させて悪いんだけど、お子さんが暴力をふるう時って、何のきっかけがあるか自分で気が付いていることがあれば話してもらえるかしら?」
「自分が子どもに何かを言ったときです。どうするの?とか学校のことを話そうとしたりしたときです。」
「そう、やっぱりそうなんだね。あのね、お子さんに学校のことに関しては働きかけるのをしばらくやめてもらえるかな?今の状態で働きかけはかえって逆効果だから。」
「何とかしたくて、って思ってるんですけど、それをやめた方がいいんですか?」
「うん、しばらく我慢してもらえるかな。ご飯だよとか必要があることは言ってもいいけど、学校のことに関しては絶対に言わないでもらえる?」
「わかりました。やってみます。」
「それとあなたはすごく疲れてるよね。自分をなんとかしないと。」
「何もする気力がわかなくて、何も考える気持ちになれなくて。。」
「自分の気持ちがいくらか落ち着くとか楽になるなってことが何かない?」
「買い物がてら散歩をした時に。。一人になれたときですかね。近くに公園があって、ベンチに座ってボーっとしているんです。」
「そう、それなら外へ出て一人になる時間を持つことを心がけてね。」
「わかりました。」
「もしも今の問題が解決したとしたら何がしたい?」
「一人旅に行きたい。」
「そう、そういう先のこと、自分がしたいことを考えるのもいいんだよね。」
そんなやり取りを最初にして、それから数か月彼女は相談会に通って来続けました。そのたびに今今の必要なアドバイスをしていきました。
学校のことに関してどうしても話さなければならない時、切羽詰まったとき、どう対応したらいいのかわからない時には電話やメールのやり取りで乗り切りました。
「学校の先生から進路のことで電話がありました。どう本人に伝えたらいいですか?」
「先生から~の内容の電話がありましたよ。って事実だけ伝えてね。それ以外は言わないようにしてね。」
そんなことを続けて半年後、ある日こんなメールが・・
「先生と皆さんのおかげで、子どもが学校について自分から話してくれるようになり、これから先の進路を考え始めました。暴力を振るわれることもなくなりました。本当にありがとうございました。また機会があればお伺いしたいと思っています。」
アドラー心理学の目的論に基づいての対応を徹底したことが功を奏したケースです。
「子どもは何のために暴力をふるうのか?」何かを得ようとして、目的があって、その目的を達成するために手段として「暴力」を使っているという風に考えるのが目的論的思考です。
「なんのためか?」と言えば「学校のことを言わないで欲しい」「これからの進路についてあれこれ言わないで欲しい。黙ってほしい」だなと思いました。言葉にできない思い、わかってもらえない思いを「暴力」という形で実現しようとしていると考えました。
まず暴力をやめてもらわないと、と思いました。そのためには暴力を使わなくても目的「親が学校のことを言わない」を達成させればいいので、「学校のことについて言わない」を徹底してもらいました。
あとは徐々にお子さんとの関係を改善していくしか方法がないと考えました。
相談会への参加だけで解決してしまったケースは結構あります。たとえばまだら登校だったものが進路について自分で考え始めるとか、お子さんから自発的に何らかのアクションが起きます。
今あなたを悩ませているどんな子どもの行動にもちゃんと目的があって、その目的達成のために「不適切と思われる方法」を採用しているのです。
アドラー子育てだと「言葉で伝えあう」ことを徹底しますので、「暴力」などという不適切な方法を使う必要がなくなっていきます。
お子さんの不適切な行動にお悩みの方にはぜひまず相談会や個別相談をご利用いただければと思います。
どんな些細なことでも一人で抱えて悩まないこと。話せば活路は必ず開けます。
2022・9・16
「自分さえ我慢すれば・・」共働き夫婦にありがちな
不公平感を是正するには?

フラットに話し合える関係に
なっていますか?
「養ってるのは自分だ。」と妻を下に見る男性はいまだに後を絶たないようです。
「それを言われたら何も言い返せなくなります。だって事実そうなんですから。」
あきらめたようにため息をつく人もおられます。
「お前なんか家でダラダラしてるだけじゃないか。何の価値もない。」
まるで人格否定のような言葉を平気で投げかけるご主人もおられ、深く傷ついている方もおられます。
言葉の暴力です。ですのでDVにも該当すると思います。
子育て中で経済的弱者である女性は言い返せないことが分かっていてそういうことを言うのはモラハラにも該当します。
子育ては立派な仕事です。金銭という報酬は発生しませんが、アドラー心理学では仕事のタスクとして捉えています。社会に貢献する人材を育成する大事な仕事なのです。
ですから女性が専業主婦であっても共働きととらえていいと思います。現実に外の仕事についている方は二つの仕事を持っている状態といっていいでしょう。
そうするとどうしても女性側の負担が増える傾向に偏りがちです。家の中のことや子どもの事は女性のやるべきことと男性が捉えていればそうなってしまいます。
そういう状態で不公平感を感じる女性たちが「自分さえ我慢すれば。。」と考えるのもありがちなことです。
「子どもが小さいので働けないですし、今は何を言われても我慢するしかありません。でもあまりにもひどい言い方をされてとても傷つくんです。平気で人格否定されます。仕事のうっ憤を私で晴らしているみたいなところもあります。働いてお金を稼いでいることがそんなに偉いんでしょうか。自分が上なんでしょうか?」
そういう気持ちを抱えながらじっと我慢している女性が今もおられるのは事実です。
でもそれでは対等な夫婦関係とは言えません。どちらがが我慢して続いている関係とは不健全であり、夫婦間の再構築を考えていかなければならないと思います。
健全な夫婦とはどういうものであると言えるかというと「役割の違いを認め合い、必要な時には助け合い、精神的に自立した大人同士」の関係といえばいいでしょうか。
偏った考え方をもたらしているのは親の世代から引き継いだ「男性とは~である」「女性とは~である」という価値観です。
「男は外へ働きに出る・女性は家で家庭を守る。」その価値観で何の不満も不公平感を持っていなければそれでいいのですが、もしもどちらかが不公平を感じながら我慢しているのであれば、夫婦間の話し合いが必要になっていくでしょう。
普段から話し合える関係が築けていること。不満をそのままにしないこと。お互いに納得のできるところまで話し合うこと。そういう関係を持つことがこれからの夫婦には求められていくのではないかと思います。
2022・9・15
「なんでもかんでもイヤイヤって、どうしたらいいの?」イヤイヤ期の捉え方とその対処法

イヤイヤ期は
成長のあかし
「なんでもかんでもイヤ、イヤって。。ほんとに困っちゃう。」
「ご飯食べる?」「イヤ」
「お風呂入ろうか?」「イヤ」
「ママと遊ぶ?」「イヤ」
こんな調子でお困りではありませんか?俗にいう魔の二歳児、イヤイヤ期。
「一体どうしたらいいの?」そんな風にお感じになられているのではないでしょうか。
お子さんがこの年齢ぐらいは目が離せない時期ですから、24時間子育てしている状態で、せめて日常のルーティンぐらいは今まで通りすたすたとこなしたいと思われるのは当然だと思います。
ところが「イヤ」の一言で今まですんなりできていたことが滞ってしまう。
なだめたりすかしたり時には怒ったりして、なんとかさせようとしてママも疲れてしまいます。これが終わらないと次ができない、その焦りといらいらは相当なものです。
挙句に思い通りにならないお子さんが癇癪を起したりするとお手上げになることもあります。
さて「イヤイヤ期」は、どうして起こるのかというと発達段階で「自分でやりたい、自分で思い通りにしたい」気持ちの表れだと言われています。自己主張の始まりです。
毎日接していると気が付かないのですが、確実にお子さんは成長しているという証でもあるのです。ということは「イヤイヤ期」に入ったなら順調に発達が進んでいるということでもあります。
さてそれではどう対応したらいいのか。少し親のほうもペースを緩めることが一つの方法です。
無理に今までのペースで物事をこなそうとしないこと。「イヤ」なら「イヤ」で少し時間をおいてみる。自分でやりたいようなら差支えない範囲で自分でやらせてみる。
生まれた時から子どもはすでに様々な体験を通して学んでいるのですから、イヤイヤ期も体験から学ぶいい機会になると思います。
自分のやり方でやったほうがママは楽でしょうが、お子さんも同様に自分のやり方を試行錯誤しているのです。それはママの庇護がある安心な体験ができるチャンスではないかとそう感じております。
少しだけゆっくり、少しだけルーティンを緩めて、子どものペースに合わせてみる。そんなことで子供の成長を楽しみながら子育てしていってくださいね。
お子さんの悩みについては相談会で承っております。ご相談のお申し込みはこちらからどうぞ。
2022・9・13
「約束をしたのにどうして守らないの?」子どもが約束を守らないのはなぜか?そしてその対処法

約束の仕方によっては
守ってもらえないことが出てくる
「なんで約束したのに守らないの?」
「だって約束なんかしてないもん。」
「嘘つかないで、この間約束したじゃない?!」
「してないよ。お母さんが勝手に決めたんだ。僕は知らない。」
お子さんが約束を守ってくれない、話し合いをして決めたのに知らん顔をする。
こういうお悩みはあるのではないでしょうか?
せっかく決めたのに約束を守ってくれないと悲しいですよね。つい怒りたくもなります。
「約束したのに守らないうちの子って・・どうして?なんで?」ってとても嫌な気持ちになるのではないでしょうか。
「平気でうそをつくような子供にしてはいけない。」そう感じて、さらに約束を守らせることにやっきとなってしまう。言葉がどんどんきつくなる。
きつい言い方をした後で「あんないい方しなくてもよかったのに。。子どもを傷つけてしまった。」と自分が後悔して自分が最後に傷つく。
子どもも傷つき親も傷つく。こういうことの繰り返しから脱却するにはどうしたらいいのでしょうか。
「約束が守られない時に何が起こっているのか?」
まず、親子関係が「タテ」になっていて、子どもは言われたことを聞かざるを得ない、聞かないと叱られるという日常の状態が反映された中での約束だったかもしれないという可能性があります。
これだと「話し合い」と親が思っていても子どもにとってはただのトップダウンにしかとらえられません。
ですから「お母さんが決めたんだ。」という言葉が出てくるのだと考えられます。まずは親子の関係を根本的に改善する必要が出てきます。「タテ」の関係を「ヨコ」へです。
対等に普段から話し合える関係にあってこそ「双方合意の約束」は成り立つのです。この状態での話し合いでは子どもの方もちゃんと納得して約束していますのでできるだけ守ろうとします。
次に親の意志が明確にあって、そこへ誘導されて約束させられたと子どもが感じているかもしれないという可能性もあります。
「結局僕が何を言ったとしてもママは僕を思い通りにしたいんでしょ?」ということを子どもが察知して、その場しのぎに約束している。
これも約束が守られないケースにはありがちです。「結論ありき」で親が話していれば、親の言うことを聞かないと家庭にいられなくなると感じている子どもは従わざるを得ません。
こういう状態では約束したとしても決して自発的に守ろうとはしないでしょう。
「約束を守ってもらうために必要なこと」
今までタテの関係だった親子関係をすぐにヨコにすることは難しいです。ですので、簡単な方法を一つ書いておきます。
それは子どもに全部決めてもらうことです。親は「こうしてほしい」とか「指示」は一切しません。
親の気持ちはいったん置いて全部子どもに決めてもらえば、子どもは守らざるを得ませんし、親が決めたことという言い訳もできなくなります。
例えばこんな感じです。宿題をなかなかやろうとしない子どもに対して、
「宿題はいつやるの?ママに教えてくれない?」
「テレビを見てからやるよ。」
「そう、ちゃんと自分で考えているのね。助かるわ。」
片づけない子どもに対して
「片づけはどうするの?」
「今度の休みの日にやるよ。」
「そう、あなたは自分でできる子だからお任せするわね。」
そのうえでやろうとやるまいとしばらくの間静観してください。そして確認もしないこと。
この繰り返しで子どもは「自分を親は信じて待ってくれている。ちゃんとしなきゃ。」という気持ちになっていきます。
その間に同時進行で「対等に話し合える」ヨコの関係を構築していけばいいのです。
こういうご相談は「サポート会」や仙台会場で受けております。ご相談のある方はどうぞご利用くださいね。
2022・9・10
「言わないとやらない、少しは自分で気が付いて動いてよ」共働き夫婦にありがちな妻の家事分担への不満

少しは自分から動いたらどうなの?
2022・9・9
「なんか話しにくいな」相手と話がかみ合わない・うまくコミュニケーションできない時に考えたいこと

心を合わせるには
リズムを合わせる
2022・9・5
夫婦の悩み「相手に直してほしいな」と感じたときの
とっておきのフレーズ

夫婦仲良くのコツでもある
意志の伝えあい
日常生活で夫婦だからこそ起こる様々な葛藤。些細なことであったとしても気になりますよね。相手の行動を直してほしいと感じる場面は多々あるのではないでしょうか。
でもアドラー心理学で子育てや対人関係法を学ばれた方は、不適切に注目しない、って考えてしまうので言葉に出すのをためらったりしてしまいます。
そんな時に私が使うフレーズについて今回はお伝えしていきますね。
我が家では主人と約束すると、スポーンとすっぽかされることがあります。
例えばこんな感じです。仙台へ行く日に
「何時に帰ってくるの?」
「~時の電車ですよ。」
「そう、それなら俺迎えに行く。」
と約束したにもかかわらず・・・来ない・・んです。
ある日美容院へ出かけました。「終わったら迎えに行ってあげるよ。電話して。」と主人が言います。
って言ってくれたけど、かけても・・・出ないんです。
どうしようかなと思いましたけど、とりあえず電車の時は自宅へ電話を入れたら慌てて来ました。
どうしたの?と聞きましたら「寝てた。」と。
「え~、自分から約束したのに?」と言いましたら
「眠かったんだから仕方がないだろう?」と言います。
美容院の時は「う~ん、電話は出ない可能性が高い」と思っていたのであらかじめ時間を決めておきました。そのうえで電話をしたので、出てくれなくても何とかなりました。
「電話くれっていうから電話したのに?」
「携帯持つの忘れたんだから仕方がないだろう。」と言いました。
さて、自分から言っておいてそれはないよなあ、と感じるのは私だけではないと思います。めったにないことであればそういうこともあるよね、で済ませられますが最近続いていたので、直してほしいなと思いました。
自分から言い出したことなので守ってもらいたい、ですよね。
それでこんな風に言いました。
「あのね、寝てたんだから仕方がない、携帯電話持つのを忘れたんだから仕方がない、ってあなたは思っていると思うけど、それをやり続けると私と仲良しでいられるの?って私は思うの。逆をされたらあなたはその人と仲良しでいたいと思う?」
そうしましたら、やっと考えてくれました。
そしてそれ以来気を付けてくれるようにはなりましたし、すっぽかしはほとんどなくなりました。
これは夫婦間で「仲良くする」とあらかじめ決めているから言えることでもあります。
「仲良くする」というゴールがあるので、その行動が仲良くするのに役に立つのか立たないのかを考えてもらうことができます。
以前あることがきっかけで「わたしはあなたと仲良く暮らしたいと思っているけど、あなたがその行動をやめないと仲良くできないし争ってばかりいることになる。あなたはどちらを選びますか?」と聞いたのです。
彼は仲良くしたいからその行動をやめると言いました。この時に「仲良くする」というゴールが双方の意志として確認でき、ゴールが決まったのです。
アドラー心理学は「どうしたら人は争わないで仲良く暮らせるか」がテーマの集積です。子育てにしろ、対人関係にしろです。
夫婦であっても親子であっても、「仲良くしよう」と双方で合意ができていればこのフレーズは使うことが可能になります。
自分がまず「仲良くする」と決めること。そしてそれを相手に伝えて相手の合意を得ることが最初にするべきことです。
それが出来ればこのフレーズは使ってもOKだと思います。どうぞご活用くださいね。
子育て・人間関係のお悩み相談は相談会・サポート会をご利用くださいね。
2022・9・3 「赤ちゃんの夜泣きがひどくてヘロヘロ」 寝不足で心が折れそうなママへ夜泣きの捉え方と対処法

赤ちゃんだってグループに
適応する力を持っている
夜泣きがひどくて抱っこしないと寝てくれない赤ちゃん
「もうヘロヘロ。どうしたら寝てくれるのかわかんない。とりあえず抱っこして毎晩毎晩揺らしてる。」
昼に寝てくれればその時に一緒に寝て何とかしのいでる。そんな生活を送っておられませんか?
「この生活がいつまで続くんだろう。自分の体がもたないんじゃないか。」という不安でいっぱいになっていませんか?
はじめての赤ちゃん、生むときの苦しさを乗り越えて、手に抱いたときのうれしくてうれしくて、と感じたあの日が遠く感じていますよね。
人によっては「おなかの中にいてくれた時の方が楽だった。」という方もおられます。
言ってもわからない、言葉が話せない、赤ちゃんとどう向き合っていけばいいのか。悩みながらヘロヘロの頭で考えることもできずどうすることもできず、思わず涙がこぼれる。
そんなあなたへ、アドラー心理学の子育てでは「赤ちゃんの夜泣き」をどうとらえるのかについて書いていきますね。
この世に生まれ出たときから赤ちゃんはもう自分が所属する家族に適応しようとしてます。どうしたら自分の要求が通るのか、親の愛を得られるのか試していると、アドラー心理学ではそう考えます。
あなたの発する言葉をちゃんと聞いています。理解はできませんしすぐ忘れますが、聞いています。赤ちゃんにとって親の存在はなくてはならないものです。親がいないと生きていけません。
そして言葉が話せませんから意志を「泣くこと」で伝えています。夜泣きも意思伝達の方法です。泣いてみて親がどう反応するかを学習しています。
「赤ちゃんが泣き止まないと抱っこする。」と赤ちゃんは「泣くことで自分の欲求を通そうとしている」と考えてください。
赤ちゃんには赤ちゃんの授乳などのサイクルがあるのですから、そのサイクルに赤ちゃんを合わせて生活するように心がけましょう。
いつも赤ちゃんの泣くのに合わせていると、このサイクルが崩れます。ママが辛くなります。泣けばなんとかしなければと考えて、その結果が抱っこするー夜泣きが続くということになってしまっています。
決まった授乳の時間以外で泣いたとしても、それに応えていると、のべつ幕なしに泣き続けるという事態が起きてしまいます。
赤ちゃんに合わせるのではありません。決まった生活サイクルに赤ちゃんを合わせるようにしてあげるのです。
夜中に泣いても構わないでおける環境であれば構わないでおくこと。もしもアパートやマンションなどで近隣に迷惑がかかる可能性があるのでしたら、下記の本がお勧めです。
家族は赤ちゃんが所属する初めてのグループです。グループにはグループのルールがあり、それに合わせないと一緒にいるメンバーが困るのだということを、学んでもらいましょう。
2022・8・22
兄弟げんかにうんざり。ママのイライラを増幅させる兄弟げんかのからくりと対処法

兄弟げんかには理由があり
対処法がある
夏休みでコロナのこともあり、お子さんがずっと家にいて、兄弟、姉妹で朝から兄弟げんかばかり。
「もうっ、また喧嘩してるの?!いい加減にしてよ。うるさいったらありゃしない。」
「やめなさい!やめなさいったら!!」
言っても全く聞き入れず「え?そんなつまらないことで?」と感じるような些細なことですぐ喧嘩になる兄弟。
いったいどうして?と困っておられませんか?
夫婦喧嘩同様に兄弟げんかは犬も食わないと、放っておくわけにもいかず、どうしたら仲良くしてもらえるのかと悩んでいるご家庭も多いのではないでしょうか?
ご相談を受けると「目的はなんでしょうね?」とお聞きすることが多いかなと思います。
目的?メリット、得られること、喧嘩で得られること、得たいことってなんでしょう?
相手に勝つこと、自分が相手より上に立つこと。
さらに踏み込んで考えると、相手に勝つこと、自分が相手より上に立つことで得られること、得たいことはなんでしょう?
「親の注目、親の愛」ですよ、とお答えします。
「どう、僕のほうが強いんだ。わかった?ママ。強い僕ってえらいでしょ?だから僕の方を見てね。弟より僕の方を愛してね。」です。
ところが親は、そんなことはわかりませんから、何とかしようとして注目を与えてしまいます。注目を与えると、叱られたにしろ子どもは得たいことを得られますから、喧嘩は続くのです。
また、やってしまいがちなこととして、喧嘩を収めるつもりで説教をすること。これも注目を得られることになるので、喧嘩をしないことにはつながりません。
さらに、子どもの言い分を聞いて「今回はあなたが悪いから、あなたがまず謝りなさい。」と言ってしまう。これをしてしまうと「悪」とされたほうの子どもは「自分は00より愛されていない。」と感じてしまいます。親の愛を奪還するために余計喧嘩がひどくなります。
喧嘩が常態化すると、大きくなっても争い続けるようになります。争いたがる大人になってしまうのです。上に立つため、勝つために他者と争う人になるのは、本人は優越感を得ながらもとても生き難いと感じ続けることになると思います。
喧嘩が多いお子さんたちに対する方法として「はじめてのお使い」と同様の機会を持たせてあげることが一つあります。ひとつの船に乗せて漕ぎ出させるのです。方法は何でも構いません。
「今年の夏はおじいちゃんのところへ二人だけで行ってみるかい?」
「今日はママはパパとデートだから二人でお留守番お願いできる?」
兄弟だけで何かに取り組ませたり、兄弟だけで出かける機会を作るなどです。親がいなければ兄弟で協力してやるしかない環境を持たせる。
それと今お子さんが小さい方には、下の子が生まれたら上の子にできることをお手伝いしてもらう。そうすると、下のお子さんを家族として慈しむお子さんになっていく可能性が高いと思います。
お母さんが生まれたお子さんにかかりきりになると、上の子は嫉妬を感じます。そしてなんとしても親の愛を取り戻そうとします。そうなると下の子は母親を奪った憎いやつになってしまいます。
喧嘩の火種はすでにこの時から植え付けられてしまうので、回避できるならした方がいいと思います。
いざ喧嘩が始まった・・・時には、兄弟を引き離しましょう。「離れましょうね。仲良くできるならまた一緒にいればいいんだから。」
そのように親が冷静に対応し続けることです。
ご参考になれば幸いです。
こういった子育てに関する日常の困りごとは、相談会で受けております。ご案内はこちらからどうぞ
2022・8・20
「嫁と姑の付き合い方」関係性を良くする伝え方

言いたいことを我慢していると
積もり積もって険悪な仲に
嫁と姑の問題でストレスを感じている方も多く、どのように付き合っていけばいいのか?旦那さんの手前きつくは言えないし、でも嫌なことは伝えたいけど関係性を悪くしてしまうことは避けたい。
「何ていえばいいのか。。」言いたいことがあるのにうまく言葉が出てこない、そんな場面が結構あるのではないでしょうか。
先日ご近所の奥さんからこんな話をお聞きしました。
子育てをしながらお仕事をされているお嫁さんが大変だろからと隣に住む息子さん夫婦のお宅へ時々お夕飯のおかずをもっていっていたところ、息子さんから「自分の家の献立の都合もあるんだから持ってこなくていい。」と言われたんだそうな。
「頭に来たけど、言ってもしょうがないと思って、あ。そうってだけ言って、もうもっていかないことにしたんだ。」とそうおっしゃいます。
そしてこう続きます。「なんで嫁さんが自分で言って来ないの?自分が孫を預かってほしい時には、いつも都合を押し付けてくるのに、ほんとに自分勝手なんだよね。」
最後に「まあ、いいんだけどね。」と言ったその方のお顔がとても寂しそうに見えました。
彼女の気持ちも、お嫁さんの気持ちも私にはよくわかります。
彼女はきっと悲しかったんだとそう思います。良かれと思ってお嫁さんの役に立ちたくてしていたのを「余計なこと」だと言われてとても悲しかったんだと思います。そしてそれをお嫁さんから直接ではなく息子さんを介して言われた。拒否されたように感じたんだろうと思います。
お嫁さんの気持ちもわかります。献立の都合もあるのにしょっちゅう息子の家だからと言っておかずを持ってくる姑。放っておいてくれればいいのに、頼んでないのにと感じるのではないでしょうか。
だけれども自分が言うと角が立つ。直接対して言う勇気がない、なんていえばいいのか言いにくい、などの理由でご主人に言ってもらうという選択をしたんでしょう。
アドラー心理学で考えると、このケースは本来は姑さんとお嫁さんの二者間の問題です。ですから二者間で片づけるのがベターです。
二者間の問題に息子さんが首を突っ込んだからお姑さんが嫌な気持ちになったのです。
(こういうパターンは結構あるので後日またメルマガで取り上げたいと思っています。)
両者に共通するのは「どう伝えたらいいのかわからない」という伝え方の問題があるのです。
アドラー心理学で考えると、課題分けに反しているということと主張的でないという二つの問題が浮かび上がってきます。
さて今回はこれをアサーティブ「相手も自分もOk」の伝え方で伝えるとどうなるかを書いてみますね。
基本は「起こった出来事」プラス「感情」プラス「提案」という公式に当てはめます。
お姑さん側から見ると「起こった出来事」は、おかずを持って行ったことについてお嫁さんではなくて息子さんが「いらない」と伝えてきたことです。
「感情」は「悲しみ」「怒り」です。怒りは悲しみが形を変えたものですから、もともとの感情は「悲しみ」になります。
「提案」は、お嫁さんから直接伝えてほしかったということです。
公式に当てはめて文章を組み立てると次のようになります。
彼女の場合には
「おかずをもっていっていたことが余計なことだったと息子から知らせてもらいましたが、あなた(お嫁さん)の口から直接言ってもらえなかったのは悲しかったです。今度からは直接言ってもらった方がわたしは嬉しいです。」
お嫁さんの場合には
「起こった出来事」は「おかずを姑が持ってくる」で、「感情」は「余計なことをして」という「いらだち」、提案は「やらなくていいです。」ということです。
「いつもおかずを届けていただいてありがとうございます。でもうちも献立を考えてあるのでもってきていただいたものを食べられないことも結構あって困るんです。ですからお義母さんのせっかくの好意が無駄になるので控えていただけると助かります。」
いかかでしょうか?双方が主張的であればいいのですが、どちらも非主張的だと双方が嫌な気持ちのままお互いの気持ちがわからないままなんとなく距離を感じてしまうのです。
どちらかが主張的であれば、そして「自分も相手もOK」の伝え方を知っていれば、わだかまりを残すことなく別の方向へ事態は変わっていきます。
アドラー心理学の子育て法にしても対人関係法にしても「話してみる」というスタンスが基本です。
お互いにどう思っているのかがわからないでもやもやしたままいるよりも、勇気をもって伝える、ということができるようになれば関係性は必ず変わっていきます。
上記の公式は自分で当てはめて使ってみて練習してみるとできるようになりますので、どうぞご活用いただければ幸いです。
こういう練習や悩みのご相談も相談会、サポート会で承っております。ご案内は下記をご覧くださいね。
2022・8・19
「どうせ僕なんか・・」自分には能力があると感じてもらえるにはトライと検証の繰り返し

あなたには能力があるんだと
思ってもらえるように
前回の記事で「したくなくてもしなければならないことをする勇気」を持ってもらうことが大事なことだと書きました。
そのためには「自分には能力があると感じてもらうことが必要である。」ということも書きました。
たとえば皆さんがお仕事をされていてこんな場面を思い浮かべてみてください。
自分がとっくにわかっていてこれからやろうとしていたことについて、上司がわざわざ口を出してきたとしましょう。
「そんなこととっくにわかってるのにわざわざ言う?」と思うようなことです。
そうすると「わざわざ言われなくてもわかってますよ。何も言わなくても。全然信頼されてないんだな。何年この仕事してると思ってんのかな。」
そういう気持ちになってがっかりすることでしょう。時には腹が立つかもしれません。
「信頼して任せてもらえていない」「自分の能力を信じてもらえていない」ことが勇気をくじかれた結果になっています。
口を出すことが勇気くじきにつながっています。
これと同様なことがお子さんに対しても起きています。
お子さんは日々私たち大人が想像できないほどの速さで変化をし続けています。
ところが私たちはそのことを考慮せずにいままでと同じように「まだできない」ことを前提に口を出してしまいがちです。
「終わったの?」「できた?」「やった?」などですね。
言う方は全く悪気がありません。今までそうしてきたからという習慣的に口に出しているか、自分が確認して安心を得ているだけです。
ところが言われたほうは「自分はできるんだと信頼されていない」と感じてしまうのです。
ですから口を出す際にいったん考えて見ることが必要です。
「この言葉を今この子にかけたたとしたら、この子は自分には能力があると感じてくれるだろうか?」と。
もしくは「どういう言葉をかけたらこの子は自分に能力があると感じることができるのだろうか?」とですね。
自信を失ったお子さんにこそこういう慎重な言葉かけが必要だと思います。
同じ言葉が万人に通用するわけではありません。私たちが一人一人違うようにお子さんも一人一人違うのです。
ですからトライと検証の繰り返ししかないと言えると思います。
アドラーの子育てや対人関係法というのはゴールが明確です。
「精神的及び社会的自立」ですが、そのために必要な感覚が「自分には能力があると感じていること」「他者は友であり仲間であると思えていること」の二つです。
この二つが持てていると勇気を失うことはありませんし、精神的・社会的自立へ向かうことができると考えます。
ゴールが明確であるからこそ「トライと検証」が成り立つのです。ゴールに照らし合わせて「役に立つのか立たないのか」を見ていくことができます。
慣れるまでに少し時間がかかるかもしれませんが、慣れてしまえば自然にできるようになっていきます。
その間、うまく行かない時には仲間が支えてくれますし自分が支えになることもできます。
いずれにしても一朝一夕にできることではないので、地道なトライと検証をしていくことが大事です。アドラー東北のサポート会や相談会をどうぞご利用ください。
相談会のご案内は下記です。サポート会では初めてご相談の方でも参加OKにしました。
グループでのご相談になりますが、その方がいいという方はご利用くださいね。
2022・8・16
「だから言ったのに、言われたとおりにやらないから」 夏休みの宿題をめぐる親子の攻防に終止符を打つ
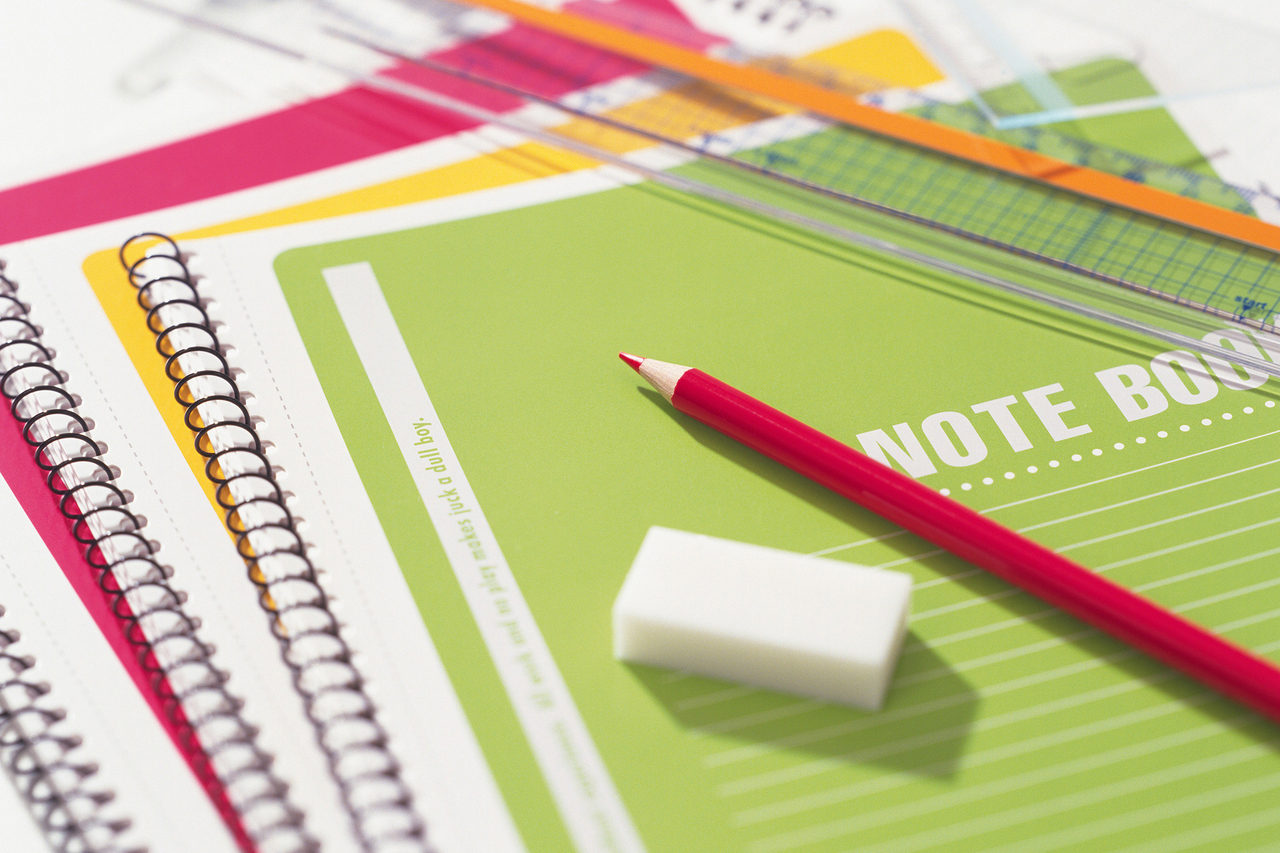
夏休みも子どもはたくさんやることがあるけれど、自発的に取り組む子になってほしい。
東北地方の夏休みはあと一週間程度で終わりになります。この時期ご家庭でママとお子さんとの夏休みの宿題をめぐってこんなやり取りが繰り広げられているかもしれません。
「もう!全然やってないじゃないの?!だから毎日ちゃんとやっておきなさいって言ったでしょ?いう通りにしないから、どうするの?こんなにためちゃって!」
「だって・・・いろいろあったんだもん。。」
「だって・・じゃありません!!こんなにためこんで間に合わないじゃないの?」
ひとしきり怒ったあとでしょんぼりしている子どもを前に気を取り直して「ほらっつ!ママも手伝うから一緒にやりましょ。」
どうして毎回毎回同じことになるのかしら?少しは自分からやる気を出してほしいんだけど、さっぱりだわね。
もしもあなたが毎年同じ光景が繰り広げられていて、そしてこの繰り返しを来年はしたくないと思っておられるなら「子どもが自発的に物事を取り組む」関わり方に変えていくことをお勧めします。
お子さんは普段はどうでしょう?普段から物事を自発的に取り組んでいますか?どちらかというと好きなことは言われなくてもやるけれども、こと勉強に関してはあなたに言われてから取り組むという姿勢が多いのではないでしょうか。
そうでないなら、夏休みの宿題も普段と同様に自発的に取り組むとは思えません。お子さんはいつも通りであり、夏休みだからと言って自発的になるわけではありませんので、あなたもいつも通りの結果を受け取ったということになります。
お子さんが自発的にしたくないことに取り組むというのは、まず「勇気」と「内側からのやる気」が必要です。
この場合の「勇気」とは「したくなくてもしなければならないことに取り組む勇気」です。そして「内側からのやる気」は「自分にはしなければならないことに取り組む能力がある」と自分を信じていてこそやる気が持てるのです。
アドラー子育ての「勇気づけ」とはそういう勇気をお子さんに与え、自分と自分の能力をはぐくむ子育て法です。
「ママ、今年は夏休みの宿題ちゃんと自分でやったよ。見て!」そんなお子さんの声を聞いてみたいと思いませんか?
親が手を出し口を出さなくても自発的に自分のことに自分で取り組む子供を育てる方法がアドラー子育てといえると思います。
親が関わり方を変えれば子どもも変わるのです。
親子関係のお悩みについてはメルマガ登録をお勧めします。ご登録は下記からどうぞ
2022・8・15
「子どもはなぜバレバレの嘘をつくのか」 平気でバレる嘘をつく子どもをどう捉える?対処する?

すぐにバレるのに
なぜうそをつくの?
「宿題終わった?」
「うん、終わったよ。」
言われて見て見たらやってない。
「せっかく夏休みで時間があるんだから自分の部屋片づけて掃除しなさいよ。」
「は~い。」
「片づけてお掃除した?」
「うん、したよ。」
行ってみて見たら物をわきへ寄せただけ。
むかあ~~~っつ、としますよね。
そして思わず
「なんで嘘つくの?!なんでそんなバレバレの嘘つくかな?!嘘つくのはいけないことでしょ!わかんないのかな、それぐらいのこと?!」って言っておられるのではないでしょうか。
「平気で嘘つくなんて信じられない。どうして平気でそういうことができるの?」怒り心頭よくわかります。腹が立って仕方がないことでしょう。
どうしてこういうことが起きるのか、なぜ子どもはすぐばれてしまうような噓をつくんでしょうか。
さて、それでは子どもが嘘をつかないで本当のことを言ったとしましょう。
「宿題した?」
「まだしてない。」
「え?なんでしてないの?」
「片づけて掃除した?」
「まだしてない。」
「え?時間あるんだからしろって言ったでしょ。なんでしてないの?」
嘘をついてもつかなくても子どもには「叱られる」という事態しか待っていないということがお判りになると思います。
どっちにしろ叱られるのだから一時的にでもそれを避けたいと思って「嘘をつく」という方法を使ってしまっているのです。
いけないことは叱らなければわからない、親として当然の考えだと思います。
でも「叱る」という方法だと、叱られるのは誰でも嫌ですから「回避」へ向かいがちになってしまうのです。
「叱られることを回避する」という目的達成のために「嘘をつく」という手段・方法を使っているということになります。
「嘘をつく」ことをなんとかやめさせようとするよりも、普段の「不適切な子どもの行動に叱るという対応をする」ところを変えないと、この方法を使うことを子どもはやめないと思います。
それではアドラーの子育て対応だとどうなるでしょう。
「宿題した?」
「したよ。」
「そう、あなたならきっとやると思っていたわ。」
「・・・・」
「片づけて掃除した?」
「したよ。」
「そう、きれいになって気持ちよくなったでしょう?」
「うん・・・・・もごもご」
自分を信じて疑わない親に対して嘘をついてしまった自分に「なんとも居心地の悪い気持ち」を子どもは持つと思います。
「親は信じてくれているのに・・自分は・・。」と感じると思います。
子どもには適切な行動をする能力がすでに備わっていますから、それを使ってくれるようになるかもしれません。
少なくても「嘘をつく」ことはなくなっていくと思います。
課題分けまで理解されている方ですと、「宿題した?」とか「片づけた?」と言ったような子どもの課題そのものに言及することもなくなっていきます。
叱るという親も嫌な気持ちになる方法を使わずとも、子どもさんが自ら「お母さん、今日ぼくちゃんと宿題やったよ。見て!」「今日ね自分の部屋をきれいにしたんだ、見てみる?」
そういう言葉をお子さんから聞きたいと思いませんか。
すごいね~、やったね!ってグータッチできる親子関係。アドラー子育てってそういう方法なのです。
自分から進んですべきことをする子ども。そういうお子さんに育つ方法です。
アドラー子育てを学ぶならまずは「アドラーコンパクト」からがお勧めです。お問い合わせは下記からどうぞ。
2022・8・12
「お盆なんか来なきゃいいのに・・」旦那の実家に帰省するのが憂鬱なママへ疲れずに過ごせる方法

お盆の憂鬱
あ~、もうお盆だ。。毎年旦那の実家に帰省することになってるけど、疲れが倍増するから嫌だな~って感じてしまう自分。
旦那の家族を大事にしようって思えないわたしって駄目な嫁かもしれない。
だって行けばさ、うちにいるように自分のペースで食事の支度とかできないし、舅や姑、親戚の叔父さん叔母さんたちに気を遣って話さなきゃならないし、嫁だから率先して台所に立ったり家のことやらなきゃいけないし。
お盆の時しか会わない人たちばっかりだからどういう人たちかよくわかんないし、どういう言葉をかけたらいいのか、話をしたらいいのかもわからん。。
気を悪くされたらどうしよう、とか気の利かない嫁だと思われたらどうしようとか、そんなことばかり考えちゃうし、いつも以上に張り切ってお料理つくったり気の利く嫁を演じるから帰るころにはヘロヘロになっちゃう。
考えちゃうとほんと行くの嫌になっちゃうな。お盆なんか来なきゃいいのに。。
お盆の時期になるとこういう気持ちになっておられませんか?
まじめで誠実であろうとし、きちんとした方に多い様に感じています。また先へ先へ見通しを立てて動く傾向のある方にも多い状態ですね。
私もお盆の帰省の時期は本当に憂鬱でした。「あれこれ考えすぎていたんだな。」と今はわかりますが、その時は「どうしたら行かないで済むだろう」なんて考えていたものです。
こういうご主人のご実家への帰省の際のネガティブな気持ちをどう自分の中で整理しておさめたらいいのでしょう。今日はいくつかご提案を書いて行きますね。
<お盆の帰省が憂鬱なママに、旦那の実家に滞在しても疲れずに過ごせる三つの方法>
まず一つ目です。
最初に申し上げておきたいのはあくまでご主人のご実家の主は舅と姑さんですよということです。ですからあなたが中心になって先頭を切って頑張る必要はもともとないのです。
あなたはお手伝い程度の感覚でいいのです。必要な時にお願いされたらお手伝いする、という感覚の方が疲れないと思います。
こういうスタンスでいると気持ちがだいぶ楽ではないでしょうか。
「今まで全部自分がやってました。姑も期待するみたいだし。」という方には「お義母さんのお料理を習いたいから教えてもらえますか?」と申し上げてお料理を見せてもらいましょう。そうして主を姑に預けるのです。
または「お義母さんと一緒に料理したいです。」と伝えてみてください。
姑もたぶん悪い気分はしないはずです。嫁が教えて欲しいって言ってくれた、料理を一緒に作りたいって言ってくれた。
腕の見せ所と感じるのではないでしょうか。お姑さんに花を持たせてあげましょう。
二つ目は無理に話をしなくていいということです。
聞かれたときには返事をすればいいので、無理に自分から話さなくていいのです。お相手の話を「うんうん」と聞くだけで相手は十分満足しています。
場を盛り上げなきゃ、話をしなきゃと思わなくていいんです。
日本人の傾向として相手との会話で「間」が空くことを嫌がります。気まずいと感じて取り繕うから疲れるのです。
間が空いてもいいんです。相手はあなたが思うほど気まずく感じていません。
ですので聞き役になればいいやとそういうスタンスでご実家に滞在中あなたがおられることも一つの方法としてはありだと思います。
三つ目は家族だけで近場の観光地や買い物などに出かけること。
ずっと家の中にいると気持ちが煮詰まってきますしイライラしてしまうこともあるでしょう。それはご自宅にいても同じだと思います。
ご主人にお願いして帰省の機会に近場の観光地巡りなどを予定に組み込んでしまうのもお勧めです。
何ならお子さんたちをお舅さんとお姑さんに預けて、「たまには夫婦で。」もありではないでしょうか。
「孫たち、おじいちゃんとおばあちゃんが好きなのでお任せしていいですか?」と言ってもいいですし、ご主人様に活躍していただいて「お願いしてもらう」もいいでしょう。
憂鬱だと感じていたお盆の帰省もちょっとした工夫で精神的な負担も減りますし、観光で楽しめてしまう、どうせ行かなきゃならないなら楽しみを見つけて乗り切ってしまいましょう。今年のお盆の帰省があなたにとって今までとは違う帰省になりますように。
アドラー東北ではこういう日常のお役に立つ情報をメルマガで配信しております。ご購読のお申込みはこちらからどうぞ
2022・8・10
「ちゃんとしなさい!!」 夏休みにママが発するお子さんへの連発定番フレーズ卒業法

連発フレーズそろそろ卒業しましょう
夏休みに入って宿題やら生活習慣についてお子さんへ「ちゃんとやりなさい。」の声掛けが多くなってきているのではないでしょうか?
さて今日はそんなあなたへ一つの提案をしておきたいと思います。
「夏休みの最後になってから慌ててやる羽目になるんだから今のうちにちゃんと宿題やりなさいよ。」
「外で遊んで帰ってきたらちゃんと足を拭いてから家の中に入って。汚いでしょ。」
「夏休みだからってダラダラいつまでも寝てないでちゃんと朝起きなさい。」
などなど「ちゃんと~しなさい。」フレーズを連発しておられませんか?
これは親心です。気になりますよね。朝から晩まで家にいてずっと目に入ってくるのですから、あれもこれもちゃんとさせなきゃと思ってしまうのは当然だと思います。
「ちゃんとした子になって欲しい」「きちんとした子になって欲しい」からこういう言葉が出てくるんですよね。
それで結果はどうかというと、さっぱりやらないんですから、声をからして言葉をかけたのはいったい何だったのか、がっかりして、悲しくて、言うことを聞いてくれない子どもをちょっぴり憎らしく感じたりしているのではないでしょうか。
そして最後には「いい加減にしなさい~~~~!!」と大爆発してしまったりするんですよね。
ではここで少々冷静に考えてみてください。
「ちゃんと~して。」と言い続けて、あなたはどんな結果を受け取っていますか?あなたの望む結果を受け取っていますか?
望む結果を受け取っているならまだいいのですが、そうではない場合は、言い続けるという行動は効果がないということになります。
「でも言わないとますますやらないのでは?」とお感じになられた方もいらっしゃるかなと思いますが、今日のご提案は「試しに別の方法・逆をやってみませんか?」というご提案です。
アドラー心理学の子育て法だとどういう対応になるかなということについてちょっと書いておきますね。
いつものように外で遊んで帰って来た子どもが足が汚いまま家の中に入ってきた。
いつもなら「足をちゃんと拭きなさい」というママが何も言わない。
「あれ?変だぞ。」と子どもは思います。
拭かなくていいなら楽だと感じてそのままにするかもしれませんし、変だと思ってきいてくるかもしれません。反応はお子さんによるでしょう。
拭かなくていいやと感じて家の中を汚い足で歩き回ったとしたら、床が汚れますので
「〇君、床の汚れを拭いてくれるかな。」と声をかけてみましょう。
「今日はママ何も言わないね。」と言われたら「そう?だってあなたは自分でできる子だから、言わなくても大丈夫だと思って。」と答えてみてください。
子どもはきっとどちらにしろ何かを感じて学ぶはずです。
前者の場合には足を拭かないで家に上がったことの結末を引き受けてもらいます。
後者の場合には勇気づけのチャンスです。
「朝ご飯は7時にしたいんだけど」とあらかじめ提案しておく。
家族で同意が得られたら、そのうえで「起こさない」
起きてこなければ朝ご飯は食べられない。結末を引き受けてもらう。
「ご飯は?」「残念だけど7時に終わりましたよ。」
「押してもダメなら引いてみる」今までの対応がうまくいかないのであれば工夫して変えていきましょう。きっと何か変化が起きると思います。
親子が喧嘩にならずに協力していく方法です。そして親の子どもを思う気持ちが伝わる方法でもあります。
こういうご相談は、相談会で受けています。またマンツーマンのアドラーコンパクトでしたらあなた自身の悩みに添ってアドラー子育てが学べます。上記のケースが当てはまらない場合にもあなたの状況に沿った対応をご提案できます。
ご活用いただければ嬉しいです。言い方ひとつ、対応の仕方ひとつでお子さんとの関係もガラッと変わっていきます。
大人同士の対応にもぜひご活用くださいね。
今までの方法をとるのか別の方法をとるのか、いずれにしてもご自分で選んだ結果が現実であることには変わりがありません。
幸せへ向かう選択をしたいものです。
2022・8・9
「親を嫌いになれない苦しさから解放されるために必要な考え方」

自分の親との関係に悩み続ける人は多い
アドラー東北がご相談にのっている身近な人間関係の悩みの中には当然自分の親との関係も含まれます。
毒親なのに嫌いになれないです。
たくさん嫌なことを言われて傷ついてきましたが、なぜか親を拒否できません。
子どもを嫌いな親がいるはずがないといろいろな場所で言われているし、実際に私を大事に思っていると言ってくれることがあります。
なので親が嫌いと思ってはいけない。
私の感情がおかしい。
私が間違っているのかなととても苦しいです。
と涙ながらにお話しくださることがあるのですが、多くの方は最初から「親の問題で悩んでいます。」「親が嫌いなんです。」と正直におっしゃる方は少ないのです。なぜなんでしょう。
それは日本には「親を大切に」とか「親への反感などもってのほか」「親孝行すべし」という親を悪く言ってはならないという暗黙のルールが根強く残っているからです。
経験上親について批判的なことを話しても「理解してもらえなかった」、それどころか「親を悪く言うなんて。」と嫌な顔をされたり説教されたり非難されたりしてきているので、うちへ来て話すときもこわごわです。
最近でこそ「毒親」という言葉が出てきて、そういう親子関係があるんだということについて知られるようになりましたが、それでもまだまだタブーだと感じることは多いです。
<親を嫌いになれない受講生の話>
最初お子さんのこれからについて不安で、というオンラインでのご相談でいらした方が、途中からご自身の親との話に変わっていって、親に対する批判がとまらなくなったことがありました。
そうなったきっかけは、私がその方のお話を聴いていて「どうもあまりお子さんの問題で悩んでいる風ではない。何か他に問題があるのではないか?」と感じ、お子さん以外のご家族のことを何気にお聞きしたら出てきたというケースでした。
「親と決別したんです。だって毎日喧嘩しなきゃならなかったから。だからきっぱりと縁を切ることにしました。」
「決別するって大変なことですよね。よくご自分の親との決別を決められましたね。大変な勇気でしたね。」と申しましたらその方は涙が止まらなくなってしまいました。
「親が一人になったので子どもとして世話をした方がいいのかなと思ったのですけど、会うとわたしのことや子どものことをあれこれ口出しして指示して、自分の思い通りにならないと気が済まない人なんです。だから会えば言い争いをしていました。こういう争ってばかりの生活は自分や子どものためにならないと思って決別することにしたんです。」
それでも「でも、でも・・・私は親を嫌いになり切れないんです。」と自分の中の揺れ動く思いを抱えておられるようでした。
このように親との関係で苦しい思いをしているのに「わたしは親が嫌いです。」と言ってしまえない、言うことを阻む頑なな何かが私たちの心の底にはあると感じます。
またある受講生はやはり同居していた親からの自立を考えていると言います。
離婚して子どもを連れて実家へ戻ったはいいが、子どもの潔癖症や登校渋りといった問題が起こって、私のところへ来た方です。
アドラー心理学の子育てを学ぶうちに、子どもの問題は解消していく半面自分と親との関係について様々な葛藤が生まれたと言います。
「それでどうするつもり?」とお聞きしましたら、「別に住むところを探して子どもと2人で住もうかと思っています。」とおっしゃっておられました。
「せっかくアドラーの育児を学んで子どもとの関係が良くなったのに、親とは相容れないことばかりで、それならいっそ距離をちゃんととった方がいいかなとそう思いました。」
「やっぱり喧嘩になるの?」
「アドラーのおかげでさすがに自分の方から喧嘩になるようなことは言わなくなりましたけど、言っても理解してもらえない煩悶は常にありますね。自分には何を言ってもいいってそう思っているんです。」
精神的に自立した凛とした女性の顔がそこにはありました。サポート会での出来事でしたが、皆が彼女を応援する言葉を投げかけました。
「親は変わりませんからね。」と最後に彼女はそう言って笑いました。
<親を嫌いになってもいい>
親のことでご相談にいらした方に必ず私が言うことがあります。
「親を嫌ってはならないということはないのですよ。親だからって嫌われるようなことを子どもにすれば嫌われるんです。それが道理です。だから無理に好きにならなくていいんです。嫌いなら嫌いでいいんですよ。」
そうすると皆さんホッとしたお顔をなさいます。初めて親のことを話して受け入れてもらえたと感じるようです。
それまで話しても理解してもらえたことがない。「もしかしたら自分が悪いのではないか。」「自分が間違っているのではないか」という恐れを常に抱いておられるのが親との関係に悩んでいる方の特徴です。
親だからと言って子どもに何をしても何を言ってもいい、そういう親子関係に苦しむ大人になった子どもがたくさんいらっしゃいます。
切っても切れない関係だからこそ苦しいのです。そういう方たちの安心して集える場を私はこれからも提供していきたいと思っています。
アドラー東北メルマガ登録はこちらからどうぞ
2022・8・8
「夏休みは子どもと毎日いるのが疲れちゃうママに知って欲しいイライラしない子どもとの接し方とは」
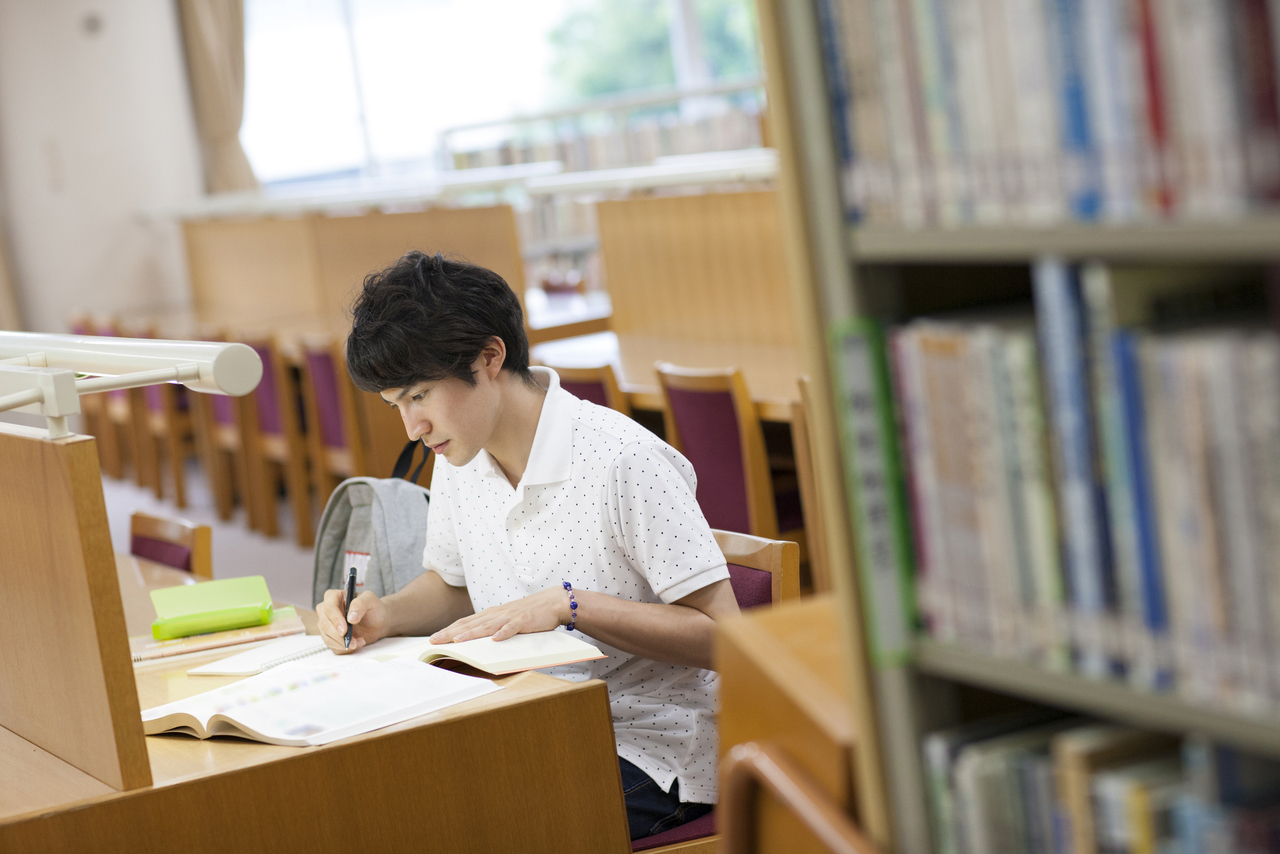
あなたの子どもを思っての行動が
実は関係悪化の原因に
夏休みはほんとうに疲れちゃう。
夏休みぐらい朝はゆっくりしたいのに、毎日子供たちが家にいるからお腹すいたーと朝ごはん。
終わったと思ったらすぐにお昼。
学校のプールや補修などの子どものスケジュールに振り回されて休み時間もありません。
知り合いに相談しても、好きな音楽を聴く、映画を観る、ドライブに行くなど自分が好きなことでの気分転換をやればいいよ、とか言われますが、そんな時間がないからイライラするんですけど?、と参考になりません。
「あなたたちは夏休みかもしれないけど私たちは年中無休だー!!」と叫びたくなるぐらい毎日イライラしっぱなしです。
というママからの話はよく聞きます。
今回はそんな夏休みのイライラを少しでも軽くする方法についてお伝えしていきます。
ベースはアドラーの子育て・対人関係法を基に、感情のコントロール、共同体感覚、子育ての目標、と言ったところを考慮するとこういう方法が考えられるということで書いています。
アドラー東北のHPに「発達段階と勇気づけ」というページがあります。生まれてからアドラー子育てで育児をすると5歳ですでに自分のことは自分でできる子どもになっていきます。
最後にリンクをはっておきますのでご参照くださいね。
ところがアドラーの子育てにいつ出会うかは人それぞれです。何か問題が起きてうちへ来られる方がほとんどですので、小学校高学年から高校生ぐらいまで、またお子さんがすでに成人になっておられるなど状況は様々です。
ですが、お子さんを見てイライラするのは皆さんに共通した悩みです。
ですのでケースに該当しなくてもイライラ解消法としてお読みいただければと思います。今回は三つほどあげておきます。
「イライラしない子どもとの接し方3つの解消法」
まず一つ目です。
イライラが続く、しょっちゅうイライラしてしまうのは、「イライラしちゃいけない」と思うからです。自分の感情に蓋をしたり見ないふりをしたりするからです。
イライラしていいんです。でもそれを感情に任せてお子さんにぶつけない。
イライラという感情に名前を付けて見ます。「イライラ君」「むかむか君」自分にフィットする名前を考えて見てください。
お子さんの行動を見てイライラが起きてきたら「あのね、今イライラ君が顔を出してるの。」とお子さんに言ってみてください。
隠さない、貯めないで自分の気持ちを小出しに伝えるのです。
「あのね、今ムカッとクンが出てきたの。」と伝えて見ましょう。
「どうしてイライラ君が出てきたの?ママ怒ってる?」
「怒ってないけどイライラしてるみたい。」
「どうして?」
「う~ん、イライラ君はねきっと片づけてほしいって思ってるからかもね。」
そんな風にお子さんに伝えて見ましょう。
片づけてくれるかどうかはわかりませんが、とりあえず自分の感情を素直に伝えたことでいくらか気持ちが落ち着くと思います。
二つ目は大いに愚痴をこぼすべしということです。
「疲れた」「もうやだ。」
一人で言ってもいいですが、できるなら同じ境遇のママと笑い話でもするようにお話して発散できればベターかなと思います。
「うちの子~でさ~。」
「あ~うちもそうだよ。」
「あ、やっぱり。一緒だね。」
可能ならご主人に受け止めてもらえれば一番いいかなとそう思います。ご夫婦の協力が問われるところです。
この時注意したいのは、解決しようとしないこと。
「いたわり、ねぎらい、思いやり」の言葉を奥様に伝えましょう。それだけで妻は頑張れるものです。「わかってもらえている」と感じるからです。
また紙に気持ちを書きなぐってくしゃくしゃポイもお勧めです。
三つめは、ご主人やご自分のご両親などのお力を借りたり、公共の場を利用して、一人時間を少しでも確保すること。
1時間でもいいので、一人でホッと息をつける時間を確保しましょう。
大きく深呼吸をして、伸びをして自分を労わりましょうね。
夜、子どもたちが寝てからこういう時間が持てるなら、その時間に自分のケアを兼ねていろいろ工夫してみて下さい。
何が何でも自分が一人でやらねば・・と思わないことです。肩の力を抜いて、お子さんにも気持ちを伝えながら協力できることは協力してもらうように習慣づける機会にもなるかもしれません。夏休みを活用するという発想の転換です。
「今ねちょっと疲れてるんだ。一人で静かにしてたいんだけどそうさせてくれる?」ぎりぎりまで我慢しないで、伝えて見ましょう。
頑張り屋のママにとって夏休みは大変な時期ではありますが、お子さんに普段できないチャレンジをしてもらえる時期でもあります。「この夏休みあなたは何かチャレンジしたいことある?」って聞いてみてもいいでしょう。
親子で生活プランを立てて見たり、工夫して楽しみをたくさん作ってみてくださいね。
子どもの発達段階と勇気づけのページはここをクリック
アドラー東北メールマガジンご購読のお申込みはこちらからどうぞ
2022・7・30
「子どものため・・って頑張ってきたのに、子どもがどんどん離れていく現実」を受け止められないママへ
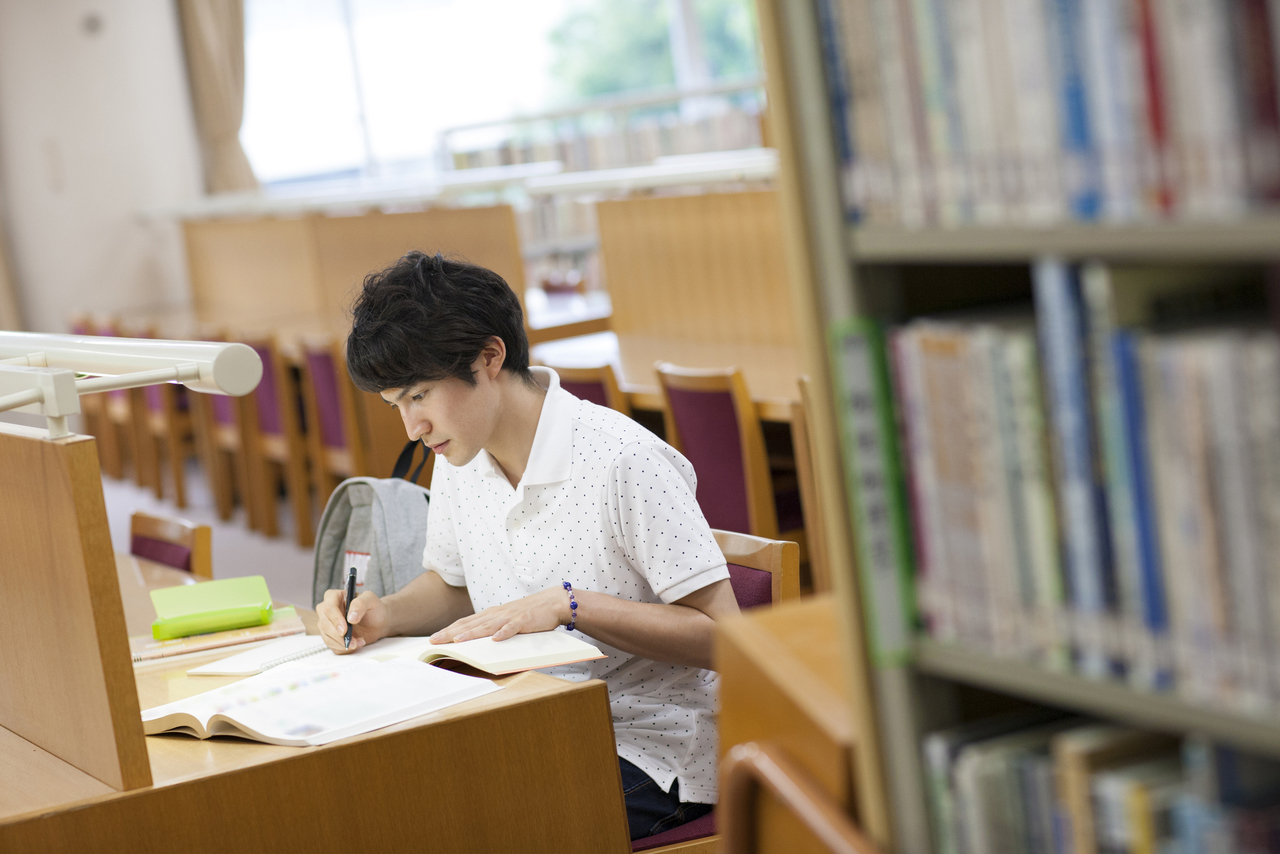
あなたの子どもを思っての行動が
実は関係悪化の原因に
自分が生み育ててきた子どもが愛しいのは誰でも同じこと。慈しみ大事に大事に育ててきた子どもとの関係がどういうわけかうまくいかなくなった。
寂しい、悲しい、辛い、こっちを以前のように向いてほしい。でも全く相手にしてくれなくなってしまった。
そういうご相談を受けることがあります。
「何とかしようとすればするほど子どもが離れていくんです。あんなにママ、ママって私にくっついて離れなかった子が。。あなたのためよって、私は毎日を過ごしてきたのに。」
「どんなお気持ちですか?」
「辛いです。以前のように息子と一緒に過ごす時間が欲しいです。寂しくてたまりません。」
「そうでしょうね。寂しいですよね。寂しさってどうしてそう感じると思いますか?」
「何でもしてあげてなんでも聞いてあげてなんでも一緒だったんですもの。」
「なるほど、それで寂しいんですね。もしかしてずっとそうしていたいと思っておられます?」
「あ、いえ、そんなことはないと思いますけど。」
「いつまでなら?」
「あ、そうか。。。永遠は無理なんですね。今までとずっと同じではいられないんですよね。」
「そう思いますか?ずっと同じではいられない?」
「ええ、だって息子だって自立していくんですもの。いずれ大人になって私から離れていくんですもの。」
「そうですよね。」
「じゃあ、それが始まったってことでしょうか?」
「そうかもしれません。そうだとするとどうされますか?」
「手が離れたら、自分はどうするか考えてませんでした。考える時なのかもしれません。今まで息子のことしか考えてこなかったので。」
「そうですか、考えて見られて何か見つけたら教えてくださいね。さて、それじゃどうしましょうか。今の息子さんとの関係ですけど。」
「なんか関わろうとすればするほど悪くなるんですけど。」
「関わるとあなたの望む結果が受け取れないとすると、どうしたらいいんでしょうね。」
「関わらないようにする?」
「そうするとどうなるでしょう?」
「わかりませんけど、できるかなあ。子どものためって暮らしてきたのに。。」
「でもそれをやり続けるとうまくいかないわけですよね。」
「そうなんです。やっぱり関りを減らしていくことがいいのかもしれない。」
「それじゃそうしてみますか?それで様子を見てみましょうか。」
「はい、できるかどうかわからないんですけどやってみたいと思います。」
お子さんのためと一生懸命やってきた方ほどこういう状態に陥りやすくなります。お子さんが自立を始めると自分の拠り所がなくなったと感じてしまい、元に戻そうとやっきとなってしまってかえってお子さんとの関係を悪化させてしまうのです。
お子さんが自立していくのですから、あなたも自分の人生をこれから生きるきっかけになさったらいいのでは?と私は思います。
子どものため、「あなたのためよ」と思って暮らしてきた人生を、あなた自身のための人生を歩みはじめるきっかけが「お子さんの自立」ではないでしょうか。そういう捉え方をすればあなたもお子さんもしあわせになるのではないかとそう感じています。
2022・7・26
「ちゃんとやってね!」の親心
手出し口出し逆効果

「ちゃんとして欲しい」
それでついつい言葉が出る
「ちゃんと片付けなさい」「ちゃんと時間を守りなさい」「ちゃんと勉強しなさい」「ちゃんと食べなさい」
一日に何度も「ちゃんと~しなさい。」そう言い続ける毎日。小さいうちは言うことを聞いていた子どもがだんだん全く言うことを聞かなくなり、反抗したり無視したりするようになってしまった。
そうなるとますます言ってしまう自分がいる。言いたくないのにどうしていうことを聞いてくれないの?
悲しくて、怒りがこみあげてきますよね。「あなたのためを思って」言っているのになんで私の気持ちがわからないの?わかってくれないの?と思われているのではないでしょうか。
それではここで以下の二つの質問について考えてみてください。
<あなたはお子さんにどうなってほしいのでしょう?>
「言わなくてもちゃんと自分でやる子になってほしい」のではないでしょうか。
<自分の行動の結末はあなたが望んでいることですか?>
「言い続ける」ことで「言わなくてもちゃんと自分でやる子になっている」という結果につながっているでしょうか?
結果はお分かりのように「言い続ける」という方法は効果がないということがわかるでしょう。
「言わないともっとやらなくなるのでは?」というご不安がおありになりましたら、こんな風に言葉をかけてみてください。
「あなたは自分でできる子だからママは言わなくてもいいわよね。」
そういわれた子どもは、自分で考えてやらざるを得なくなります。自分に自信がなければ助けを求めてくるかもしれません。
必要があれば手を貸すことも可能ですし、もうできると思えば「あなたは自分でできると思うの。」と助けがなくてもあなたにはできる力がありますよ、と声をかけてみてください。
言い続けることはあなたにとってもつらいことですので、効果がないのでしたらやめてしまうことです。
そして別の方法という選択肢を考えていきたいものですね。
2022・7・23
「夏休みなんかいらない!!」
初日からすでにくたくた・・先を考えるとうんざり

家に帰るの嫌だな・・
2022・7・16
「なんで反抗ばっかりするの?!」
ー反抗期だから仕方がないと思っていませんか?

反抗するには理由がある
2022・7・15
「誰かや何かの期待に応えるために頑張る人」

他者の期待に応え続けて頑張るから
疲れがたまる
2022・7・12
「なんでわたしばっかり・・涙があふれるとき」

私の望んでいたのは
こんな生活・こんな家族じゃない
あなたは「なんでじぶんばっかり・・」と感じることはありませんか?
ご家庭で職場で、「自分ばっかり頑張ってる」とか「自分だけ冷たく当たられる」「じぶんばかり仕事を押し付けられる」そう感じておられることはありませんか?
一人で頑張る、一人で我慢する、一生懸命で心根の優しいあなただからこそ起きることではないでしょうか。
今日はそんなケースの一つを取り上げます。
*********************
やれやれ今日も仕事が終わった。。暑いし疲れたなと感じながらも急いで買い物を済ませて自宅へ戻る。
居間のドアを開けたら、帰宅した子どもたちの食べ飲み散らかした後がそのまま放置されている。
当の子どもたちはゲームに夢中になって自分が帰宅したことにも気が付かない。
こんなに散らかして!食べたものぐらい片づけてよ、というも、返事すらしない。
ぶつぶつ文句を言いながら片づけ、晩御飯の支度にかかる。そこへ主人が帰宅してきた。
「あ~あ、疲れた。風呂は?」と言って脱いだ靴下をポイっとその場に投げ捨てる。すぐに用意するから待って、と言って風呂場へ。
お風呂の浴槽にお湯をため、すぐ入れるようにしますからと言ったが、主人はさっそくビールを開けてテレビを見ている。完全にリラックスモードだ。聞こえたのか聞こえないのか、何も言わない。
ビールを飲みながらテレビを見ている主人、ゲームをし続ける子どもたち。
その背中を見ながら・・何かが違うと感じる。何かが違うんだ、なぜ?なぜ?と思う自分がいる。
キッチンに戻って野菜を切りながら・・・なんでじぶんばっかり、なんでじぶんばっかりという思いが自分の中に膨れ上がる。
そして、思わず涙が。。。
私はずっとこうして人生を送っていかなければならないのか?私一人が頑張らなければならないのか?なんでじぶんばっかり、と思いながら暮らしていかなければならないのか。。
私はこんな人生・生活・家庭・家族を望んでいたわけじゃない。
***********************
お仕事をされていなくてもお子さんが小さくて手がかかり目が離せない方も同様ではないかしらと思います。ご主人がお休みの日にも自分を優先してさっぱり日ごろの子育ての大変さを受け持ってくれない。休めない心と体を抱え「じぶんばっかり。。」って、そう思うこともあるでしょうね。
「なんでじぶんばっかり・・・」そう、感じたときはすでにあなたは十分すぎるほど頑張っておられるのだと私は思います。
そしてそれを誰も認めてくれない、やって当たりまえだと周りは考えていると感じておられるのではないでしょうか。
誰も認めてくれない、周りがわかってくれないのはとてもつらいことです。そして頑張り屋のあなたは弱音を吐けないでいる。
どうしたらあなたの辛さをわかってもらえるのでしょう?どうしたら家族があなたに協力してくれるのでしょう?
もしも可能ならばあなたは自分の辛さ、大変さを理解してもらいたいのではありませんか。家族にもできることは協力してもらえればどんなに助かるかと、そう思ってもおられるのではないでしょうか。
そんなことできるはずがない、もしかしてそう思っておられませんか?
一人で頑張らなくていい方法があるのです。アドラーの子育て法、対人関係法はあなたの辛さをきっとやわらげ、皆で協力して暮らす方法をあなたに示してくれます。
頑張っているあなたへ、今の「なんで自分ばっかり」と思いながら一人で頑張る方法ではなく、他者を理解し協力して暮らしていく新しい家族の在り方、方法を学んで採用していただき、忙しい毎日という状況は変わらなくても心の負担を減らしていただけたら嬉しいです。
今の辛いあなたの暮らし、抱え込んだ心の辛さがきっと楽になります。
2022・7・8
「何回言えばわかるの?!」・・同じことで揉める
どうせ私のことなんかどうでもいいんでしょ!って思っていませんか?

何度も言ってるのに・・
もう、信じられないっ!!
「ねえ、あなたって何回も同じこと言われて、それでも言われたことわからないの?!何度同じことを言わせるのよ!」
怒りに任せてこんな言葉をあなたは言ってしまうことがありませんか?
A子さんのケースで見てみましょう。
A子さんは、ご主人にいつも「帰宅が遅くなる時には連絡くださいね。」と言っていますが、さっぱり連絡を入れてくれないのです。
帰宅したご主人といつも喧嘩になってしまいます。
「こんな簡単なことがなんでわからないんだろう?!」「あなたのためにお風呂沸かしてご飯作って待ってるのに。」
「メール一本、ラインで一言、電話するとか、ちょっとのことなのに、それすらしてもらえないなんて。。」
と毎回それをご主人に伝えるのですが、ご主人はしてくれないのです。
怒りをぶつけている間にだんだん悲しくなってきます。
「どうせ、私のことなんかどうでもいいんだ。私なんか大事にしてもらえないんだ。」とそう考えたりします。
悲しさと怒りの行きつ戻りつの気持ちがますますご主人への態度を硬化させていきます。
「仕事中にちょっと・・ってなかなかできにくいんだから、それぐらいのことでそんなに怒るなよ。」とご主人はA子さんの気持ちが理解できないようでうんざりしたような顔をしてしまうのです。
あなたにとって大したことじゃなくても私にとっては大事なことなのに、わかってくれない。。。
そんな風に思うとますます悲しく、怒りがこみ上げてきます。そして「あなたなんか絶対許さないから!」と思ってしまうのです。
あなたの気持ちはよくわかります。私もそう思ったことが何度もありましたから。そして意地になって何日も口を聞かなかったりもしました。
さて、アドラー心理学で対応するとどうなるか。。
アドラー心理学では「人はどうしたら仲良くなれるか」を目指す心理学です。仲良くする方法の集大成がアドラー心理学です。ですからこの場合「争って勝つ」、すなわち「ご主人に言うことを聞かせる」ことがゴールであれば使えないことになります。
そうではなくて「自分の気持ちを知ってもらって理解してもらってどうするか考えてもらう」をゴールにします。
そうすると今の伝え方ではない方法が考えられます。怒ってしまったら「自分が怒っていることは伝わりますが、何がわかって欲しいのかは伝わりません。
あなたはこの場合何をわかって欲しいのでしょうか。そうですよね「連絡をくれないと自分が困るし悲しい」ということが伝わればいいのです。これをそのまま伝えます。
そうするとまず喧嘩にはなりません。なぜなら「自分の気持ちを自分もOK、相手もOKの主張の仕方で伝える」ということになりますから。
そしてお互いに歩み寄りながら解決するにはどうしたらいいのか、についてきっと話し合うことになるでしょう。相手の立場や気持ちが理解でき、お互いに思いやりの心をもって相手に対することができるようになります。
これらの方法を使えば、「悲しませてしまった」と理解したご主人からは「これからはできるだけ連絡するようにするよ。いつもありがとう。」という言葉や、わかってくれたご主人に対してうれしく感じたあなたは「彼には彼なりの事情もあるんだ」と知ることができて「もっとおいしいご飯作るね。」と考えたりも出来ると思います。
2022・7・2
「イライライラーどっか~~~ん!!」していませんか?

我慢して大爆発!していませんか?
「なんでそんなこと言うの?」
「それって普通そうしないでしょ?」
「言った通りにしないから。言うこと聞けばいいのに。」
「そんなことするなんて信じられない。」
「言わなくてもわかってよ。」
「ちゃんとやって!」
というような数々の気持ちを抱えて言えなくて、たまりにためて最後にどっか~~~~ん!!
タイトルをご覧になっていかがですか?実はこれかつての私です。
爆発した時はすっきりするんですよね。
でもそのあとでじわじわと「あんなに怒らなきゃよかった。傷つけちゃった。あんないい方しなくてもよかったのに。」って自分がへこみます。
最後の最後に自分が一番傷つくのです。
そして「ああ、やっぱり私って駄目なんだわ。自分が好きになれない。」って思うのです。
そういう私でしたが今はそういうことはありません。
これは対人関係の方法を変える、新しい方法を採用したからです。それがアドラー心理学の子育て法、対人関係法でした。
今までの習慣を変えるのですからとても時間がかかります。でも少しずつ取り組めば誰でもできる方法です。
今かつての私のように自分を最後に傷つけてしまっている方、ぜひ新しい方法を採用して自分を傷つけるのをやめていきませんか?
そして自分を好きになってください。
この間スーパーである高齢の女性に怒鳴られたんです。「そこ、どけ!」と言われました。
びっくりして思わず主人と顔を見合わせましたが「怒られちゃったね。」と言って二人で笑いました。
肩を怒らせ歩き去っていくその女性の後姿は心なしかとても寂しそうに思えました。
私だってアドラーに出会っていなかったら・・・と思ったり、出会えた自分は幸せだなと同時にそう思いました。あなたにもきっとできる方法です。ともに新しい方法を身に着ける道を歩んでみませんか?
2022・5・17
「相手にイラっと来た時の捉え方」

自己決定すること
相手にイラっと来た。相手の行動にイラっと来た。
人間関係を良好にするにはそれらのケースでどう起こった出来事をとらえなおすかが大事です。
あなたが嫌だなと感じたこと、感じた人について考えてみましょう。
友人と待ち合わせをしてランチをすることになったが、時間になっても約束した相手が来ない。イライラが募る。
20分が過ぎて相手がやっと来たが「ごめん、悪いね。待った?」と全然悪いことをしたように感じていないようだ。
それでも「ううん、私も今来たとこ。」と言ってしまう自分がいる。なんで「遅いよ。」ってはっきり言えないんだろう。そんな自分も「やだな。」と思う。
相手にそう言いながらも心の中では「もう少し謝り方ってものがあるでしょう?」と思ったりする自分がいるからだ。
「人を待たせて平気だなんてちょっと性格疑っちゃう。」
「へえ、こういう人だったんだ。。」とどんどんネガティブな思考が膨らんでもやもやしたまま。それがどんどん相手への怒りを呼び込む。
ランチを食べていてもさっぱり味がわからない。せっかく楽しみにしてたのに来なきゃよかった、とさえ思ってしまう。
「あなたが時間通りに来れば、こんな嫌な気持ちになることもなかったのに。あなたのせいよ。」
ランチ後どこか行く?って言われて「今日は帰る」って言ってしまった。別れた後で「なんか気が付いたかな。悪いことしちゃったかな。付き合えばよかったかな、とまた悶々とする。
せっかくの楽しみにしていたランチが台無しになってしまったケースですね。
さて、アドラー心理学で考えていきましょう。
最初に遅れてきた相手にイラっとしていますが、その怒りはあなたのどういう思考から来ていますか?
「時間や約束は守るべきである」とか「相手を待たせてはいけない」とか、ですね。これはあなたが大事にしている価値です。
あなたが大事にしている価値はあなたのものであって、相手も同じように大事にしているとは限らないのです。友人との気楽なランチだから仕事の時のようにキツキツ考えなくてもいいと思っていたかもしれません。また「どうして遅れたの?」とその場で聞けば何らかの理由が出てきたかもしれません。
自分が大切に思っている友人であれば「どうしちゃったんだろう?」という不安もあるかもしれませんし、「もっと私を大事にしてよ。」という悲しみから来る怒りなのかもしれません。
いずれにしても最初に何も言わないでしまったことが後々の怒りを増幅させたことは間違いがないように思います。
とっさの時に聞けない、これはよくあることですが、実はこの言わないでしまったことが後々までもやもやした気持ちを引きずったり相手への怒りを増幅する原因になったりするのです。
何かがまたあったときに「あの時も~だった。」と持ち出したりもしたりしてしまいます。嫌な出来事というのは相手の存在と共に記憶に残りやすいのです。自分の中にも、モヤモヤが残ります。相手へのマイナスイメージが蓄積されていくので、積もれば相手との関係を切ってしまったりになりかねません。
あなたの小さな「イラっと」を見過ごさないことです。そして自分の気持ちに丁寧に向き合って相手に伝えていくことです。
捉え方も伝えることで変わる可能性があります。相手は言い訳をしたくない人かもしれません。
「20分も遅刻はやだなあ。」短いフレーズでいいのです。ストレートに伝えてみてください。そうすると「ごめん、実はね。」と何かしらの理由があったのかもしれないのです。
2022・5・17
「この子が反抗的なのは何のため?」目的を見ると相手のことが理解できるんです。

行動の目的は善である
アドラー心理学の人間関係を良好にするコツの一つに「相手の目的を見る」という方法があります。
私たちは相手が何を言ったか、どう行動したかにばかり目が行きますが、言ったことやしたことには必ず目的があり、その目的は善であるとアドラー心理学では考えます。
たとえば、素直な長男に対して反抗的な次男。「どうしてこの子はこんなに反抗ばかりするのかしら?」と考えてしまいがちですが、目的を考えると「反抗する」という方法を使ってなんらかの目的を達しようとしていると、そう捉えます。
「うちの子なんですけど、長男はとても素直で大人しくていい子なんですけど、それに反して次男は反抗的で乱暴で困ってしまうんです。同じように育てたつもりなんですけどどうしてこんなに違うんでしょう。」
よくあるご質問とお悩みです。
兄弟同士ってどうしても争うんです。どうして争うかというと「親の愛」を得たくて争うんです。どっちが親に愛されているのかは自分がグループの中に居場所を持つために必要だと感じています。愛されていないと自分はここにいられないと思っています。それが子どもです。
次男さんが長男さんと別の性格特性を発揮する目的は「親に自分の方を向いてもらいたい」という目的で「反抗」という形でそれを達成しようとしているのかもしれません。長男と同じ方法「素直さ」や「大人しさ」では自分の方を向いてもらえないと感じて別の方法で目的を達成しようとしている可能性があります。
「自分の方を向いてもらいたい」という考えは悪い考えではありませんよね。むしろ人間として自然な願いであり、善であるとアドラー心理学では考えます。
ですので目的は「善」です。しかしながら「方法」が「反抗」という方法なのであまり家族間では役に立たないというか親との関係を良くする方法ではないということになります。
最終ゴール・、目的が何にしろ私たちは皆違う方法をとるのです。方法が役に立つ方法を使っているか役に立たない方法を使っているか、好ましいか好ましくないかの違いだけです。
ちなみにA君にあこがれるB君がいたとして、「彼のようになりたい」と思ったB君が考えられる方法の選択肢は三つあげてみました。図をご覧くださいね。B君がグループに所属するのに役立つ方法はどれになるのか・・・お分かりですよね。
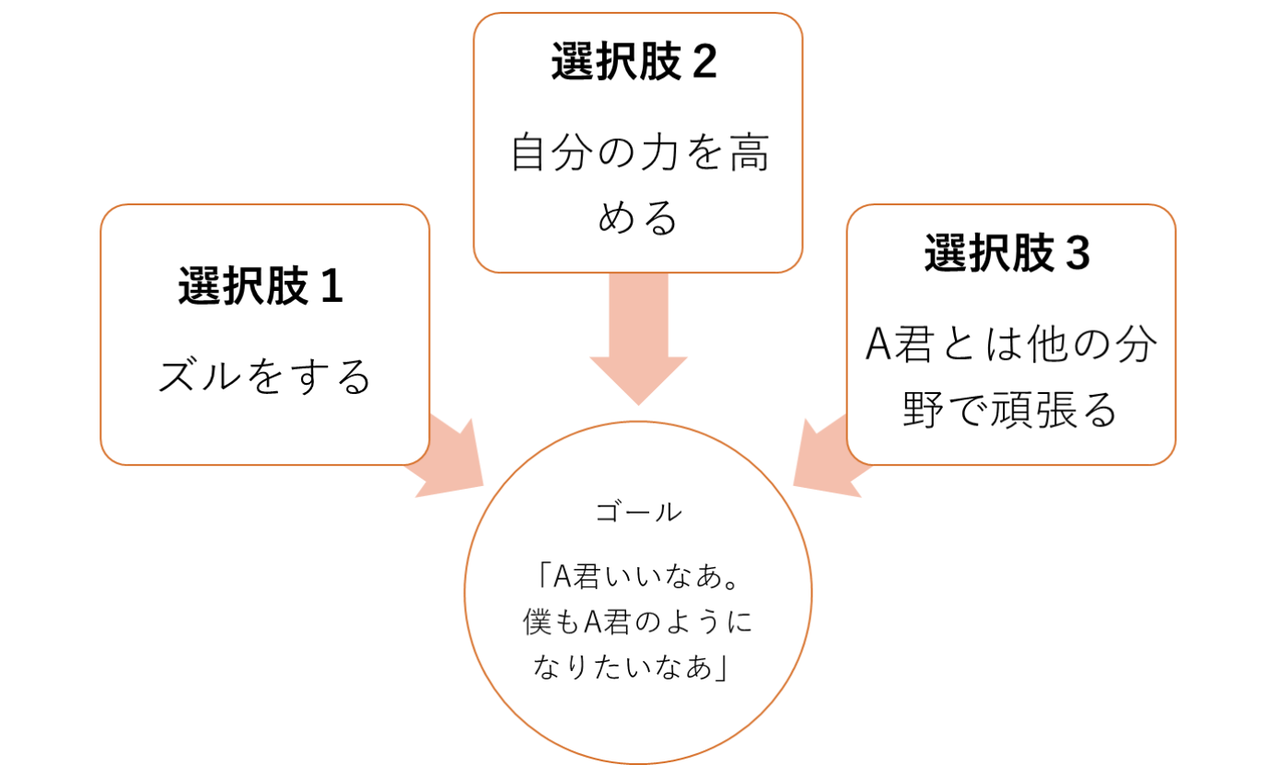
目的は善「方法が違うだけ」
2022・5・16
「いい人だと思ったのに・・がっかり」が多いあなたへ他者への視点を変えて嫌いな人を減らす三つのポイント

相手のどこを見ますか?・・
「いい人だと思ったんだけど、あんなことするなんて。。もうあの人とは付き合わない。」
「長い付き合いだからと我慢していたけど、やっぱりダメだわ。もうあの人との付き合いは切っちゃおう。」
我慢してまで付き合う必要なし、嫌なところを見ちゃってがっかり。あんな人だと思わなかった。。
さて、あなたにはそういう気持ちになったこと、なることがおおくありませんか?
結果として相手と疎遠になったり、相手との関係を切ってしまったり。
よくわかります。私も以前はそうでした。「許せない」と感じてしまうと、相手との関係を自分から切っていました。
当然ながらお付き合いできる人がどんどん少なくなっていきます。そして「どうして自分は人とうまくやれないのだろう」と悩んでいたのです。
こういう状態に陥っている場合、いくつか検証するポイントが三つほどあります。
<嫌いな人、苦手な人が多い場合に検証すべき三つのポイント>
一つは相手の行動を見るときに嫌だなとか不適切だなと感じるところばかりをクローズアップしてみてないかどうか、です。
実は私たちには「嫌だな」と感じると、その自分の考えが正しいことを裏付けることばかりに目が行くという脳の働きがあります。
嫌な人であると感じた自分が「やっぱりそうだ。」と感じる情報ばかり集めてしまうのです。そしてその嫌な人ということがあたかも正しいことのようにしてしまうのです。
日本にはこんな言葉があります。「坊主憎けりゃ袈裟まで」という言葉ですね。
ですから「もしかしたらそういう見方に陥っているのではないか」と検証してみることです。
アドラー心理学の勇気づけは相手のいいところに注目するという方法です。これが身につくと「よきところ」「適切な行動」に注目し、相手の良くないところ、不適切な行動には注目しないという方法をとります。ですのでいやだなと感じ所にはフォーカスしなくなっていきますし、相手のよいところにもちゃんと目が行くようになり「そんなに悪い人ではないのかもしれない」と考えられるようになっていきます。
二つ目は相手の不適切な行動は何のメリットがあってそうしているのか、を考えてみることです。
子どもがいくら言っても爪を噛むのをやめない。それはママの注目を得たいというメリットがあってやっています。
夫がいくらお願いしてもお酒を控えてくれない。「ストレス解消」というメリットを得ているかもしれません。
相手の行動は何か原因があってそうしたのではなく、何か得たいことがあってそうしたのであると考えます。目的がわかるようになると、その目的そのものは悪くないことが多く、使っている方法があまり好ましくないのだということがわかるようになります。ですからそのメリットを得るほかの方法を考えて提案することができます。
最後の一つはそのクローズアップしたところを相手のすべてととらえてしまっていないかどうかです。こういう一部を前部ととらえてしまうような物事の見方をベーシックミステイクスといいます。認知のゆがみとも言います。
相手のある時ある場所でのほんの一部の行動を見て、その人全部ととらえてしまう見方です。これでは短所が見つかればすぐに縁を切ってしまうことになってしまいます。
当然のことながら自分にも短所がたくさんあって、それを理由に相手から縁を切られたら悲しいと思えるようになりました。
以上のような三つの検証が必要になります。この相手の見方の修正をし徐々に他者への捉え方を変えていくことでほとんどの人とお付き合いできるようになっていきます。苦手な人もいなくなっていきます。
付き合うかどうか、どの程度付き合うかを自分で決めて相手との関係を築けるようになっています。誰に対しても同じにしなくていいのだということもわかるようになります。
こういう方法は一度学んだからと言ってすぐにできるわけではありません。自覚的に自分の癖を修正していくことが必要になります。
このようなご相談は相談会やサポート会などの機会を設けています。
まずは自分がどういう状況で他者とうまくいかないのかを見極めて、そこの修正を試みることが大事と思います。
ご自分の状況は相談会で受けておりますのでどうぞご活用くださいね。
2022・5・14
「仕事のできない同僚にイライラ」同じ給料もらってるのに。。。と感じたときの捉え方

なんでよ?!って思ったら・・
「何度言っても同じミスをする同僚」「同じ仕事をしているのにやたらと仕事が遅い同僚」そんな時あなたはこう感じていませんか?
「なんでわかんないのかな?こんな簡単なこともできないの?何度言えばわかるの?同じ給料もらってんだからちゃんとやってよ。」
「だからいってんじゃん!!こっちばっかり先に終わるからいつもあなたの手伝いしないと仕事が終わらない、不公平よ。」と同じ職で働いている同僚にイライラすることありませんか。
そしてつい「だからあの人ダメなのよね。使えないわ。まったくおんなじ給料もらってんのにこっちはちゃんとやってるのに、あっちはできない。って頭に来るわ。」
確かにそう感じる気持ちはとてもよくわかります。自分がより仕事をしているとすれば不公平だとも感じることでしょう。
そんな時、こんな風に捉えなおしたらいかがでしょうか。
「人には得意なことと不得意なことがある」「相手は同じ職場で働く仲間であるから協力して仕事を終わらせられればいい。」「仕事の量やペースがどうであれ最終的には会社の利益になればいい」
職場で達成するべきは「職場の利益」です。ですから皆が同じ方向へ向かって助け合いながら進んでいくという状態になっていればいいのです。
同僚同士が争いの気持ちを持つことは仕事をイライラしながらこなすことにつながり効率的に進まない状態に陥ってしまいます。
今一度仕事とは「会社の利益のために協力して仕事をこなすところである。」ということを考え直してみたいものですね。
2022・5・12
講座&フォローが必要な理由

知識だけでは車の運転はできない
先日講座を受講してくださった方が「本で読むのと実際に講座を受けるのは大違い。」とおっしゃいました。
私はよく車の運転でたとえますが、車のことや運転の方法を本で読んで知っているとします。でも運転はできません。実際に運転するには練習が必要です。
そして本で読んだ運転の方法を自己流の解釈をしている可能性もあります。
基本を講座できっちり学んだうえで何度か練習が必要なのです。そうして初めて快適に運用できるようになります。
一番人気なのはアドラーコンパクトです。マンツーマンで今の一人一人の悩みの状態に合わせて学べますし、受講間隔の設定も自由です。しかもお財布に優しい。「この受講料はほんと助かります。」って言われることも多い講座です。
残念ながら土日は空き時間があってもすぐに埋まってしまいます。平日でしたら割とご希望に添えるのですが、皆さんお仕事されているので時間のやり繰りは大変です。
でも受けてよかったと一番思っていただけている講座です。
気になる方は以下のリンクで詳細をご覧くださいね。
2022・5・10
人間関係で必要なのは「共感力」

要求よりまず「相手を理解しようとする気持ち」が大事
GWは講座や相談をびっしり入れてしまって昨日はさすがにヘロヘロでしたが、ちょうど主人も休みだったのであっちこっちへ出かけて気分転換してきました。
先日「人間関係で一番つらいこと」というページをアップしましたが、とにかく相手に対して「理解しよう」という気持ちのない人が多すぎると感じています。
「理解できない」かもしれないが「理解しようとすること」はできる。
「理解しようとしてくれている。」それが伝われば相手はこころを開く。にもかかわらずまず「要求」や自分の「主張」をまず先とばかりにする人のなんと多いことか。それでは人間関係は決してうまくいきません。
日曜日のサポート会で「共感」ってどういうことなんだろうね、というテーマで皆で話し合いました。
10人いれば10人の解釈があるだろうと思います。アドラー先生は「相手の目で見て、相手の耳で聴き、相手の心で感じること。」とおっしゃっていますが、言うは易し行うは難しです。
私自身は自分が共感を持てているかどうかは相手の反応で判断します。相手が初対面にもかかわらず率直に心を開いて自己開示してくれた時、どうやら持てていたようだとそう思います。
そうねえ、今は9割がたできるようになったかな。共感力だって自分で意識して育てていかないと育たないのです。l
2022・4・27
劣等感「自分は劣っているという感覚」の使い方

劣等感の使い方は
役に立つのか立たないのかで決まる
アドラー心理学の大きなテーマの一つに「劣等感の使い方」があります。アドラーの最初の著書も「器官劣等」についての著述でした。
劣等感には二種類あります。他者と自分を比較することで生まれる「対他劣等感」。そして理想の自分と現実の自分を比較することで生まれる「対自劣等感」です。
対他劣等感は持ってもあまり意味がありません。なぜならもし比較した相手を自分が超えることができたとしても、上には上がいるのが現実だからです。対他劣等感に悩んでいたとしても大概の人はそのことにいずれ気が付きます。
アドラー心理学で取り上げるのは「対自劣等感」です。理想の自分と現実の自分とのギャップが劣等感を生み出します。
その時にどうすればいいのか、答えは二つ。自分を高めることに使うのか、自分をあきらめることに使うのかの二択です。どちらを選択するかは自分が決めていますし、自分で決められるとアドラー心理学では考えるのです。
理想と現実があまりにも乖離している場合にはとても本人は苦しいと思います。たとえば「完全でありたい」とか「完全でなければならない」というような理想を持っている場合、完全でない自分に劣等感を感じてしまいます。
完全でありたい、はあってもいいのですが「完全な自分」はありません。そのことに気が付いていただいて理想を少し下げることも必要になります。いずれにしても劣等感を自分のエネルギーに変えて高めることに使うには「勇気」が必要です。逃げるのはいつでもできますし簡単なことですが、やり続けるといつまでも自分に自信が持てないということになります。
現実可能なことから劣等感を自分のばねにして日々向上していく。それがアドラー心理学で生きるということになるでしょう。
2022・4・22
性格はいかにしてつくられるのか

1人1人全く違う性格
それはどこから来るのか?
アドラー心理学ではいわゆる性格をライフスタイルと呼びます。ライフスタイルはどのように形成されるのかというと、10歳ぐらいまでの自分を取り巻く人々の行動、起こった出来事をどう意味づけしたかによって本人が選択・決定します。
もちろんその選択と決定は意識レベルの低い段階でなされていますので、本人はほとんど自覚がありません。
したがってその選択・決定がどうも他者関係で不具合を起こしてしまうという場合が現在の人間関係がうまくいかないというケースです。実際には、選択のし直し決定を変えればいいということになります。
それにはアドラー派のセラピストによって「ライフスタイルの解明」が必要になります。どこをどう変えればいいのか、今の自分はどういうわけで意識しないまま不具合のパターンを繰り返しているのかがわかって初めて変えられることになります。
これはライフスタイル診断・早期回想分析という方法でクリアになります。ほとんどの方はアドラーの子育て法・対人関係法を実践することで解決できると私は感じており、ライフスタイル診断・早期回想分析までは必要がない人がほとんどです。
ライフスタイル形成の一つの要因となるのが下記の図です。子どものころ自分を取り巻く大人たちはどのように行動していたのか。例えば相手に言うことを聞かせたいのであれば怒鳴るとか、泣くとか、いろいろな方法を使ったであろう大人のことを子どもは目の当たりにします。
その中から自分にとって都合のいい方法を採択したのが今の自分です。
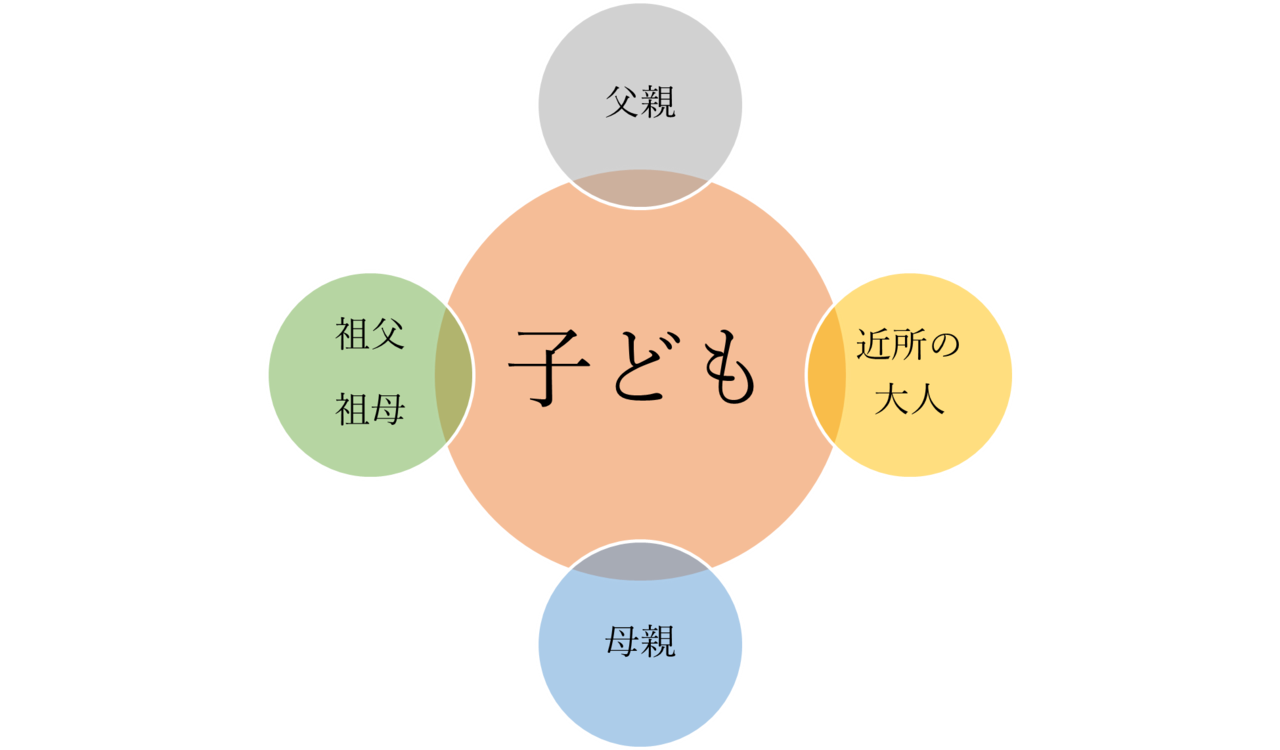
性格形成は自分を取り巻く大人たちがどう動いていたかが鍵
2022・4・20
謙虚と謙遜

謙虚は必要・謙遜は不必要
最近講座中によく話が出て盛り上がるのは「謙虚と謙遜」について。
日本人って褒められると「いやいや、そんなに自分は大した人間ではありませんよ。」みたいな謙遜が出る。
ある受講生が、私に「謙虚であることは必要だけど、謙遜は必要ないよ。」とピシャっと言われたことを忘れられないという。
謙遜する限り「自分にOK」は出せませんよね。自分がちゃんと努力してそれを誰かに「すごいね」って「頑張ったね」って言われたら「ありがとう」という言葉が出てくるはず。「ありがとう。はい、私は頑張りました。」の意味ですけど、あなたは出てきますか?
謙虚であることと謙遜することは全くの別物。謙遜は別に要らないと思う。努力しているならそれをちゃんと認めること。誰にはばかることなく「自分は頑張りました。」「頑張ってます。」って。
結果ではない。努力した、取り組んだという経過が大事。これができると結果が出なくても落ち込むことはない。なぜなら努力したということ、自分なりに取り組んだことを一番わかっているのは自分だから。
「自分を認めてあげられるのは自分しかいない」
他の誰が認めてくれなくても自分で自分が認められればいい。これができる人は本当に強い。これを講座にしたのがセルフコンパッション。ありがたいことに結構お申込みをいただいてこれからの人気講座になりそうです。「自分にOK」出せる人が増えていけばいい。自己受容していると何があっても揺らぎません。がっちり大地に根を張って生きられます。興味のある方は下記のリンクから見てみてくださいね。
2022・4・18
日本のタブーに切り込む

世代間連鎖を断ち切る
今いろいろな人間関係で悩んでいる方の根っこにあるのは自分と親との関係から派生しているんです。
親の使っていた方法を子どもの自分が採用して対人関係に使うことで不具合が起きている。
表面的にはアドラー心理学の対応法でだいぶ改善されるんだけれども、もっと深いところに根っこがあるので、親子関係がかつてどうであったかということを見て言って、どこがどうかを見極めてから修正して行かないと本人の生き難さはなくならないんですよね。
たとえわかったとしてもそれを別なものに変えるかどうかは本人次第なわけですが、親子関係で難しいのは「親を否定してはならない」という日本人特有のタブー。
否定するわけではないのですし、親が使っていた方法を使うことがあなたを生き難くしているのだからそれを別な方法に変えたらどうでしょうって話なんだけれども、そこは認知の問題で、かなりの抵抗を感じる人がおられる。親を否定する=自分を否定するって考えちゃうみたいです。
ところがうちの受講生のほとんどは、やはり親との関係で悩んでいます。話を聞いてみれば明らかに親の方に門題があったりもする。そして「親を嫌う自分はどこかおかしいんじゃないか」と考えたりして自分を責めたりもする。これはとても本人にとっては辛いことです。
親のことは親のこととして「自分はどう生きるか」の再構築ーこれがアドラー心理学でやれることです。
人は変えられませんが自分のことは変えられますから。
2022・4・15
「人は変わるものだ」が大前提

昔と同じ・あの人のことはわかっているという思い込み
人間関係の悩みトップ5をサイトに掲載していて、男女ともに「友人関係」がリストアップされました。
年代を経るにしたがって、皆環境が変わりますし、また体験から大きく人間そのものが変わっていて別人になっているということもあります。
昔と同じ感覚でいると、相手が付き合いにくく感じたりするのです。
相手も自分も変化しているはずですが、「あの人は~だから」という決めつけ。これされると嫌なんだよねえ。
私はあなたの知っている以前の私ではありません、と言いたくなったりします。自分が変わらないからといって相手も変わらない、変わっていないはずだというのは少々説得力に欠けます。
友人関係が歳をとるにしたがって疎遠になって言ったり、苦痛になっていくのは、環境・生活・価値観のほかにその人そのものの変化(考え方など)もあるのではないでしょうか。
相手のことを知っているという思い込み、身近な人間ほど陥りがち。気をつけたいものですね。
2022・4・12
他者関係に必要な配慮の表現

意見言葉や仮定の言葉を使う
他者関係であまり使わない方がいい表現には「断定・決めつけ」があります。
「相手の気持ちは、相手の考えは相手に聞いてみなければわからない」が大前提です。
また自分が正しいという傾向が強い場合「~に違いない」などの「~なんでしょ!」と言った言い方もしてしまいます。
特に怒りの感情に任せて言ってしまいがちですが、こういう言い方をすると相手の感情を逆なでするだけでなく、相手は返事のしようがなくなったりします。
アドラー心理学を実践していくとまず意見言葉が使えるようになります。「わたしは~だと思うのだけれど。」とか「~だと私は思うんだけれど。」と言った表現です。
また他者への共感ができるようになれば相手の気持ちや意見の確認に「もしかしたら~かな?」という言い方ができるようになっていきます。
こういう言い方をできるようになれば、相手との関係が悪くなることはそうそうないのです。
2022・4・6
男女のすれ違いは何から起きるか

どうして起きる?男女のすれ違い
ご夫婦やら恋愛中のカップルやら、いつもうまくいくことばかりではありません。ご相談は多いのですが、その基本的な男女の違いを理解しているかどうかがカギになります。さてその原因とは?について書いてみます。
大概意見の食い違いとか価値観の違いとか、何かが起きた時にすれ違いが大きくなっていきます。
この辺はアサーティブ・相手もOK自分もOKの伝え方で相手と関わることでほとんどが解消されますが、根っこの部分で男女の違いについて理解しているといいように思います。
何か問題が起きた時、男性はほとんど「解決へ向かって進もう」とします。けれど、女性は「その問題についての自分の気持ちが解って欲しいという「共感へ向かって進んでほしい」と思うのです。
男性は解決に向かい、女性は共感を求める。
この違いがわかっていると男性は「彼女は解決してほしいのではなくわかって欲しいんだ。」と思えばいいし、女性は「彼は自分の気持ちどうこうよりもどうしたら解決できるかを考えているんだ。」と理解できます。
あとはアサーティブでお互いの歩み寄りを計るだけです。仕事をする女性がほとんどになってきている現代では、男女が逆になるケースも見受けられます。
実際には基本的な部分ではこの違いを押さえておけばそれほどすれ違いは広がりません。
妻が「今日は~があってね。大変だったの。」と言ったとき、あなたが「それは~すればいいでしょ。」みたいな返事をしていたとしたら、それは妻にとっては不満足な答えになってしまうでしょう。
「そう、そんなことがあったの。それは大変だったね。」と返すご主人、恋人であればきっと「わかってもらえた」と満足を得られることでしょう。
お互いの違いを理解しようとすること「共感力」を持てるかどうかにかかっていると言えると思います。これは自覚的努力が必要ですが、「理解したい」という気持ちさえあれば育むことは誰でもいつからでも持つことができると思います。
2022・4・5
三回続けると人格否定になる要注意な言葉

つい・・・繰り返してしまう
要注意な言葉
日常生活でつい使ってしまう危ない言葉
「なんで?」「どうして?」
これは「なんで~するの?(しないの?)」「どうして~するの?(しないの?)」という批判の響きが含まれます。
これが三回続けて使うと相手には「人格否定」と取られてしまいます。
ほとんどの方がこの表現は使ってしまっていると思います。
相手に対する期待がすでに自分の中にあるからで、その通りにならない時にこの言葉が出てきます。
「自分の考えだと当然~だと思うけど、あなたはそうではない。それは許せない。」という意味です。
「人は一人一人違うのである」「相手は自分とは別の人間であるから違うことが前提」ということが理解できていればこういう表現は出てきません。アドラー心理学の認知論ですね。
言れたほうは「そう言れても・・・。」と言葉に詰まってしまいます。返事がないのでさらに「なんで?」「どうして?」が続いてしまうようです。
挙句に「~だからでしょ!!」と決めつけの言葉になってしまいがち。これでは相手との関係は良くなりません。
自分と相手は違う人間であることが前提にあれば「ちょっと自分の考えと違うんだけど、どうしてそうしたのか教えてくれないかな?」と言ったような言葉が出てきます。
「なんで?」「どうして?」という表現は三回続けたら人格否定になるー覚えておきたいものです。
認知「出来事はどう解釈されるか」
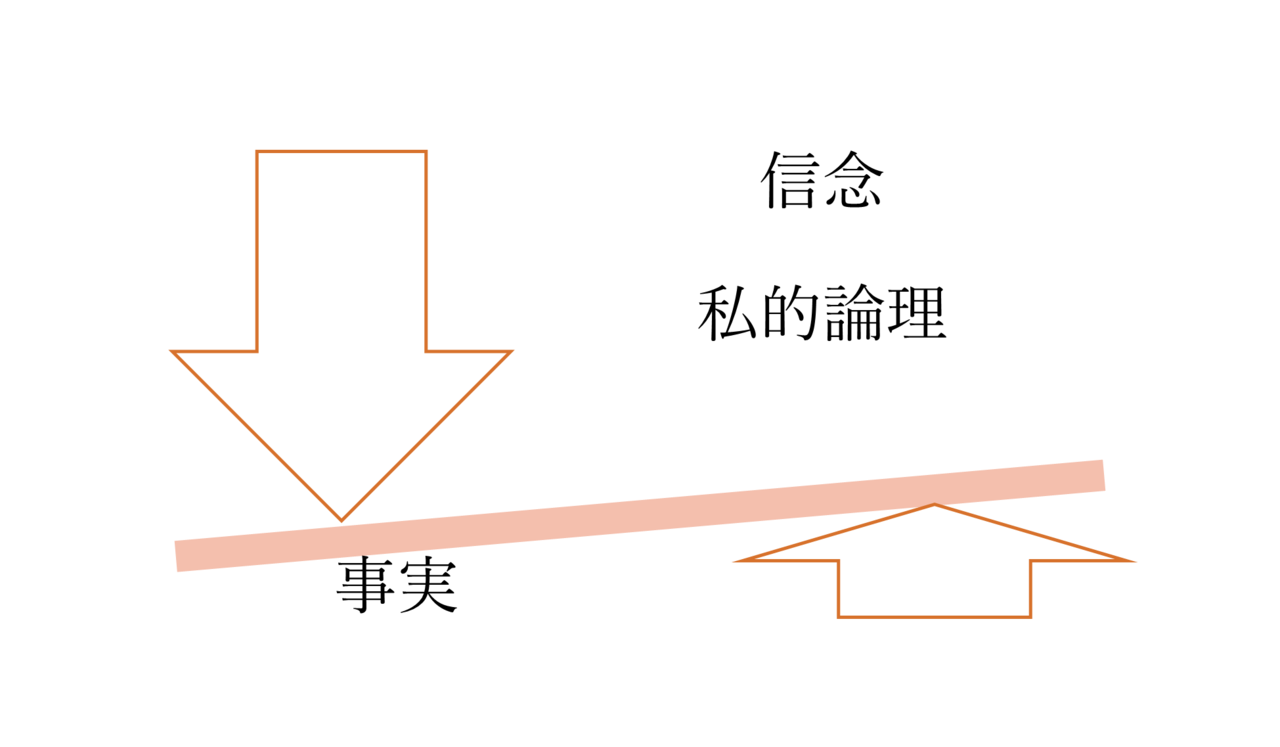
私的論理が事実より強い
人間関係で一番大きな影響が出るのが「出来事の解釈・捉え方」です。これは「認知」と呼ばれます。
今度メルマガで詳細について書こうと思っていますが、ライフスタイルでできている「私的論理」は「事実」より強い。
たとえば「人は信頼できない」と思っている人は、成育歴の中のどこかでその「私的論理」採用しています。
そうすると「信頼できる人・出来事」があってもそれは例外としてとらえ「信頼できない人・出来事」ばかりに注目して事実には蓋してみなかったことにしてしまいます。これが私たちの脳の働きです。
そうして信頼できない人や出来事の情報ばかり集め「やっぱりそうだ。」とばかりに自分の「私的論理」についての強化が起きるのです。
「そうではない事実」があることについて「あれはたまたまだった。」と考える。事実に目が行った方が「信頼できる人がいる」と考えられるので人間関係は良い方向へいくと思います。アドラー学ぶと視点が変るので、事実について正確に見られるようになります。
人間関係で一番大きな影響が出るのが「出来事の解釈・捉え方」です。これは「認知」と呼ばれます。
今度メルマガで詳細について書こうと思っていますが、ライフスタイルでできている「私的論理」は「事実」より強い。
たとえば「人は信頼できない」と思っている人は、成育歴の中のどこかでその「私的論理」採用しています。
そうすると「信頼できる人・出来事」があってもそれは例外としてとらえ「信頼できない人・出来事」ばかりに注目して事実には蓋してみなかったことにしてしまいます。これが私たちの脳の働きです。
そうして信頼できない人や出来事の情報ばかり集め「やっぱりそうだ。」とばかりに自分の「私的論理」についての強化が起きるのです。
「そうではない事実」があることについて「あれはたまたまだった。」と考える。事実に目が行った方が「信頼できる人がいる」と考えられるので人間関係は良い方向へいくと思います。アドラー学ぶと視点が変るので、事実について正確に見られるようになります。
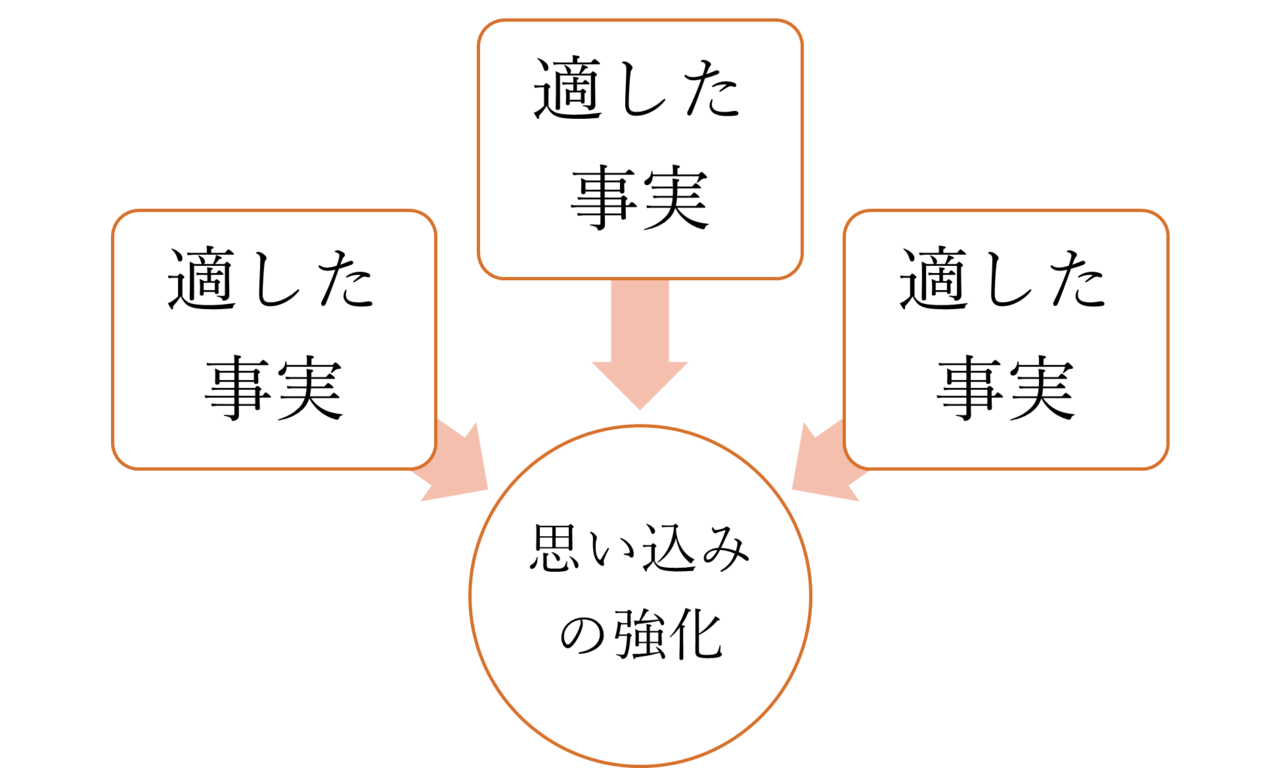
画像の説明を入力してください
自分の対応OK?Not OK?検証フレーズ
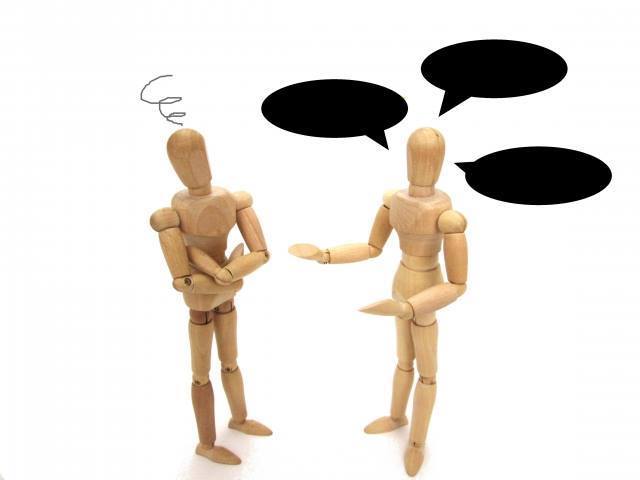
「対応」は失敗を活かしてこそ
「次」につながる
アドラー子育てを実践していると「うまくいかないなあ」とか「失敗しちゃったな」という場面は多々あるでしょう。
子どもがわがままを言って自分の意志を通そうとします。まさに理屈もなくごり押ししてきます。あなたが何と言おうと頑として聞きません。
もうすぐご飯だとわかっているのに「おやつ」をくれとねだったり、お約束のお片づけを放り出して「今ゲームしたいから」と知らんふりしたり。
そんな時、あきらめておやつを出したり、ゲームをさせ続けるとどうなるでしょう?
「ごり押しすれば通る」ことを学んでしまうかもしれません。自分の対応があっているかどうかを検証するのに便利なフレーズがあります。
対応に迷ったら以下のフレーズを自分で呟いてみてください。
「わたしが~すると、子どもは何を学ぶんだろうか?」
学ぶことがわかったらそれが子どもに役立つのか役立たないのかがわかります。社会に通用するのかしないのかもわかります。それじゃどうすればいいのか、役に立つ対応が次に考えられるはずです。
失敗した時こそ「何を学んでもらえればいいのか」そのためにはどういう対応が望ましいかを考えるチャンスだと思います。失敗を糧にステップアップしていきましょう。
アドレリアンは真の楽観主義者

くよくよ考えるより
行動したほうがいい
アドラー心理学を軸に生きていると「真の楽観主義」でいられるようになるんです。
これから先どうなるかわからないものをくよくよ考えても仕方がない。それより「今自分がすべきこと」をちゃっちゃとやりましょう、というスタンスで生きられるようになる。
お気楽主義は「やるべきことをしないでなんとかなる」という考え方。
自己肯定感が高い人の中にはこの二つを混同している人がおられるね。
真の自己肯定感が高い人って前者だと思うのです。後者に対しては「その自信はどこから来るの?」と思うことが多々ある。
昨年の秋にすごく体調が良くなったので、「走りたい」という気持ちが自然に出てきた。市民マラソンに2キロってコースがあるから、チャレンジしてみたいと思った。今年はコロナ対策で10キロのコースしかないというので来年から完全再開だということでした。
来年まで時間の余裕があるならバッチリ準備できますよね。ということで日々ウォーキングで距離を伸ばしてフットワークを軽くしているところ。
行動しないと自信はつきません。これははっきり言えます。考えているだけでは何も変わりません。行動するからこそ「自分が好き」が増えるってものです。
コロナ過で女性の自殺増加

今朝ニュースを見ていて、コロナ過の中で女性の自殺が増えているという報道がありました。
自殺者の原因内訳は、特に家庭内の問題で悩んで自殺するというデーターが示されています。
家庭内の問題と言うのは、夫婦間、子育ての問題、同居する家族間の問題とのこと。
アドラー実践する人が増えて、自己受容して生きられる人が多ければ、こんなことにはならないと思います。
アドラー心理学は「他者と協力して仲良く生きるための心理学」です。そして自己受容はありのままの自分を受け入れるということ。
双方揃っていれば、決して自ら命を絶つなんてことは起きないと思っています。
国民総鬱の時代が来ると言われて久しいのですが、「予防」という観点からはなかなか人は動かない。
自分が悩んだり、苦しかったり、生き難いと感じた時に相談をしてもらえればいいのだけれど、日本人には「身内の恥をさらさない」という強い信念がある。
それをこちらが丹念に崩していかないと、この状況は変わらないだろうと、そう思っています。まだまだやれることはたくさんある。
今年は「東北勇気づけプロジェクト」に着手すると決めている。どういう形になるか、これからプランニングです。
自己肯定と自己受容の違い

ずっと違和感を覚えていた「自己肯定」、最近になって自分の中ですっきり自己受容との違いが整理ができた。
いわゆる一部の自己肯定感が高い心理職の人たちに「その自信はいったいどこから来るの?」と感じることが多かったんですよね。
同じ資格を持っている人でもそうでない方もおられるので、性格の問題かしら?と思ったりもしていたけど、やはり自己肯定感を高めるトレーニングの過程で「捉え方・受け止め方」の違いがあったんだなとそう感じました。
自己受容は、今の自分が60点だとして、それを認めてそこからスタートし61点になるには、62点になるには・・という未来への向上心がセットになります。
それに対して自己肯定は、たとえ自分が60点だとしても100点だとしてしまうこと。これじゃ根拠のない自信に満ち溢れた人が出てくるはずよね。
すっきりしました。
「言い訳封じ」アドラーのやり方

人生の課題を前に「様々な方法」で課題を避けようとする人々の姿を今まで書いてきました。
アドラー心理学は別名「言い訳封じ」の心理学と言っていいと思います。
もっともらしい言い訳や方法で課題に取り組めない人々は勇気をくじかれているので「勇気づけ」をして「あなたにはできます。」「あなたにはその能力があります。」と勇気を持っていただけるようにしていきます。
その過程で時に「言い訳封じ」をすることもあります。相手のライフスタイルにもよりますが
「そろそろ言い訳やめませんか?」「それは問題にならないと思うのですが。」と言った介入をすることがあります。
本人はそのご自分の傾向を自覚していないことが多いのです。以前書いた直面化にも近いかもしれませんが、背中を時に強く押すきっかけになります。
こちらも時と本人の様子、タイミングを計ってのことです。セラピストとしての力量が問われます。
相手のニーズをつかめない人々
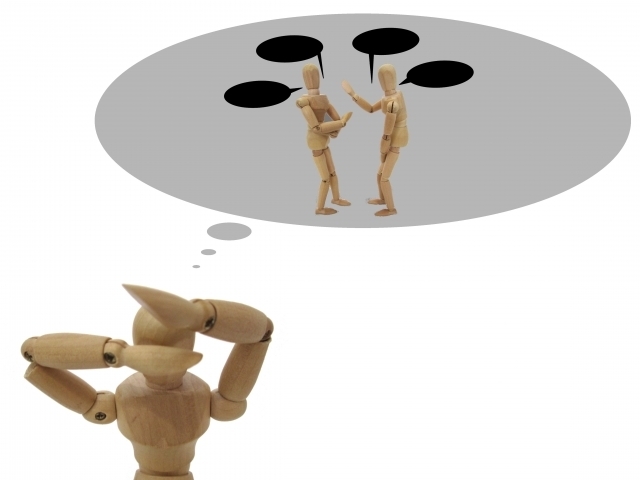
相手と話していてかみ合わないとき、お互いに相手のニーズをつかめていないことがあります。
お互いのニーズをつかめないまま話を続けると、とんでもない誤解に発展してしまいます。
アドラー心理学の認知論はこういうときにも使えるのですが、相手と通じていると思い込まない、相手は違うかもしれないということを常に意識することにつながります。
もしかしたらとんでもない思い込みを双方がしているかもしれないのです。なぜなら認知論によれば「人は一人一人違う」からであり、当然「同じことを見聞きしても感じること、考えることは違う」からです。
「もしかしたら自分の考えていることは違うかもしれない。相手は別のことを考えているかもしれない。」という意識をもっていれば、そこに必ず「確認」という作業が入ります。
特に皆さんのお近くで「思い込みの強い人」がおられるなら、こちらが「確認」をしてカバーするぐらいの気持ちで対した方がいいと思います。
また思い込みで相手が暴走した場合、「どうしてそうなったのか?」も確認して「それはあなたの思い込みですよ。」ということも繰り返し伝えていかなければなりません。
特に家族は「わかっているもの」としてこの確認を怠りがちです。身近なところにこそ落とし穴があるのだということをわかっていた方がいいかもしれません。
課題への直面化

課題を前に取り組まなくて済むように様々な方法を私たちは取ることについては今まで書いてきました。
アドラー心理学を学び始めると、その避けていた課題に直面することになります。
アドラー派のカウンセラーはその際に直面化という方法を使います。
これはあなたの課題ですから取り組みますか?取り組みませんか?取り組まないとどうなりますか?取り組むとどうなるでしょう?
など、クライアントに決断を迫る場面が出てきます。先日の事例検討会で「相手のライフスタイルを見てやらないと、、。」という話をしました。
ライフスタイルには「受け身」の人と「能動」の人がいます。受け身の人にはズバッと直面化を促しても割とうまくいくことが多いのですが、能動的な人それもバリバリのドライバー傾向(優越)の強い人については、慎重に事を運ばなければなりません。
反感を食らう、もしくはカウンセラーやリーダー不信に陥る。相手のライフスタイルなくして
他者支援はあり得ません。相手のライフスタイルを「たぶん~だな。」とわかるところまでは行けても「それじゃ~の時はどうする?」まで行かないと技術で終わってしまいます。
テクニックをスキルに落とし込む。臨床で必要なのはそういうことだと思います。
自分を守る方法(5)「排除傾向」

ライフスタイルに基づく信念が柔軟であればあるほど、人の適応力は高くなります。
頑固で柔軟性のない信念は人の成長過程で人生の課題に屈服したり、そういう人たちは自分が無傷なままで人生の方が変わってくれればいいと思っています。
もし私たちが自分を称賛する人々とだけ付き合っていたら、自分の人生を変える準備ができていないので他の人たちからのアプローチを制限してしまうことになります。
自分へのアプローチを制限し、要求に適さない人々や状況を排除することになってしまいます。違いを認め、違う人との交流を通して自分のライフスタイルの信念を柔軟にすればこそ人生に適応できるのです。
自分とは合わないから、自分とは違うからと言って遠ざけていればその柔軟性は育まれません。
自分を守る方法(5)「不安を作る」

「挑戦を避けて自尊心を予防保護する方法の一つは、不安を作ることである。」アドラー
人はうまくいかなくなると人生を恐れ、他の人々や課題を恐れます。
恐怖症やパニック、神経質な状態も、個人に課せられた課題から免除されるのに役立つのです。
私たちは何かを達成できないことを正当化するために「わたしは不安なの。」というフレーズをよく使うのです。
不安はアドラーにとっては、自分を守るための手段であり、課題への挑戦を回避する手段にすぎません。
恐れは免除にならないのがアドラー心理学です。課題を前にしり込みする人々の背中を押し続けるのは私たちアドレリアンができる最大の貢献だと私は思っています。
自分を守る方法(5)「距離をとるー障害物をつくる」

何かが終わらないと~できない。
こう考える人は結構おられます。
「子どもの受験が終わらないと。」「子どもが自立してから」「主人の単身赴任が終わらないと。」
などなど自分の課題を先送りします。
働きたくない人は「今そんな気分じゃないから」と自分の感情を理由にしたりします。
働きたくないのでこういう場合には決して感情の問題は解決しないのです。
ある人は細かいことに忙しすぎて肝心の重大な課題に取り組むことができません。
事体はどんどん悪くなる、些細な事柄を重大ごとのように考え、手元の課題にフォーカスすることができなくなっていきます。
人生は時に立ち止まるべきよ、そうでないと私は進めないの、と言って立ち止まったまま動かない人は自分の人生そのものを障害物と定義していると言えます。
自分を守る方法(5)「距離をとるー立ち止まり・大人になることを拒む人々」

人生の課題を前に「立ち止まってしまう」人がいます。
立ち止まると時間が稼げます。誰か適切な対応を指示してくれたり誰かが自分の課題を解決してくれるものとして時間を稼ぐのです。自分が課題に向き合い克服しなくて済むようにです。
他の人が自分の人生を踏み出しているにも関わらず、自分だけは遅い思春期にいるようなものかもしれません。
その人は「大人になること」を拒んでいるのです。
「大人になったら大変」とそう考えているのかもしれません。
自分の周りの大人を見てそう思いこんでいる可能性はあると思います。
大人になったら自分の課題に向き合い対処しなければならなくなります。立ち止まったまま、時間をできるだけ稼いでそれを避けようとすると言えるでしょう。
自分を守る方法(5)「距離をとるー後退・かぐや姫」

後退ー後ろへ下がることですから「課題への挑戦」から遠ざかることになります。
課題が通り過ぎるのを待つ、もしくは現実に目をつぶり課題などなかったかのように行動します。
ギリシャ文学の中にユリシーズの妻であったペネロペの話が出てきます。
ユリシーズ亡き後ペネロペは押し寄せる求婚者を前に埋葬用の服を作ることを理由にそれを拒否し続けました。
埋葬服を作り終わったら誰か一人と結婚します。実際には一日中服を縫いながら夜になるとそれをほどいていました。
押し寄せる求婚者に無理難題を出し、結婚を受け入れようとしなかったかぐや姫に似ています。
後退は断念(気乗りのしない試み)と破産(完全なあきらめ)を含んでいます。
自分を守る方法(5)「距離をとる」

人生の課題に直面し挑戦しなければならなくなった時、人は特有の動きをとることがあります。
取り組まない人の言い訳は「言葉」ですが、距離をとる振る舞いは「動き」です。
それは何をしようとしているのかを表しています。
アドラーがよく述べていたことは、人の本当の意図をしるにはその人が「どう動くか。」を見ることです。
「人を理解したければ耳を閉ざさなければならない。」
私たちは見さえすればいいのです。パントマイムを見ているように相手がどう動くかさえ分かればいいのです。
距離をとるという方法には四つあります。
「後退」「立ち止まる」「躊躇して行ったり来たりする」「障害物をつくる」
次回から順に書いて行きます。
自分を守る方法(4)「攻撃性ー非難」
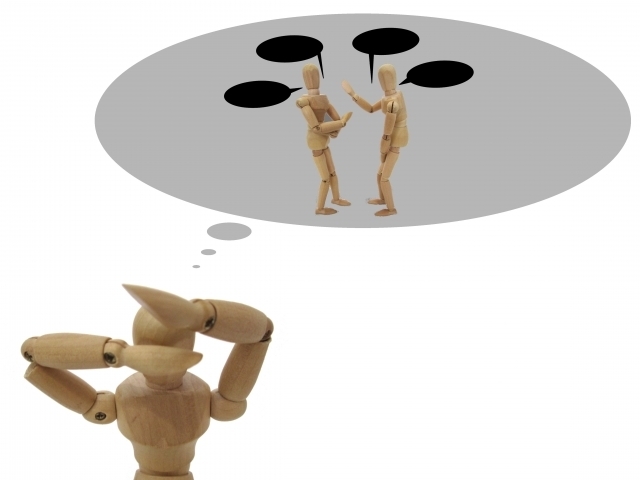
攻撃性の形をとる「非難」には二種類あります。
他者非難と自己非難です。他者非難は自己弁明です。
「自分は~である(~であるべきと思っている)のにあなたときたら・・。という形をとります。」これはどういう結果になるかというと他者が責任を取らされます。
「あなたのせいで傷ついた。」こんな言葉が浮かんできそうです。
傷ついたのはそう解釈した側の課題です。明らかに相手を傷つけようとする意図がない限り、他者はおおむね良かれと思って言っていることが多いのですが、「傷つけた。」という結果を相手に追わせて相手の責任にしようとします。
自己非難と罪の意識はアドラーが攻撃性の最終形と言った形で、アドラーはこういっています。
「もしも人が他者を傷つけるために自分を傷つけるなら、彼らは典型的な子どもの行動をとっていることになる。」
これは自殺のメカニズムを説明するのに理解しやすいかもしれません。
自分はダメな人間で存在価値がないと自殺をする人は、自分をダメにした、存在価値を認めなかった周り・社会に対して最後の手段として傷をつけようとしていると言えます。
また自分に気が付いてくれない、自分に注目してくれない周りや社会への復讐として、自分の命を懸けるという方法です。
子どもは自分や他者に何の幸せももたらさない方法で目的を達成しがちです。それは大人になっても同じで、その方法をとり続けることは容易に想像できるところです。
自分を守る方法(3)「攻撃性ー軽視」

「軽視」は実際に他者を下に見ることです。自分がもし他者より劣っていると感じたら自分自身を高めるようにするか、もしくは相手を引きずり下ろすしかありません。
「軽視」には「理想化」と「心配」の二つの形があります。
「理想化」は自分の理想を掲げ実在の人物をその理想に照らし合わせて拒否してしまうことです。
理想の女性を追い求め、会う女性をその理想で測り出会う女性を満足できないとしてひそかに価値を下げてしまいます。
「心配」は「自分がいなければ他者は何もできない」かのようにふるまいます。他者が自分を必要としていることで他者の犠牲の上に自分を高めることができると言えます。
私はアドラーをやり始めて「心配しているんです。」と言われるとなんだかとても嫌な気持ちになることが多かったのですが、理由はこれだったんですね。
自分はそんなあなたに心配していただくほど無力でも無能力でもありません、と言いたいと感じていました。
自分の中に「相手が自分を軽視している」と感じるアドラーセンサーが働いていたんだと思います。
分かり易い例で言えば「心配だからちゃんと~してね。」と親に言われると、子どもは「親に心配かけちゃいけない。」と思います。そうすると親に心配をかけないようにすることが子どもの思考・行動にブロックをかけてしまいます。
そうしないと家族という共同体に自分が所属できない、所属が危うくなると感じるからです。
自分が差し迫った状況(いじめ)などに置かれていても、親や身近な大人に相談できない子どもがほとんどで、追い詰められて死を選んでしまうのは「話したら心配をかける」というブロックが働いているということも考えられます。
良かれと思っての心配もほどほどにしておくに越したことはないのです。
課題分けで言えば「心配」は親の課題であり子どもの課題ではありません。自分の課題を子どもに肩代わりさせてしまっているということに気が付けば、ほどほどに・・・ができるようになると思います。
大人同士でもこれは同じです。相手のことが心配なのは自分の課題なのです。
自分を守る方法(2)「言い訳」

症状が無意識であるのに対して言い訳は典型的な意識的な自分を守る方法です。
個人はいつでもそうですが「こうでなかったら、私は~できただろうに。」ということを言いたがります。
アドラーはこういう方法を
「はい、でも・・YES~BUT」と言っています。
「~しませんか?」に対して「はいそうしたいです。でも~」というわけです。
お子さんでしょっちゅう手を洗っているお子さんがおられますが、アドラー心理学でいうと「彼女(彼)は現実の問題を避けるために手洗いを利用している。」ということになるでしょう。
現実に適応するよりも自分の清潔に固執している状態と言えます。
「もしこの手洗いをやめることができさえすれば、働けるのに。」という言い訳に使われます。
言い訳は別な言い方をすると「合理化」です。あたかももっともだと自分も周りも納得するように「言い訳」を合理化するのです。
合理化も言い訳も人間のプライド・自尊心を守るためのものであることと考えるのです。
自分を守る方法(1)「症状」

症状を発現する人々は、課題や挑戦に対してまだ準備できていないと感じていて、これを避けるために症状を使います。
もしも私に頭痛が起きたらテスト勉強をするにはあまりにも「具合が悪い」のかもしれませんし、私がとても落胆していたら、他の人に私のことを世話させることができるかもしれません。
もしも指示を聞くだけでいっぱいになっていたら、私は仕事の課題に打ち込めないわけです。
人間の機能における症候学の役割については別に記載しますが、ここでは症状は自尊心を予防保護し、責任や他者との関わりからの免除のために作り出されることと指摘しておきます。
自分には「まだ準備が整っていない」と感じているのです。準備が100%になったとしても、何か理由を持ち出して取り組むことを避ける人々は勇気をくじかれています。自分の能力を信じていないし、自分に価値があるとは思えないでいるのです。
だからこそ「勇気づける」ことが必要なのです。「あなたには価値があり、あなたには能力がある」ということを伝え続けなければなりません。
自分を守る働きー「セーフガード」
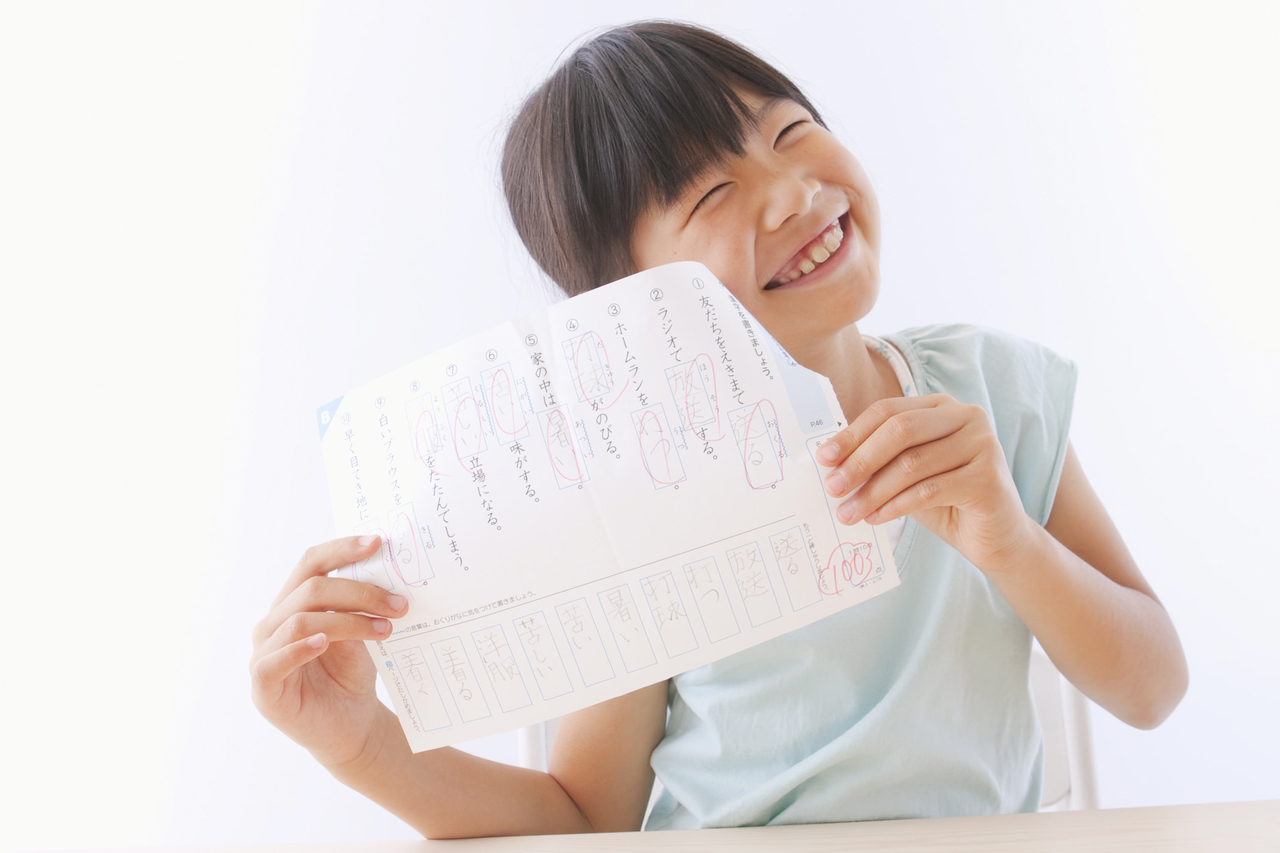
私たちにはもともと生物としての防衛本能が備わっています。
生き抜くために必要があってあるのですが、これが他者に対して使われるとどうなるか、どういう反応・行動が起きるのか、についてしばらく書いていこうと思います。
人によっていろんな形をとりますし、あってしかるべきものですが、程度が問題になるのです。
自分を他者から守るって結局のところ「自尊心が傷つかないようにする」ということです。
自尊心を守るための行動ー症状・言い訳・攻撃性・距離をとる・不安をつくる・排斥&除外
こんなところが挙げられます。
私たちの心の仕組み上「自分を守らなきゃ」と思ってそうしています。
これが過度なのが「神経症」と言われる状態です。自分の能力を信じていないので、人生のタスクから逃げようとします。
その際に上記のような反応が出るのです。
アドラーを学ぶことで自分に自信がつけば「そんなに自分を固くガードしなくても大丈夫みたい」とか「わりとできるかもしれない」と思えたり、強すぎた傾向が緩和されていくと思います。
おひとりさま好きと孤立・孤独はイコールではない

昨日の記事でフューチャーマッピングの画像が小さくて見えないというご連絡があったので最後にでっかい画像のせておきます。やり方は人それぞれ工夫しながらやっていったらいい。
さて最近増えている「おひとりさま好き」と「孤立感」「孤独感」は同じではありません。
一人が好きは、単にテイストの問題。好みです。
孤立とか孤独は「他者とつながっている感覚を持てていないこと」です。
一人が好きで一人でいることが多いとしても他者とつながっている感覚が持てていればOK。
私たちは誰でも老いるし社会的な役割を手放すときが来ます。自分が何もできなくなる時が来るのです。
その時に他者とつながっている感覚が持てていれば「最後まで自分らしく生きたい」という気持ちが持てる。そのためにもやはり自分の世界を持っていることが望ましい。
一人暮らしだとか結婚していないとか、そういう人に対して「可哀そう」とか「寂しいでしょう」なんて言葉をかける方がおられるが、そういう発想をする人の方がよっぽど寂しいのです。
実家の母なんかはちゃんと自分の世界を持っていますから、そういう意味では一人で暮していても精神的な部分では安心していられる。
他者や何かを自分の拠り所とせず自分の足で立て、ということです。
そうでないと自分が何も役割が無くなって何もできなくなったときに自分を投げてしまう。
投げ捨てていい命は一つもないと私は思っています。
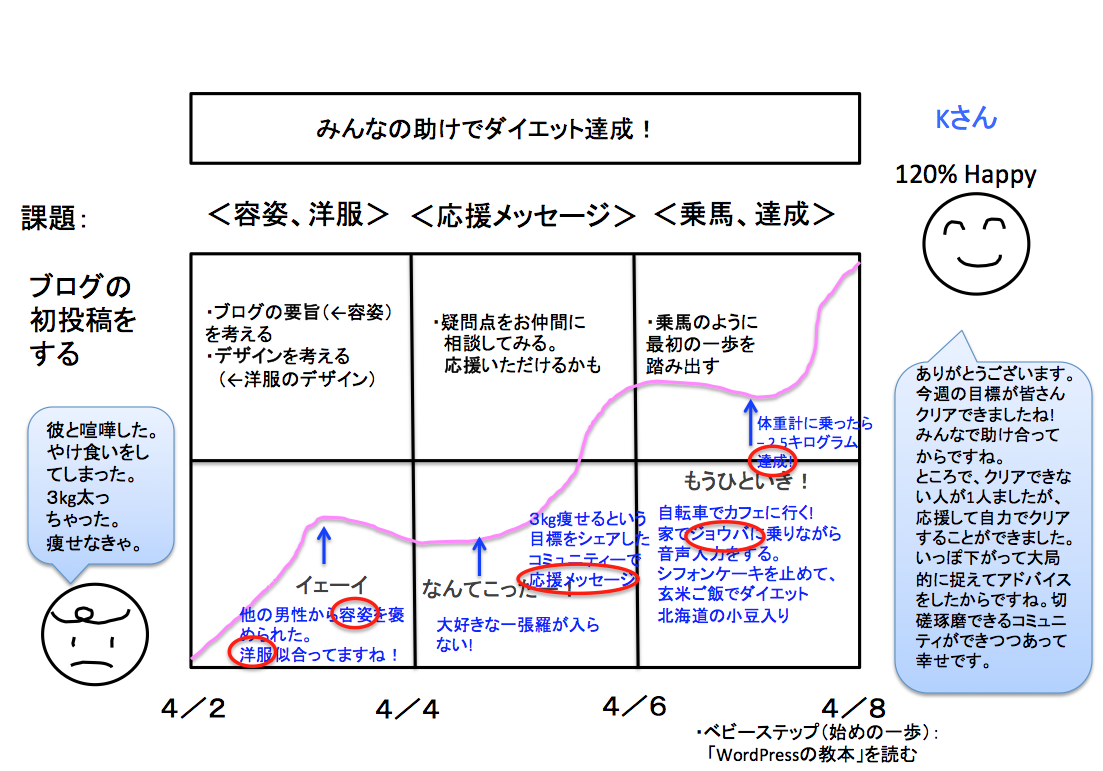
フューチャーマッピング
2022・創造性をフル活用ーこうなるといいなあの実現法
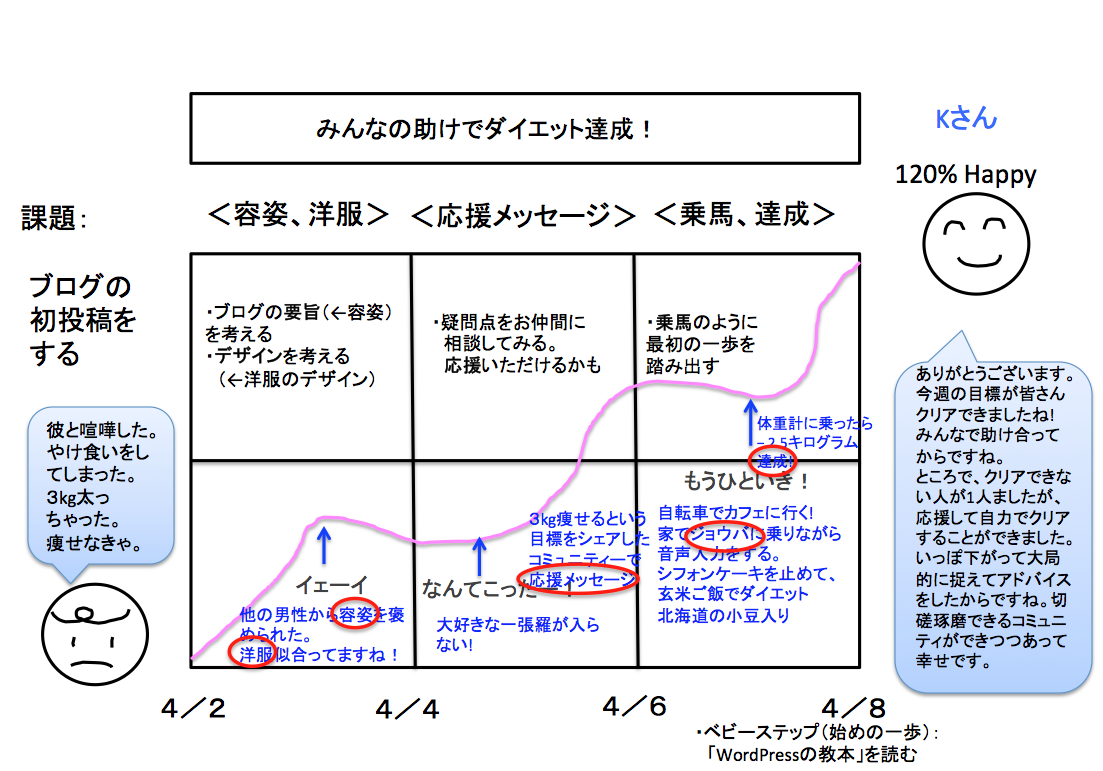
今年も始まりました。7時になりたい自分になる方法をメルマガで配信予定です。
アドラーでいうと自己決定性ー創造力の活用ということになります。
私の使っているのはフューチャーチャーマッピングという方法です。
だいたい実現したいことがあると、皆さんはゴールを設定したらそこへ向かって自分が一歩一歩階段を上がっていくイメージを持たれると思います。
それでいいのですが、1段1段の設定を具体的にどうするか、で悩まれるのではないでしょうか。1段の設定が低すぎるとゴールまでの階段は長すぎることになりますし、高過ぎると上がれないということになります。
フューチャーマッピングはゴールから現時点への1年後なりたい自分になるために、今年の12月にあなたはどんな気持ちで年の瀬を迎えたいのかを設定し、そのためには11月にはどうなっていたらいいのか、10月は?9月は?6月は?と逆に考えていきます。
最終的には現在から一週間の設定でのプラン作成になります。
そうすると一週間の細かい単位で具体的に何をどうすればいいのか、何ができそうかが自分の頭の中にクリアになります。
「~だったらいいなあ。」という漠然としたもので構わないので、創造力を膨らませてなりたい自分、こうであったらいいなあという自分をぜひ考えて見てくださいね。
何かを達成したいというものがある方には特にお勧めです。取り掛かりたいことがあるがなかなか手につかない方にもお勧めです。
1年後・半年後・一か月後・一週間後のゴール設定が明確になりますよ。
2021・総括
人生の課題に向き合う人々に勇気づけられた一年
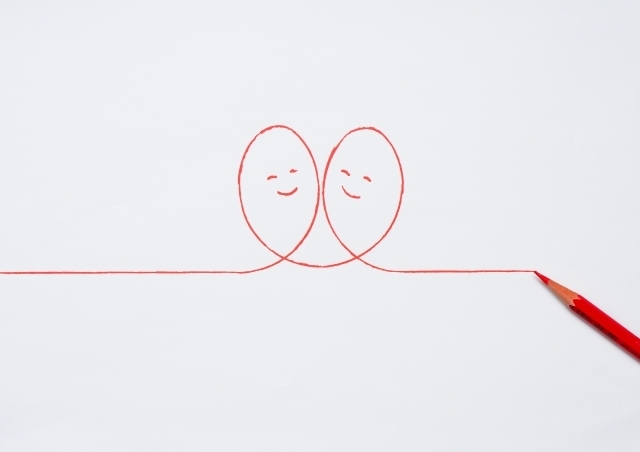
「落ち込んだことを含めいい一年でした。」大リーグAリーグでMVPを獲得した地元出身の大谷翔平選手の言葉です。
私自身もそんな感じかなと思っています。落ち込みはなかったかもしれない。
今年はコロナ過をうけてすべての講座をオンラインで開催してきました。仙台のみでやっていたときと同様、毎月20名~30名のご参加で年間300人ほどの方に関わらせていただきました。
共感をテーマにした一年でもありました。「相手の目で見て相手の耳で聞き相手の心で感じる。」です。
腹の立つことがあっても「多分相手はこう捉えているんだな、相手はこう聞いたんだな、相手はこういう気持ちでいるんだな。」そういう観点で起こった出来事や相手を見ることができれば相手を理解し、受容することは可能です。
来年以降もこのテーマは不変です。なぜなら「勇気づけとは共感的に関わること」ですから。
プライベートで言えば、1月に父が亡くなり、3月に姑が骨折・入院・施設を四か所転々と、その間母が何度か具合が悪くなり救急へ、姑の落ち着き先が決まり母の調子がいくらか良くなったと思ったら、新潟の叔父が死去・相続の手続きをすることになり、という感じで三年前からずっとこんな調子です。
それでもほとんど精神的に落ち込むこともへたることもなくやってこられたのは、やはり折々に関わって助けてくださった方たちのおかげでした。
講座でもプライベートでもそうですが、人生の課題に向き合う人々、手を差し伸べてくださる方々の姿は私自身とても勇気づけられました。
人はひとりではない。ひとりでは生きていけないのだということを実感させられた1年でもありました。
そういう得られることの多い一年でしたので、ありがたいという気持ちしか今はありません。
優しい穏やかな気持ちで今年最後の一日を迎えることができました。今年一年関わってくださった方々に「ありがとう」の言葉を送りたいと思っています。
そして自分にもありがとう、と言いたいです。
来年以降はコロナの状況を見ながらですが、仙台とオンラインの同時開催で相談会や講座を進めていくつもりです。プライベートでもまたたくさんの方々にお世話になることでしょう。
そういった中で感謝の気持ちをもって相手と対すること、自分に対することを大事にして行けたらいいなとそう感じています。
どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
心の不調・きっかけは「人間関係」

もう少し内閣府の調査について書いていくと、心の不調を訴えた人のきっかけも調べているんですが、複数回答で少々わかりにくいんだけれども、職場の人間関係をきっかけに心を病んでしまったという人が60%なんですよね。
他に身近な人間関係、直接職場に関係のない人間関係も含めるとかなりのパーセンテージを占めていて、私たちにとって人間関係がどうであるかがいかに大事かということがわかります。
自分だけはならない、みんなそう思っています。多分なってしまった人もそう思っていただろうと。
でもこればかりはわからない。これから先二人に一人が鬱という予測もある。メンタルを強くするというよりしなやかな発想・対応ができるようになっていることが望ましいと感じています。
アドラーを学んで、軽い鬱からすっかり脱却した方は結構いらっしゃいます。あとはやっぱりプラス自己受容とレジリエンス。
ありのままの自分を受け入れることができていて、しなやかな心の回復力を持っていること。
これできてると現時点では心の不調最強予防と言えると思います。
回答で気になったのは「もともと持った性格」って項目があって、それを選んだ人がいるんですけど、ありのままの自分を認めていたら「もともとの性格」で心病んだりしないと思うけどね。
この回答を見てもいかに自分を認めていない人が多いのかがわかるような気がしています。
「自分の世界を持つ」の勧め

先日ふれた「総務省」の新しいデーターっていうのは「全国の自治体職員のメンタルヘルス(心の健康)に関する初の大規模調査の結果」なんですが、それによると心を病んで1週間以上休んだ職員が2万1千人もいると、いうことが出てます。
この自治体職員の中には「教員・消防・警察」が含まれていませんで一般行政の方たちが対象とのこと。
全部含まれたらどれだけの数になるのか、民間を加えれば恐ろしい数値になることは容易に想像できますよね。
私たちって「すべきこと」「しなければならないこと」で人生のほとんどの時間を過ごしてしまいがちです。たとえば社会人としてとか、父として母としてとか、嫁として長男としてとか・・などの社会的役割から発生する事柄をこなすことで自分の人生のほとんどを送っているのではないかと考えます。
私はこれからの時代心の健康を保つには「すべきこと」と同時に「したいこと」の世界を個人が持った方がいいのではないかとそう考えています。
日本人には「やりたいことをやる=わがまま=悪いこと(罪悪感)」という図式がある。
これを「やりたいことをやる=自分を大事にする=良きこと(充足感)」という図式に変えたいものです。
ヨーロッパあたりだとまず「やりたいこと」があっての「やるべきこと」って考えが根底にあるような気がするんです。
日本人は休暇を「余暇」だと考えますけど、余暇ってすなわち「やるべきことをやって余った時間を好きなことに使う」って考えですよね。
ヨーロッパだと「まず休暇をあらかじめ決めて、その休暇に向けてやるべきこと(仕事)を頑張る」って逆の発想してます。
どっちにも長短あるんでしょうけど、私にはちょっと日本人は「がんばりすぎよね。」と感じられてならない。
もちろん子育て真っ最中であるとか、仕事を始めたばかりであるとか、頑張らなきゃいけない時期も人生にはあるわけですが、だからといって自分を大事に自分に優しくしなくていいということにはならないのではないか、そう感じてます。
アドラーあるある・配偶者が協力してくれないっ!

最近ご夫婦で受講して下さる方が増えてきたり、学んだことをご家族で共有して家族でアドラーのファンになってくださったりするご家庭もありとてもうれしいと感じています。
講座受講後はとても優しい気持ちになりますから、そういうお母さんを見たお子さんが「アドラー大好き」って言ってくださったりね。
でもほとんどはどちらか一人、やはりママさん(パパさん)の受講が多いのが現実です。そして「自分がせっかくアドラーを学んで勇気づけしているのに、主人が(妻が)子どもの勇気をくじいてしまう。」
アドラー実戦あるあるです。こういう悩みは誰もが直面すると思います。
でもね、これをやり続けるとたぶん配偶者はアドラー嫌いになってしまうんですよね。
なぜなら「協力してくれない」「一緒にやってくれない」と思った時点ですでに相手のことを評価していますから。いったん嫌いになったら二度と好きになってはくれないと思うんです。それはできれば避けたい。
それでこう考えて見ませんか?ってことをご提案しておきたいのですが。
「これって夫婦仲良くしなさいよ。」っていう自分の課題だって。
相手を自分と同じ方向向かせるとか評価するんじゃなくて「仲良くしよう」という方向に自分が向かえばいいんです。
ってことはお子さんに対してと同様に配偶者も勇気づけしていけばいいのです。
だいたいが「子どものことを思って・・」って視点で見れば夫婦間での目標の一致があるわけですから、わざわざ採用している方法が違うからと言って争う必要はないのですよね。
自分は自分の方法で、相手は相手の方法で子どものために良かれと思って・・なのですから。
そこが一致しているのに争うのはもったいないと思うんだよなあ。。どうせならアドラー好きになってほしいなとそんな風に思っています。
感情を味わい尽くす
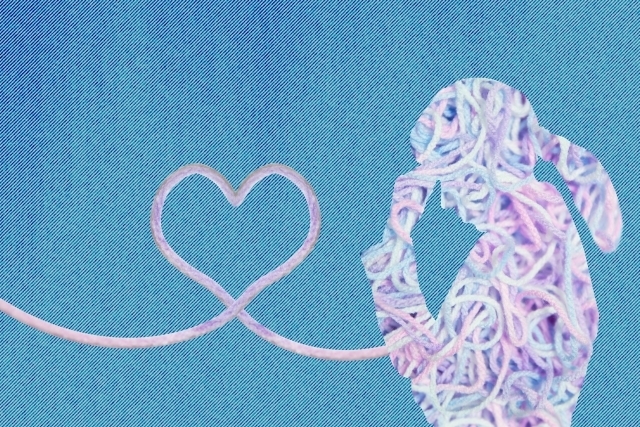
感情を子どもや他者に向けずに対処できるようになってきたら、今度は自分の感情と丁寧に向き合うことが必要になります。
そうでないと感情が押し込められたまま自分が苦しいと思う。
その時は一人になれる場所、一人になれる時間でやることが必要かなと思うんです。
丁寧に自分に問いかけていくといろんな感情が自分の中から出てくると思います。
不安だったんだな、寂しかったんだな、悲しかったんだね、辛かったんだな・・・。
そういう自分を評価しない(いやこう考えてはダメだとか、それはできないとか言わない)で「ああ、自分はそうだったのか。」と受け止めて味わい尽くすこと。
気持ちを押し込めてきた人ほど時間がかかると思うけど、最後の最後に自分って愛しいと感じるところまで行けば大丈夫だと思うのでそこまでやれればいい。
私はこの2~3年の出来事に向き合う時間が取れなかったので、今年の10月ぐらいからあらかた2か月自分と向き合う作業をしてきました。
内観に近いかもしれない。一般に普及している内観は親に対しての感謝であったり自分を取り巻く人への感謝を見つける作業ですが、私のいう内観は自分への感謝を見つける作業です。
自分が愛しいと感じられれば、前を向き先へ進むことができます。
感情がやっと動くようになったと感じています。感情の動かない方、多いんです。何をどうするかとか何を言うか、に囚われて、自分の気持ち・感情に向き合うことをしてきていない。
本当はそれが一番生きていく上で大事だと私は思うようになりました。それは自分を大事にしていること、愛している感覚を持てていることにつながると、そう思っています。
アドラー心理学とネフのセルフコンパッション

アドラーの子育て講座を受講すると、前半は子どもや他者にどうかかわるかといういわゆるテクニックの部分を学んでいきます。
そして最後に自分がそのテクニックを活かすにはどうあればいいのか、という人間的な在り方、土台の部分について学習していくことになります。
相互尊敬・相互信頼・貢献感・自己受容という土台があって初めてその技術が活かせるのです。
相互尊敬・相互信頼・貢献感については「自分の方からより尊敬し信頼し、他者のために貢献していこう」と自己決定すれば何とかなるかもしれないけれど、自己受容についてはどうしても自分を評価してしまってなかなかたどり着けない方が多いです。
自分を勇気づけられさえすればできるけれども、「できない自分」に勇気くじきをしてしまいがちです。
今年は幸いなことにネフのセルフコンパッションに出会ったので、どうしても自分にダメ出しをしてしまいがちな自分に厳しい方がきっと「自分って弱いところもダメなところもいいところも全部ひっくるめてOK」と思っていただけるようにしたいと思っています。
この時に必要なことがやっぱりアドラーの「不完全である勇気」と「完全になろうとする勇気」だろうと。
これがないとただの「自己肯定全開のしょ~もないやつ」になりかねません。
アドラーとセルフコンパッション、どうコラボしていくか、プランがまとまらないけれども、来年の私の課題です。
セルフコンパッションー自分にも他者に対するように少しでいいから思いやりを持ちましょうね、ってことです。
自分に優しくしてね、自分を大事にしてね、ご自愛くださいね、日本にはいろんな自分を思いやる表現があるんだけれども、実際にそれができているかというとかなりの疑問です。
ちょうど内閣府の調査で新しいデーターが出たばかり。自治体職員の60%が人間関係で心を病んでいるなんて見逃せない報告が出たばかりです。
年末年始ぐらい自分に優しくしてくださるといいなあと思います。
最初は「あ、みんな違うんだ。。」とわかればいい。

みんな同じだと思っていることが人間関係のトラブルの原因になることが多いのですが、みんな同じという思考の底には「だから自分が正しい」という信念があります。
誰かと会話していて「それ普通は~だよね。」なんて言葉を聞いたことは皆さんあると思うのです。
その普通はどこから来ているかというと自分のそう思う価値です。
アドラー実践者をアドレリアンと言いますが、アドレリアンでしたらこんな言い方をします。「それ私の考えだと~だと思うんですけどどうですか?」
人は同じ出来事に遭遇してもひとりひとり解釈が違うーこれをアドラー心理学の認知論というのですが、どう解釈するのかが人によって違うと知っていることが大事です。
同じ出来事を見れば皆が同じ解釈をすると考えると、「普通は~だよね」になりますが、違うことを前提とすれば「自分は~だと思うけど。」と言う言い方になります。
普通は~だよね、と考える人は相手が自分の考えることと違う行動をしたときに腹を立てたり不安になったり慌てたりします。
グループワークの時に「~という出来事についてどう考えましたか?」というワークをすると
10人いれば10人の解釈が出てきます。こうやって体験から「人は一人一人違うんだ。」ということを学んでいただきます。
自分が正しい、自分が絶対という考えは他者との関係を良くすることはありません。なぜなら相手は自分が否定されたと感じるからです。自分の定規でもって相手を計るのと変りません。
定規を当てて自分を評価する相手と仲良くしたい人はおられないだろうと思います。
自分の持っている価値や判断基準はあくまで自分一人のものと知っているだけでいいのです。
あなたが正しいわけでも相手が正しいわけでもありません。お互いの考えを聴きあい尊重して歩み寄るためにも「人は一人一人違うんだ。」ということを知って欲しいものです。
感情的になるな、論理的であれ!

片方、もしくは双方が感情的になったら物事は良い方向へ進むことはありません。
すでに「権力闘争」の段階に入ってしまっているのでね。
どちらかがアドラーを知っていて「同じ土俵に上がらない」「リングから降りる」ことを知っているとそれは避けられるのですが。
ご相談があったときには「争いたいですか?」「勝ちたいのですか?」とお聞きします。
争いたいとおっしゃるとか、勝ちたい、とおっしゃる方にこちらができることはありません。お好きにどうぞとしか言えないのです。
でも相談に来たということは「本当は争いたくない」「別に勝つことを望んでいるわけではない。」と考えている可能性も残っています。
その辺は丁寧にお聞きしていきます。
いずれにしても感情的になることは相手との距離を遠ざけます。プラスの感情は相手との距離を近づけますが、独りよがりな場合には逆の作用をすることもあります。
アドラーをやっていると論理的な思考が身につきます。感情で行動を起こすのではなく、論理的な筋道があって行動を起こすようになっていくのです。
なぜなら私たちは生きとし生けるものの中で唯一理性・思考を持った存在だからです。先の見通しや将来の創造ができるのも私たち人間だけです。
冷静に考えれば「争うこと」は「幸せをもたらすのかどうか?」は誰でもわかることです。
なぜ日本人は自分や他者にOK出せないのか?

仕事上内閣府や総務省の調査データーを参考にすることが多いんですけど、興味深いデーターがたくさん出ています。
今年はドイツ人に比べて日本人の自己肯定感が半分ぐらいのパーセンテージしかないというデーターが出てました。
同じように勤勉でまじめな国民性なのに、ドイツの人の半分ぐらいしか私たち日本人は自分や他者にOK出せてない。
自殺や鬱が多いはずよねとそう思う。なんでか?っていうとすごく簡単なこと。
日本には「ちゃんとやって当たり前」「もっと頑張れ、もっとやれるはずだ」の国民性があるから。
私はこれを変えていく必要があると思っていて、「(あなたが今どうであろうと)あなたはあなたでいいのよ。」とか「頑張ってるね。」って今の自分や他者を認めていく人間関係を作っていきたい。
欧米とか宗教がバックグラウンドにある国だと、これを子どものころから教会の教えとして子どもに伝えることができるが、日本ではそれがないので本当は学校でやれればいい。
「自分もあなたも今いるだけで価値があるんだ。」ということを。でも学歴・成績至上主義の今の学校じゃ現実問題として無理でしょうね。
これが自分の中に根付くと本当に「強くなれる」んだよね。しなやかで強い心をもって生きられる。
あなたは自分にOK出せてますか?
あなたはすでにグッド・イナフなんです。ってことを伝えていきたいなあ。
あなたが何者か?はそれほど大事ではない。

人間関係は「どんな人?」で
決まる
ある人に興味を持った時に「あの人って何してる人?」って聞きますか?
それとも「あの人はどんな人?」って聞きますか?
何している人って問いは「職業」が答えになりますよね。
「お医者さん」って答えが来たらそれだけでその人を信用するに足ると思ってしまう方結構おられます。
ご存じのようにお医者さんと言ってもひとそれぞれです。
他にも「学校の先生」だとか「弁護士」だとか、職業を聞いただけでまるのまんまその人をいい人だとか立派な人だとか思ってしまうことありませんか?
人間関係においては、この問いはあまり役に立ちません。
私はどうしても必要がある場合とか、先方に知らせておいた方が失礼にならないだろうと考えたときにしか自分の仕事を明かしません。
人によっては職業を聞いたとたんにガラッと態度を変えてしまう方がおられるからです。
人間関係で大事なのは「その人が何をしている人であるか」ということよりも「その人がどういう人か」の方が大事なのです。
あなたの大事な友達は「~という職業だから」大事なのではありません。優しさだったり誠実さだったりと「どういう人か」が大事だからこそ友達なのではありませんか?
お子さんに対しても「何者かになること」を強制していませんか?どういうお子さんに育ってほしいのかの方が大事ではないかといつも思います。
うちの受講生にもお医者さんだったり弁護士さんだったり学校の先生だったりいらっしゃいますが、講座を通して親しくなってから「え?お医者さん?」とか「え?弁護士さん」とか飲み会で判明することのほうが多いんですよね。
営業攻勢をかけられる

HPを見て営業をかけてくる
人それぞれ
近年営業をかけられることが増えているんですが、私に営業をかけてくる人たちはうちのHPを見て「ぜひうちと組みませんか?」みたいな感じです。
検索対策してあるので上位に表示されますから目に留まるんでしょうね。
要は受講生とうちの間に入って紹介を取り次ぎマージンを取るという会社からのオファーがほとんどです。
テレビだと「マイベストプロ」がありますが、メールで型通りの営業してくるのでいつもスルーしています。
電話をかけてくる営業さんはまだ本気度が高いですが、実際問題としてこれ以上受講生が増えるとキャパオーバーになるので「困っていませんので。」と丁寧にお断りすることが多いです。
そんな中でお一人とても感じのいい方がおられて一応お話だけでも聞こうかなと言う気になりました。
何がその営業さんが他の方と違うかと言うと、よくうちのHPを読んでうちの強みをちゃんと理解しておられる。
うちが他と違うのは「講座をやりっぱなしにしない。身につくまで徹底的にフォローする」ところです。
よく見ておられると感心してお話を聴く気になったのです。でも結局のところこれ以上仕事は受けられないのでお断りしましたが、相手のことをちゃんとわかっている営業さんに、仕事の基本を見せていただいたように感じます。提供される側が嬉しいと感じること、自分のことをちゃんと理解してくれていると感じること。
それは人間関係でも同じなのですよね。自分のことをわかってくれる人がいるってうれしいに決まっています。
突かれた・・やられたな・・そんな気持ちになったのでした。
同胞葛藤・兄弟間の争い(3)親としてできること

できるだけ兄弟間の差を
つくらないこと
兄弟葛藤は劣等感の大きさが現れる顕著な例です。
何人かの子どもがいて、一人だけがとても優秀な場合または、一人だけがほかの子どもよりポジション的に低い場合などに劣等感の増幅が起きます。
上の子どもがこのポジションに置かれると、自分が一番上なのに一番役立たずだと感じている可能性は高くなると思います。
親がこういった兄弟間の葛藤を避けるためにできることは、意識的にしろ無意識的にしろ兄弟の比較をしないこと、学歴やその兄弟に対する対応に本人たちがあまり差を感じさせないような工夫をすることが求められると思います。
とはいっても本人たちはどうしても兄弟間で自分で比較をしてしまいます。それは避けられませんので、自分がほかの兄弟より劣っていると感じていることが察せられるのであれば、その子の良きところに注目して積極的に勇気づけしたいものです。
「どうせ僕は。。。」と言い出したら「あなたは自分の良さがわからないのかもしれないが、お母さんにはちゃんとわかっているし、あなたはかけがえのない大事な子どもであるのよ。」と伝えたいものです。
失敗をとがめずチャレンジしたことを勇気づけることももちろん必要になります。
同胞葛藤・兄弟間の争い(2)カインとアベル

葛藤は避けられないのか?
同胞葛藤について最初の記述と言えば聖書の「カインとアベル」の物語ということになるでしょう。
カインとアベルは同胞葛藤の末に片方が片方を殺害するに至りました。
兄弟とはそういうものだという解釈になりますが、アドラー心理学で考えると、子どもが争うにしろ、それは本人の自己決定ということになりますし、どういう性格を形成するかも本人の自己決定です。
したがって、避けられないものであるとは考えません。これはとても希望を感じられる解釈ではないかと私は感じています。
おおむね今の自分の性格が嫌でたまらないという方は多いのですけれど、アドラー心理学の自己決定性から言えば、その性格を選択したのは自分ですし、家庭内に居場所を持つため、親に愛されるための戦略であったということになります。
今その自分の性格が嫌でたまらないというのであれば、いつでも自分で選択しなおすことができると考えます。
喧嘩をする、争いという方法で兄弟間の所属を満たすのではなく、話し合いで家族の中に所属するという選択をすることも可能なのです。
そのためにはモデルとなる親が争いで物事を解決することを示すのではなく、話し合いで物事を解決する姿勢・行動を示していかなければなりません。
同胞葛藤・兄弟間の争い(1)

生まれ来る命が葛藤を生む
兄弟間の争いを同胞葛藤と言います。
歳の近い男の子どうし、女の子どうしはもちろんですが、異性の兄弟間にも起こります。
「なぜうちはけんかばかり?」と考えてしまうかもしれませんが、原理は意外と簡単です。
親の愛を巡って子どもは争うのです。これがエスカレートすると大人になってからもその争いは続き、断絶・決別にいたることもあります。
「どちらが親から愛されているのか?」があるからです。
親の愛を巡っての戦いが同胞葛藤です。
勝っていると感じているほうはその地位を失わないように努力しますし、負けていると感じているほうは勝っているほうを理由なく憎んだりします。
親が弟をひいきしているのであれば、本来ひいきしている親を憎みそうなものですが、そうではありません。弟を憎みます。そのあたりは恋愛に似ているかもしれません。
それほど子どもにとっては親の愛を得ることはいきるために必要な重大事なのです。
ギークの時代
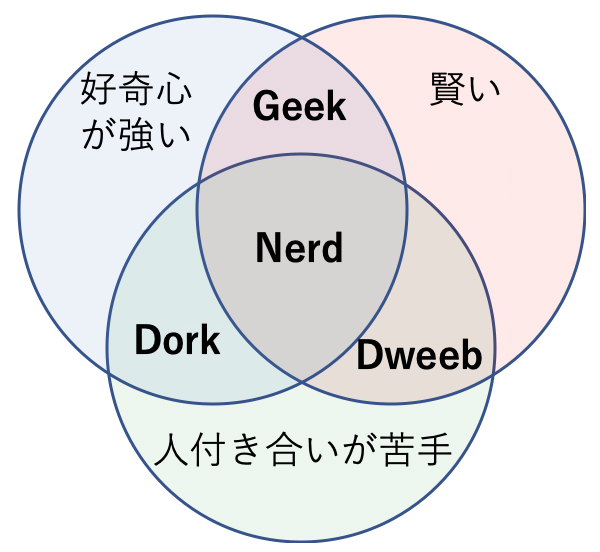
ギークとは人間関係も構築でき
社会に適応できるオタクである。
先日ある精神科医の「遊び方講座」を受講した折にギークという言葉を知りました。
これからはギークの時代だそうです。確かに何かを徹底的に追及する人が成功する例が多々あります。
周りからどう思われようと関係なく、自分がこれだと思ったものを追求していくうちに高みにたどり着いていたという感じなのでしょう。
日本語だと「オタク」ということになりますが、日本でいうオタクは内にこもり陰気な印象があります。
ギークと言われる人は専門性と人間性を併せ持った分類であることが図からもわかります。
人としてのバランスもとれている、しかもオタクである、そんな若者が増えていくのかもしれません。
今学校に適応できない、会社に適応できないではじかれている人たちは、世の中が他者との違いを認める寛容な世界になればギークになれるのかもしれないとそんな風に感じています。
仙台会場再開のお知らせ

気持ちがいいと感じる
方法を使いましょう。
コロナで長らくご不便をおかけしていましたが、仙台会場を年明け1月から再開します。
密を避けるため大きめの会場で定員は10名とさせていただきます。
メルマガで告知しましたところすでに残り座席3名様となっております。
久しぶりに体面でお顔を見られるのはとてもうれしく感じています。
身近な人たちがコロナですっかり出不精になってしまっている傾向があるので、また元気なお顔をたくさん見られるといいなあと、そんな風に思っています。
当面は「子育て・人間関係の相談会」のみの開催として、1月はランチ(
も予定しています。
どうぞリアルを楽しみたい方いらしてくださいね。
自分を好きになる方法

気持ちがいいと感じる
方法を使いましょう。
自分を好きになる方法を探しておられる方は結構おられるようです。
アドラー心理学でいうと自分を勇気づけることとなりますが、要は自分がしたり言ったりしたことで嫌な気持ちにならない方法を使うということです。
自分が嫌な気持ちになったとすればその方法は自分を好きになるのに役に立ちません。
誰かに何かを言われて嫌な気持ちになったとしても、それは相手のせいではありません。
相手の言ったことの意味づけを変えたり相手の良き意図を見つけたり相手を理解しようとすれば解決できるものです。
自分がしたことや言ったことで嫌な気持ちになったのだとすれば自分が行動・言い方を変えることで対応していけばいいのです。
嫌な気持ちにならない工夫は誰でもできます。ただ教えてもらわないとわからないことです。なぜなら学校も親も友達も誰も教えてくれないからです。
アドラー心理学の実践とはそういうことです。自分や他者との関係で嫌な気持ちにならない方法を学ぶということです。それが自分が好きになることにつながっていきます。
人間関係は仕事ではない

評価をしてしまいがち
私たちは生まれたときから「評価」にさらされて生きてきました。
生まれればほかの子と比べてどうか、親の期待からするとどうか、学校の先生の基準からすればどうか、といった具合です。
他者の物差しで測られ、いいとか悪いとか、正しいとか間違っているとか評価され続けています。
でもこれを人間関係に持ち込むとうまく行きません。
誰も相手の物差しで「あなたは間違っていますよ。」とは言われたくないのです。あなたは私の期待には届いていません、あなたは私とは違うのでダメです、も同様です。
相手の物差しで測られる人生は辛いものです。あなたはあなたの基準で生きていいのです。
あなたが間違っているのではなく、その方法が間違っているとはいえることもあると思います。
評価は「行動」のみに言及し、くれぐれも相手の存在自体に及ばないように気をつけたいものです。
これはあらゆる人間関係の基本です。
・悩んでいる問題の解決方法・2

課題分けで考えて見る
相手がどういう行動をするか、どういう言葉を発するか、は誰の課題かというと相手の課題です。
そしてその相手の行動をどうとらえるのかはあなたの課題です。
すなわちもし相手の行動に「頭にきた」としたら、頭にきたのは、相手の課題ではなくあなたの課題なのです。
その際に大事なのはなぜあなたが怒りを感じたかを丁寧に見てみることです。
そこにはあなたの大事にしている価値観や「~すべき」という思考があると思います。
怒っては駄目というわけではありませんが、あまり二者間にはいい影響がないので、相手に向けない習慣を構築したいのものです。
言葉で伝えるという方法ですが、そのためには自分が何をわかってほしかったのかを明確にする必要があります。そうでないといつまでもわかってもらえないということになります。
・悩んでいる問題の解決方法・1

悩みの解決は相手を変えることではない、自分の捉え方を変えること
子育てにしろ、人間関係にしろ、悩んでいるときは「相手をどうにかして変えようとする」から悩んでいるんですよね。
今の相手がダメだから、今の相手が不十分だからと言って、相手にOKになってもらえたり、相手に十分になってもらったりしてほしいわけです。
このOKや十分は誰が基準のOKか、だれが基準の十分かというと、あなたが基準なわけです。
だから自分が満足するまで相手に変わってほしいと思っています。ところがこれは実際やろうとするととても大変なことです。
相手がそうしたいと思っているならまだ可能性がありますが、相手が望んでいない場合はほぼ無理です。
なので悩みの解決はどうすることが現実的で効果的かというと、相手の問題と捉えていたことを「自分事」にしてしまうことです。自分のことなら解決できます。
その辺はもう少し詳しく書いていきたいと思います。
不機嫌も機嫌も伝染する

TPOをわきまえられない
大人もいる
昨日たまたま夕方テレビをつけていて、大相撲の中継を見ていました。
ある力士をめぐって解説者がふがいないと言って怒ってしまい、アナウンサーがそれをなんとかなだめようとしていました。
「怒ってしまって不機嫌をあらわにしたら解説にならんじゃないの。」と思いました。その辺の立ち話をしてるんじゃなくて、公共の電波を使って不特定多数の人に聞かせることじゃないと感じ、とても不愉快に感じました。
普段の生活でもこんな感じで「この世は我が世」とばかりにやっているのかもしれず、それに対して誰も何も言えないのかもしれませんね。
聞いていると不機嫌が伝染しそうな気がしたので、画面から目をそらしました。いわゆる業界では大御所なんでしょうが、某放送でも大御所と称する人が誰彼にかまわず言いたい放題で、その番組も見るのを止めました。
決めつけのひどいものは聞いていてとても不愉快になりますね。何の権利があって本人をぼこぼこにするのか聞いてみたいものです。
我慢は美徳?負けは弱虫?

人生は楽しむもの・・
そういう発想に変えていきたい
実家の母と付き合っていると「我慢は美徳」であったり
「弱いのはダメ」と思っていたりする節があります。
毎日私たち兄弟は順番に夕方安否確認の電話を母にすることになっていますが、昨日は私の担当日で、エアコンの話になりました。
昨日はすごく蒸し暑い日で、黙って座っていても汗が流れ出てくるような日でした。
エアコンをつけているかどうか聞いたところ、窓を開けているからつけないと言います。
何をしていたかと聞くと「暑くてだるくて何もしないでいた。」と言います。エアコンをつけて快適な温度にすれば、何かやろうという気持ちになるかもしれないのにと思いました。
高齢者はそうでなくても暑さや寒さに鈍感になります。気が付いたら熱中症になっていたなんてことがあるらしいので、つける様に言いました。
こういう我慢は必要なのか?と思います。暑さに負けてエアコンをつけることは自分の弱さでそれは認められないとでも言いたげです。
こういう考えは必要なんだろうか?役に立つんだろうか?と思います。
エアコンつけないで我慢するのは母の自由だけれど、もし具合が悪くなったら、自分が辛い思いをするし、私たちも困るのです。誰にもいいことがありません。
これも一つの「協力」と言えるのではないかしらと思います。自分一人の考えに固執することはあまりいい方向へ行かないように感じています。
我慢は美徳であるとか、弱さは負けであるとか・・・という価値観から、人生は楽しむものという発想に変えていくのはこれからの時代に必要なことかもしれません。
ブームとは・・仕掛けがあって起きる

ブームとは
誰かによって仕掛けられるもの
最近いつも行くスーパーで「オートミールの特設コーナー」ができました。
昨日も同じお店へ行きましたら、今度は書店で「大人の塗り絵コーナー」が新設されていました。
誰かが仕掛けたなと思いました。テレビで取り上げたりするとあっという間にブームが起きます。
私が大学生のころって仙台の名物は「笹かまぼこ」と「牡蠣」しかなかったのですが、いつの間にか「牛タン」やら「ずんだ」やらが出てきました。
これも狙って仕掛けたから今名物になって定着しているのです。このようにブームとは誰かや何かをきっかけに、もしくは最初から狙って起きたり起こしたりするものです。
アドラーのブームと言えば「嫌われる勇気」ですよね。あれも仕掛けとしては最高だったのではないかと思います。
別に岸見先生が仕掛けようとしたわけではないでしょうが、出版社側は「売れる」という仕掛けをしていくのが仕事ですから、あれをきっかけにブームになったんです。
でもいまだに売れ続けているってすごいことです。本の力を感じます。
うちはあんまりブームに関係なくて、ブームだからと学びに来た人は少なかったし、今もそうです。そのほうが助かるんですよね。ブームだからって飛びついた人にアドラーは続けられないことが多い。根っこに厳しさがあるからね。
困って、何とかしたくて・・・じゃないと人は必死にならないからね。
対人支援職あるある・・

資格はある・・・
でも・・
「人は自分のことはわからない」とはよく言われることですが、いわゆる対人支援職、カウンセラーであるとかセラピストであるとかを生業にしている方で、資格は持っているが・・全然活かせない方はたくさんおられます。
昨日もSNSである方とやり取りしていて「あ~あるあるだね。」と言って笑ったんだけど、まったく「共感力」がない。
頭ではラポールの形成(信頼関係の構築)が大事ですよとか、共感で相手に対しましょうとかわかってるんでしょうけど、実際にはできていない方が多いです。
これがないと対人支援はやれません。
共感力を磨くことが信頼関係の構築につながる。そのためには徹底的に相手の立場に立って考えられることができるようになることが必要です。
あなたは今~な気持ちではありませんか?ぐらいなことが相手に確かめなくてもわかるようになることが必要です。
もちろん違っていることもあるので実際の現場では必ず相手に確認しますが。そうするとほぼほぼあっていることが多くなっていくはずです。
私がアドラーをやって一番難しくて苦労してやっとできるようになったことがこの共感ということでした。
資格はある、だからその資格を信じてクライアントが来るのですが、あまりにも共感とは程遠い対応をされるとびっくりだね‥なんて話をして笑いました。
資格があること、試験を受けて資格を取っていること、自分がそれでずっとやってきたから、でできていると勘違いしている向きもあります。
試験に合格したから、やれているからと言って共感ということができているわけではないことは人の支援に関わるなら肝に銘じておきたいものです。
ちなみにアドラー心理学の「勇気づけ」は共感的に他者と関わることです。ですから「共感力」のない人は勇気づけもできないということになります。
値段の問題ではない

日本品質絶対主義から
離脱するときが来たか・・
最近仕事はほぼサブのパソコンでこなしています。
オンラインの講座はオフィスの関係上メインのパソコンを使っていますが、このメインパソコン、サブの3倍の値段なのに、不具合が多くて使いにくいと感じています。
まだ3年しか使っていないのに、オンラインのZ00Mと相性がとても悪いうえに、すでにアルファベットのWが反応しない時があります。
ZOOMとの相性の悪さはうちだけではなく、あっちこっちで起こっているようです。
日本製だからと言って大丈夫とは言えない、安心していられないのよね。サブは海外のメーカーですが、サクサクと動きますからついサブに向かって仕事をすることになります。
値段や日本製であるとかが購入の基準にならなくなってきました。ユーザーが使いにくいと感じれば、高かろうと低かろうと価値は下がります。
講座もそうなんだけど、高かろう悪かろう、って結構あるようです。大枚はたいたのにさっぱり??だわ、というのは多い。
講座をやっているところってビジネスシステムに組み込まれるのは当たり前なので、それは自分で選択すればいいが、ビジネスシステムだとわからないで入ってしまった人が大枚をはたき続けて最後に気が付くみたいなのはよく見かけます。大枚はたいていい勉強したと思えばいい。人は痛い思いをしないと儲けの仕組みに気が付かなかったりするもんだからね。
安かろうが良かろう、がうちの講座って言えばいいか。(笑)さっぱり私は儲ける気がないので。
おかげさまでそこそこやれていて困らない程度に収入になればいいと思ってやってます。
発達障害とHSPについて思うこと

欠点として捉えず
特性として活かすことが大事
発達障害・ADHDであるとか、HSPであるとかということを自分や家族、子どもの欠点であるかのようにとらえている方は多いようにお見受けします。
発達障害については、お子さんがそうだと言ってご心配で親御さんが来られますが、アドラー育児を学んで実践していただくとほとんど気にならなくなり問題として捉えなくなります。
アドラー育児をやっていただくことで、そのお子さんの傾向が関係性を改善することでなくなるもの、それでも特性として残るものがはっきりします。
発達障害の症状にしても、HSPにしても、他の人と同じことをやろうとするとできないとか大変だとかということになるかもしれませんが、特性を活かしてほかの人と別のことをやればいいと考えれば才能になります。
そういう意味で相手の適切を見ていくアドラー育児や対人関係法は、発達障害やHSPnと言われるもののプラスの側面に注目していきますし、個人一人一人の良さや能力を伸ばすという点ではとても優れた方法であると感じています。
「うちの子、発達障害で。。」とか「実はわたし、HSPで。。」と言われたら「あら、他の人にない素晴らしい才能をお持ちなのね。」と答えたいと思っています。
システムで家族を見てみるーシステム論

システムの不具合を見るのが
家族療法
この間オンラインで夜に臨床されている方たちの事例検討会がありました。
6回シリーズで昨年一回目を受けたんですが、その後コロナで受講できなくなり、今年に入ってオンラインで再度やるというのでやっと続きに参加できました。
アドラー派のカウンセリング技法一つがおまけでつきますので、とてもお得な講座です。
その中で臨床で子どもの問題についてどうするか、といろいろ事例が出たんですが、システム論の話も出ました。
家族を一つのシステムと見立てて、システムの不具合が子どもの体の症状だったり、不適切な行動に出るという考え方です。
考え方としてはありだけど、現実問題として家族療法・家族全員そろってカウンセリングってのは難しいでしょうね。
自分が臨床重ねていると、子どもの不適切な行動や子どもの病的と言われる症状も、母親を中心として親が変わると親自身がそのことに注目しなくなるので(気にならなくなる)、自然に減っていくっていうのはよくあるんですよね。
安易に心療内科などの病院へ、投薬治療へ、の前にアドラーの子育てを試してもらいたいもんだと感じています。
お酒は飲むもので飲まれるものではないー飲まれるようになったら病気です。
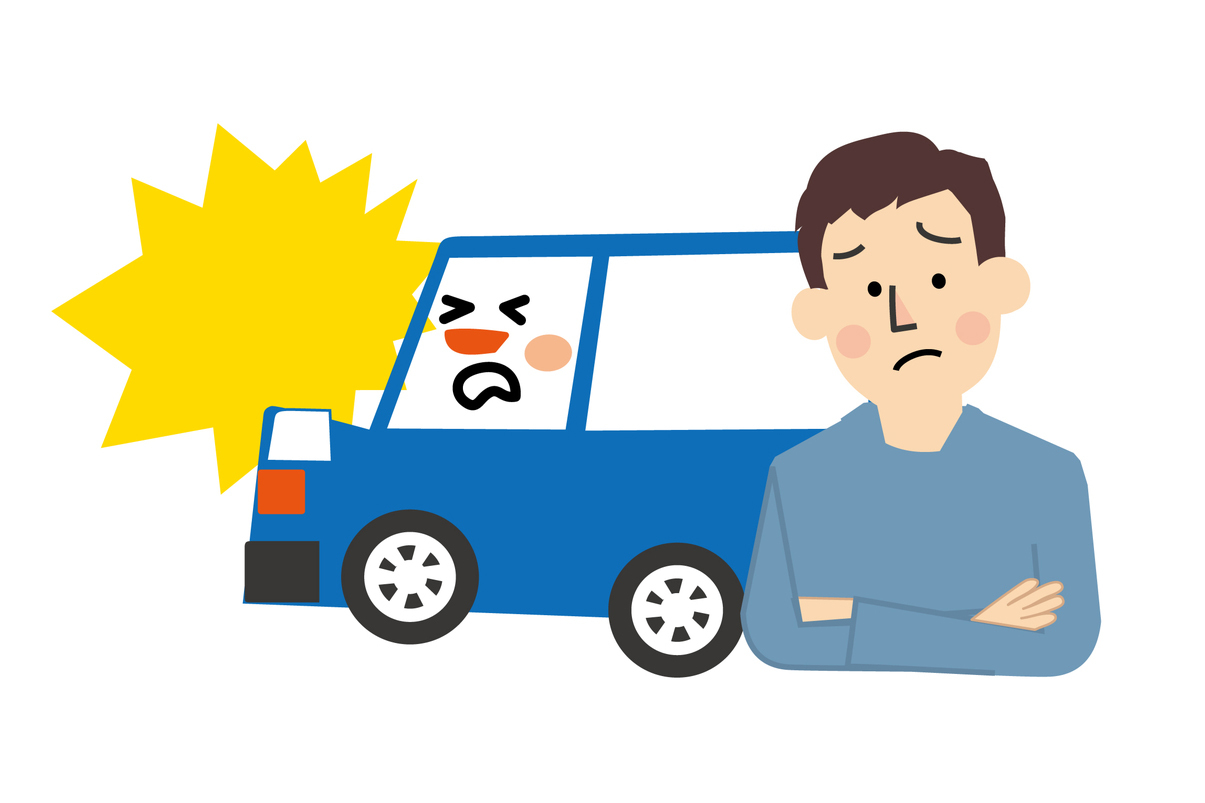
飲んだらダメな時に
飲むのはすでに病気
千葉で飲酒運転による痛ましい事故が起きましたね。
飲酒運転や酒気帯び運転の事故が起きると、たとえば公務員だったりすると所属長が「職場で再度規律について皆で周知しあう。」みたいな謝罪会見をしますが、それって意味ないと思う。
飲んだらダメな時に飲むのはもう病気です。アルコールのコントロールが自分でできなくなっているのですから意志の力でどうにかなるものではありません。
アドラー心理学では「飲酒」の「目的」を考えるんだけれど、目的が「現実逃避」だったりすると変えられるもの変えられないものが出てきますし、
他のことで現実逃避できればいいんだけれども、安易にお酒で現実の憂さ晴らしをする習慣のある人は易きに流される傾向があるのでお酒を断つのはなかなか難しいんですよね。
だからまず病院へ、というのが現在では最初の選択肢になると思います。とはいっても薬が中心の治療ですし、今のところ決定的な治療法があるわけではありません。
薬でお酒への欲求を押さえたうえでどうする?って話になる。周りが何を言ってもダメですしね。
断酒会ってグループ療法が主ですけど、実際どれほどの効果があるのか疑問ですが、「一人ではない」感覚を持ってもらうことが狙いだとすると、それってアドラーでいうところの「所属感」ですから、自分は役に立っているし所属できている感があれば、破壊的な方向へは行かないかもしれないね。
田舎ってところは飲酒についてとても甘々。しかも不便だから車生活。
まあ我が家も母屋もお酒の問題は大きかったから余計関心があると言えるのですけど。。
お酒は飲むもので飲まれるものではない。飲まれるようになったらもうボーダー越えてますよ、ってことは言えるんだろうと思っています。
「気にしすぎ」「心配しすぎ」を何とかしたい・3

distructionーすべきことから
目を背けない
今日は「気にしすぎ」「心配しすぎ」な人への第3回目の投稿です。
心配の種がわかっているのに、それにあえて目を向けずに気をそらす方向へ進んでいる。
マイナスのdistructionしているかどうか?がカギになります。
試験が近づいていて勉強しなければならない、勉強することで不安や心配は解消するにもかかわらず、あえてそれから逃避して、今の楽しいことを追いかけて、勉強のことを考えないようにする、と言った対処の状態です。
この場合には、明らかに不安や心配は解消されませんので長引きます。取り組めない、行動に移せない理由があればそれを考えます。
自分一人では対処できないと感じていたり、できそうもないと感じていたりすれば、身近な他者に助けを求めればいいのです。
そうして取り組むべきことに勇気をもって取り組むことができれば、不安や心配からは解放されると思います。
ただこれは自分のことに限ることは言うまでもありません。
子どもが勉強しないからと言って子どもの問題を親が解決することはできません。声をかけたり、必要なことがあれば(本人からの希望があれば)手を差し出すぐらいのことしかできません。
親が自分の問題でない子どものことで不安や心配をしてそれを増幅させることは、あまり両者にとって建設的ではないと言えます。
「気にしすぎ」「心配しすぎ」を何とかしたい・2

クヨクヨ考えて「不安・心配」に
かられがちな人
今日は「気にしすぎ」「心配しすぎ」な人への第2回目の投稿です。
役に立たない、要は考えても仕方がない、どうしようもないことを気にしすぎる人への対処法2つ目です。
一つ目は「行動に結びつかないこういう感情はあまり役に立たないんだ」と自覚することでした。
アドラー心理学ではもう一声「続けますか?やめますか?」と相手に自己決定してもらうという段階があります。
「やめたい」なら「やめる」と自分で決めてもらうのです。その際に使える方法があります。
今日は「またいつものように考えても仕方がないことを考え始めたな。」と気が付いたら使える方法です。
それは目の前のことに集中すること、言い換えると「今ここ」に生きること。アドラー心理学でも確か「嫌われる勇気」に出てきますね。
そうすると今のことに集中してやっているとすっかり忘れてしまいます。こういう集中力というのは、マインドフルネスとか最近は言われますけど、「これねえ、やってるとすっかり時間を忘れちゃうのよ。夢中になってしまって。。」ということがある、もしくは経験があるのであれば、だれでもできると思います。
それじゃ寝ているときにこの不安に駆られてしまったらどうするか、おなかに手を当てて呼吸に集中しましょう。
息を吐くたびにおなかが引っ込んだり膨らんだり、口や鼻を通る息を感じることに意識を向けていきます。
これもトレーニングでできるようになってきます。この方法は特に寝つきの悪い方、お勧めです。できるようになると短時間で眠りに落ちていけるようになります。
「気にしすぎ」「心配しすぎ」を何とかしたい・1

クヨクヨ考えて「不安・心配」に
かられがちな人
あれこれ気にしすぎて、心配しすぎて気疲れしちゃう。
そんな方へ気にしすぎない方法、心配しすぎない方法を3回にわたって書いてみたいと思います。
これってノルウェーのどっかの大学で研究されて論文が出てるみたいですが、アドラーの考え方とマッチするなあと感じています。
今日はまず1つ目です。
アドラーを勉強している人の判断軸は「役に立つのか立たないのか?」ですよね。
気にしすぎや心配しすぎは不安という感情を伴って増幅するんですけど、まずその不安は「行動によって解消できるかどうか」を考えて見ましょう。
行動に結びつくことで解消される「不安」「気がかり」「心配」はとても役に立つ感情です。
たとえば天気予報を見ていて「大荒れになるから避難の準備をしよう」と考えてする。これだと大荒れの天気に対して「準備」という行動に結びつくのでとても役に立つ感情になります。
役に立たない「不安」は、行動に結びつかない場合です。これはどうしようもないので、考え続けても増幅するだけだということです。
不安を増幅させても解決に結びつきませんから役に立たない感情ということになります。
「あれ?なんか悪いこと言っちゃったかな。嫌われたかも。。」と不安になったところで、過去には戻れませんから、次にどうするかを考えたほうがよほど建設的だと言えます。
このように「気にしすぎ」「心配」そして「不安」は、役に立つ場合と役に立たない場合があるんだということをわかっておきましょう。あなたの「気にしすぎ」はどちらでしょうか?
子どもの困った質問にどう答えるか?

子どもは質問をする天才
昨日のメルマガで兄弟間の劣等感について書きました。
親にそのつもりがなくても、子どもは親をめぐってどうしても自分の方が愛されているということを確認したくなるのです。
「お兄ちゃんと私とどっちが好き?」
こんなビッグクエスチョンは良くお聞きしますが、なんて答えたらいいでしょう?
「どっちも好きだよ。」で納得してくれればいいのですが、そうもいかないかもしれません。
困った質問には「逆質問」という方法があります。
「それじゃ君はお兄ちゃんが好き?」「うん、好きだよ。」「そっか、お兄ちゃんが好きなのは素敵なことだね。」
「いいえ、嫌い。」「「おや?どうして?教えてくれない?」「あのね、~だから。。」
「そっか、~なところは嫌か。。好きなところはある?」
子どもの質問にどう答えるかを考えるより、子どもがどう考えているか聞いてしまいましょう。
人は思い込みの世界に生きているー認知論

あれ?なんか変??
アドラーの認知論を知っていると「本当に人って思い込みの世界に生きているんだな。」と思うことが多々あります。
以前ボランティアの資金稼ぎに漬物屋さんでアルバイトをしていました。
そのころにご近所のご主人が「直子ちゃん野沢菜あげるよ。」と言ってくださったのですが「漬けたのがいい?自分で漬ける?」と聞かれたので「自分で漬けられないので漬けたのが欲しいです。」と言いましたら「え?漬物屋さんに勤めてるのに?」と言われました。
漬物屋さんに勤めてるんだから漬物を漬けられるだろう・・ですね。(笑)
こういう話はたくさんあって、英語の先生だから英語に関することは何でも知っているだろうとか、英語をぺらぺら話せるだろうとか。。
田舎あるあるだと、学校の先生なんだから立派な人だろうとか、お医者さんだから人格優れた人だろうとか。。
大学出てるんだから頭が良くて賢いだろうとか、です。
人は人です。その人が何をしているかとか立場がどうだとかということとその人がどういう人かは全く別の問題です。そうすると、思い込みで~だと思っていることが多いほど理想や期待があるので失望したりも多くなります。
人は人だよ・・・と、親であろうとなんであろうと。。。そう思うようになり相手に思い込みによる期待や理想を抱かなくなってくると失望したりがっかりして相手を嫌いになったりも少なくなるんじゃないかなと、そんな風に思います。
相手不在の一方的なコミュニケーション

相手不在・・
この世の中は自分が中心
コミュニケーションというのは、基本的に自分と相手とのキャッチボールだと思うんですが、相手の話を聞かない、耳をかさない、一方的に自分の主張だけをしてくる、高齢者とお話をしていると特にそういう場面に遭遇します。
いわゆるマシンガントークというものです。ご近所さんはほぼ高齢者ばかりですから、そういうのは日常茶飯事で、はいはいと言ってお話を聞く側に徹します。
身近なお付き合いをしなければならない相手なので自分から関係を悪くすることはありません。
とにかく一方的なのです。昨日も姑のお友達という方からお電話がありましたが、同じ調子で聞きたいことだけ聞いて言いたいことだけ言って一方的に電話が切れました。
日曜日には主人の叔父が来て同様に一方的にしゃべりまくって帰っていきました。私はちょうどオンライン中でしたので出ませんで済みましたが、主人は結局付き合わざるをえなくなり相手をしておりました。
「よく相手できるわね。」と言いましたら「俺だって早く帰ってくれないかなと思っている。」と正直な胸の内を話してくれました。
相手は目の前にいるが目に入っていない状態と言えばいいかしら?それでいて黙って聞いていると「なんで返事をしない?」となることもあります。
返事したくてもできないよね、そんなにグイグイ自分の主張だけされたら。。
そういえば勉強会でも「私の意見を言っても結局自分の思うとおりにするんだから意見を言っても無駄」と感じて黙ってしまう・・なんていうお話も出ました。
相手の意見に耳を傾けず自分の主張を譲らない。最初から「自分が正しい」ありきの人とお話をしたいとは誰も思いません。
関わらなくて済む大人同士であれば「相手にしない」「関わらない」そういう対処もあっていいと思います。また高齢者すべてがそうだというわけでもありません。
きちんと相手を見て言葉のキャッチボールをしながらお話しできる・・・基本的なことができる方もおられます。ただ残念だけれど自分の身近で考えると圧倒的に少数派です。
「聞き方」にしても「話し方」にしてもこういうトレーニングは大事なことだなと感じています。
アドラーの対人関係法はまず「自分が話すことよりも相手の話を聞く」ことが優先なので、こういう方には「話したいことを我慢してもらう」が最初のステップになります。
まあそうしたいかどうか、は本人の選択になります。私は自分と関係のない方でしたら付き合わない、関わらないようにしますけどね。
算数的に解くか?数学的に解くか?

別のアプローチがある
別の視点があるから面白い・・
メルマガで取り上げた算数の計算
二つの考え方を書いておきますね。
問題は6÷2(1+2)でした。
まるでELMの最初のワークをやっているような感じではあります。
「算数的な考え方」
2(1+2)の2と()の間に×が省略されていると考えます。
そうすると6÷2×(1+2)となりますから、割り算と掛け算の混合算の場合には前から順に解くということで6÷2×3で答えは9になります。
「数学的な考え方」
2(1+2)を一つのまとまりと考えます。そうするとこの部分はまとめ計算すると6になります。したがって6÷6ということになり、答えは1になります。文字式の応用になるんですよね。
メルマガでも書きましたけど、この問題の答えをめぐって大論争になったのですが、算数的に解きましょう。文字式を例にして数学的に解きましょうという最初の定義がないので、どちらも正解と言わざるを得ません。
最初の定義・前提が合わないものを論争しても答えは出ない。ただ争いが起きるだけ、ということになるでしょう。
これは子育てや人間関係にも通じますね。「仲良くするとする。。」という前提と「争って勝つ」という前提では、その先は全く違ったものになるのですから。。
決めたら行動するーそれが自信につながる

一度決めたらやってみる・・
自信のない方というのは、考えてばかりおられる。考えているんだけれど行動しない。行動しないから変わらない。変わらないからいつまでも自信が持てない。
こういう悪循環に陥っています。
もしかしたら行動してもだめかもしれない。ダメな時に傷つかないように行動しないことにしよう。
そう考えておられるかもしれません。
でも行動したこと自体に意味があるのです。現実を変えようとして一歩踏み出したことに意味がある。自分には行動する能力があるんだと。
一回行動できたんだから次もできるかもしれない。やってみよう。う言うことの繰り返しが自信の積み重ねになります。一度のチャレンジがあなたの人生を変えることもあるんだと思います。
人間関係も一緒です。うまく行かなかったときに傷つかないようにしよう、と考えれば付き合うこと自体を止めてしまいます。
こういう時私たちは精神的にあまり健康でない思考に陥っているとアドラー心理学では考えます。勇気が持てていないのです。
実際のところ、アクションを起こしてみればわかりますが、他者はそんなに悪者ばかりではないし、おおむね好意的で優しいのです。
現実という結果を引き受ける
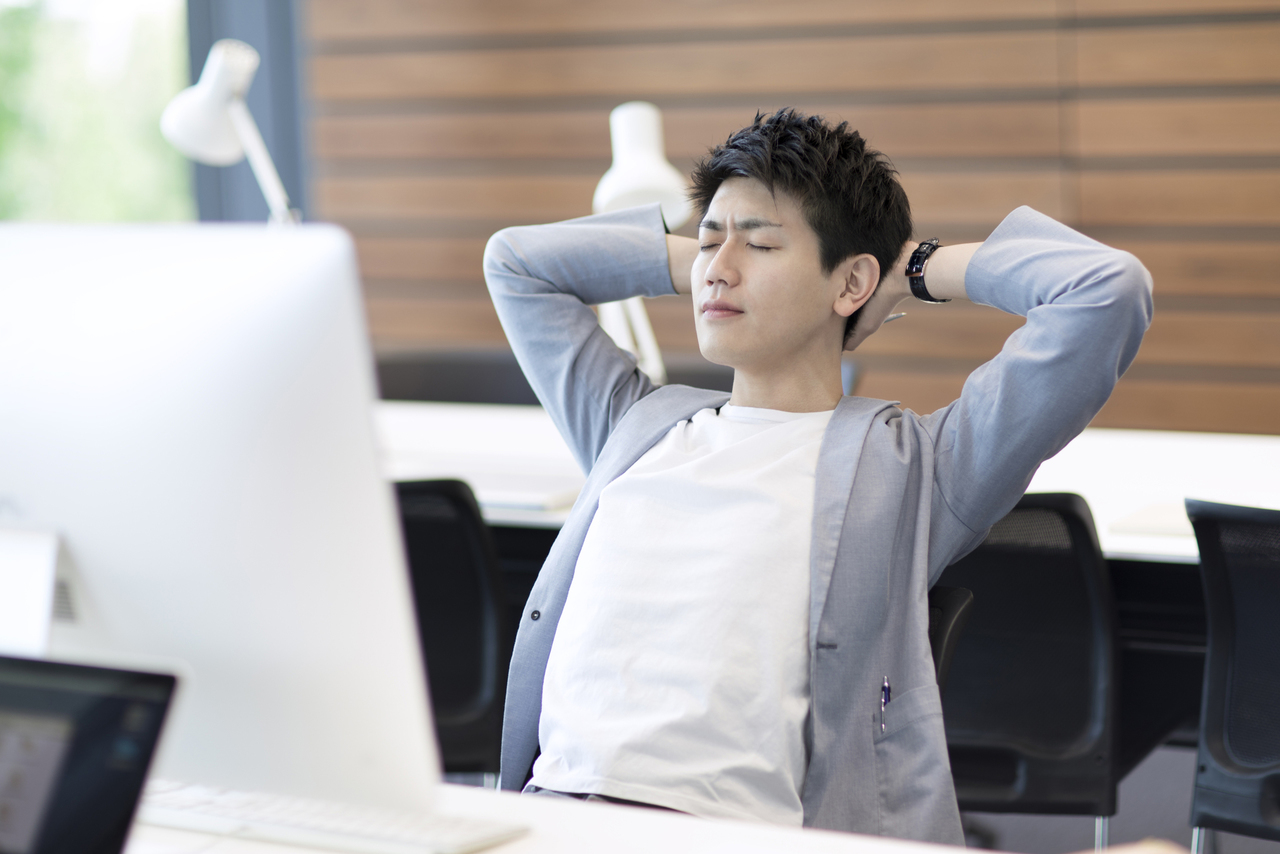
「やってられん・・。」
グループの中にそう思っている人がいたら・・。
昨日午後買い物に行ったときに以前の職場の同僚に会いました。コロナになる前は一緒にカラオケに行ったりご飯を食べたりしていた人です。
久しぶり~♪と声を掛けたら「直子さん、会社が大変なのよ。」と言います。どうしたのかと思ったら、跡継ぎとして入社した社長夫婦の息子さんが会社を辞めて家を出たとのこと。
いきなりだったそうで、きっと家で散々もめてたんだねと、そんな話をしました。
親と縁を切った・・。子どもに縁を切られた・・。あのご夫婦と付き合うのは本当に大変だとは思いましたが、長男さんもずいぶん思い切ったものだと。「いくら親だからってもうやってられん!!」という気持ちだったんかなと。
基本的に人間関係の争いはどっちもどっちと私は思っていますが、困るのは社員さんたち。会社が存続できなければ、という不安で皆さんいっぱいのようです。
自分たちの行動の結果を自分たちが引き受けるのは仕方がないが、職場・会社というグループに対する責任はどうとるのか・・。
グループに対する責任・・について機会があったら書いてみたいと思います。
ヤングケアラーの定義

上の子どもが下の子どもを慈しみ
喜びをもって関わる関係
ヤングケアラーという言葉が出てくるようになりました。調べてみると子どもが親の介護をしたり下の兄弟の世話をするなどの意味のようです。
子どもが自分のタスクに取り組めない場合(自分がすべきことをすべき年代に取り組めない場合)や「強制」があったり、嫌だけどやらなきゃといった意にそわないがやらされるやらざるを得ない状況などが判断のポイントだと思うのですけど、今の定義だと「協力し支えあう親子関係」とか「家族のグループで自分が役割をもって何かしらの役に立つ」ことを目指すアドラー心理学の考え方に、極端に考える人がNOを言う可能性も出てきます。
大事なのは「喜んで」「自発的に」というキーワードでしょう。問題の実態が私自身把握できないので今は何とも言えないが、言葉が独り歩きするのはよくあること。
考えてみれば私だってヤングケアラーだったわけです。中学校から家事を全部やっていたし、弟の幼稚園の送り迎えや病院へ連れて行くなどずっと高校までやっていました。
それが問題だと言われればそうかもしれないが、それがなくても勉強したかどうか・・自分の課題に取り組んだかどうか・・・はやっぱり自己決定だと思うんですよね。
これからのヤングケアラーという言葉がどうなっていくのか、について事態の推移を見守りたいと思っています。
「事実は一つだが解釈は無限大」ー認知論
楽しくアドラーを学ぼう会・開催

もっとアドラーを学びたい
そんな人たちが増えている
最近の傾向として、一つの講座が終わると「もっともっとアドラーを学びたい」という方たちが増えてきているなと感じています。
これだけ世の中にアドラー本があふれているのに・・です。不思議ですね。
今日はELM3回コースの最終回でした。終わるのが本当に残念で寂しいなという気持ちでした。それはご参加の方たちも同じだったようです。
それで理論を楽しく学べる勉強会をやろうか、という話になりました。
今までの親の会はそのまま子育てで悩んでいる方たちのために残して、アドラー心理学勉強会は「人間関係塾」と名前を変え、アドラーの理論や講座の復習は「楽しく理論を学ぼう会」と変えていこうと思います。
楽しく深く学ぶ仲間との時間。これからも私やご参加の皆さんの人生を濃く豊かにしていってくれると思います。
ああ、本当に楽しかった。。
個人の世界観は雰囲気で現れる・・

その人の世界観が雰囲気として現れるのが「構え」
苦手な人いますよね。。誰だっていると思います。
家族や身近な人間関係や、どうしても付き合わなければならない人たちとは関係を悪くしない配慮は必要でしょうが、自分の人生で関わらなくて済む第三者なら・・付き合わなければ付き合わなくて済むなら「なかよくしなくてもいいや。」もあっていいと思います。
今私自身はどうかというと、ほとんどの場合なんとか対処できることが分かっているので問題はないけれど、いわゆる「構え」が違う人はわかりますので、あまり距離をつめないようにしています。
「構え」は、その人の持っている世界観が反映して雰囲気として発出する。他者に対して「構える人」と言えばわかるかなと思います。
他者に対して構える人はたとえばうちのグループに入ると「浮き」ますから、世界観が変わるには時間がかかるのであまり触らないようにする。来続けているとその構えが自然に取れて浮かなくなる。
アドラー心理学をやっていてもこれが全く変わらない人はたくさんおられます。資格があろうが、長い間やっていようが、たくさん講座を受けていようが、変わらない人は変わりません。
どこがどう?って明確に説明できないところが世界観なので、雰囲気としかいいようがない。
自分の周りの世界や他者をどう見ているか・・。他者は敵ばかりでこの世は危険なので用心しないと・・と思っているのか、他者は友であり仲間でありこの世界はおおむね安全安心だと思っているのか‥の違いです。
アドラー学んで世界観が変わらないってのは、教える側に問題があるんだと思うんです。教える側が「構え」ていれば、構えた教えをアドラー心理学として伝えるんだから、変わらないよなというのが実感です。
だから誰から学ぶか・・ってとても大事だなと思っています。
仲良くなるのに理由はいらない

自己決定通りに進んでいく
「仲良くしたいかしたくないか」は自己決定。。
付き合えないとか付き合いが苦手だというのは、自分が相手に条件を付けているだけ・・なんだよねえ、と感じるこの頃。
あの人はああだから、こうだから・・・だからちょっと付き合えない・・って感じでしょうか。
相手の一部分だけを見てそれが相手の全部だと思ったり、相手の嫌なところに注目したりすると、付き合えないと感じることが増えるんだなあと。
ところが相手にとっても自分のそういうところは見えているはずで、お互い様よねと思う。
「仲良くしたい?したくない?」
講座の時にご相談者に決めていただくのですけど「仲良くしたい」場合には相談になるのですが、「仲良くしたくない」場合には相談になりません。
「仲良くしたいならどうしたらいいのか?」は具体的に話が進みます。
ところが「仲良くする」も人によっていろいろ捉え方があって、うちのわんこのように引っ付くことが仲良しと思っていたりする人もいるし、基本的におひとりさまが好きででもたまには一緒もいいなという人もいて、どういう付き合い方が自分にとって自然で楽であるのか、は違うんですよね。
この辺の加減を自分なりに実現していくのが難しいと感じるところなのかもしれません。
私自身はどうかというと「引っ付かれる」のが大嫌いです。「かまってちゃん」は振りほどきたくなります。ところがどういうわけか「引っ付かれ」たり「かまってちゃん」が来るんだなあ・・・(笑)
親の会追加開催・理由はシンプル
「困っている人がいるんだからできることをやる」

悩んでいる人をひとりにしない
困ってる人がいるんだから・・・やればいい。そんな単純な理由で親の会追加開催することにしました。
最近ようやく体調も良くなってきたところだし、例年通りGW明けから不登校相談が急増しているし、5月の親の会は早々と満席になってしまったし。。
ということで仕事を増やす。(笑)
やれるんだからやればいい・・一人でも二人でも気持ちが楽になることに自分がお役に立てれば何よりだと思います。
来た人は良くこう言う。「こういう相談ができるところってないんです。」
こういう相談って??、「誰にも知られず」「同じ悩みを抱えたものが集って」「なんでも相談できて」「気持ちが軽くなって」「希望が持てて」「明るくなれて」かな???
聞いたことがないのでわからないんですけど、とりあえず参加してよかった・・はあるみたいです。
確かに・・・自分が悩んでいたときもそうだったけど「どこに?」「だれに?」「どうしたら?」はもちろんだけど、相談しても解決の道筋が示されないとかあまり真剣に相手にされなかったり、批判されたり指示されたりするんじゃないかという恐れはありますものね。
ありのまま受け止めてもらうだけでも参加してよかったと思ってもらえるのかもね。
というわけで追加開催はこちらから⇒オンライン講座案内
思わず笑ってしまったこと

相手の不思議も「笑って許せる関係」
先日お弁当をひっくり返してしまった主人の話を昨日メルマガで書いたんですけど、昨日は洗濯物の中にティッシュが入っていて洗濯物がティッシュのくずだらけになってしまいました。
あら?ティッシュ??と思って「洗濯物がティッシュだらけになってる。」と言いましたら、主人が「あ!俺。ズボンのポケットにティッシュ入れてたんだった。。」と。
あら、今日はそれなの?と思ったら思わず吹き出してしまいました。「この人は・・しょうがないわね。」と思ったらなんだかとてもおかしくなったのです。
で朝から洗濯物を一枚一枚干しながら私がくずをパタパタしている横で、散らばったティッシュのくずを掃除機で吸い取る主人。
日曜日の朝から仲良く共同作業。。いいでしょう?(笑)どっちが指示したわけでもなく、自然に共同作業になってる我が家。
夫婦の凹凸ってこんな感じのことです。
「自分のことは自分ではわからない」

「自分のことは自分ではわからないものだ」
最近の自分を見ていて、確かに「世話焼き」だと思うようになりました。
誰かや何かのために・・・せっせとやっていることが多いと感じます。
「世話焼き」と母のケアマネさんに言われてから、最近になってようやく「あ、そうだわ。」と気が付くようになりました。
アドラーをやり始めてからはできるだけ、手をかけないようにしていたつもりですし、以前に比べたら格段に誰かのために・・は減っているけれど、まだまだやってることが多いのかもしれないと。
ただ「~してあげたのに・・・。」という発想がアドラーのおかげでなくなった。
その分余計無意識にやるようになっていたのかもしれませんが、「やりたいからやる」でいいのかも・・・とも思っています。
今日はオンラインのSMILE。コロナでオンラインになってから、ずっと家にいるようになって
昨日気が付いたけど「自分の理想の生活してるなあ・・。」って。家にいるのが基本的に好きだから「仕事も好きなことも」家でできるって最高だと思っています。
目的が違う・アドラー前とアドラー後

「聞いてみる」の目的が違う
アドラー前とアドラー後
昨日の続きですが、アドラー前とアドラー後は、同じ「他者の意見を聞いてみる」でも目的が違うなと思います。
アドラーを学ぶ前は「自分の正しさを証明したくて」とか「自分が間違っているのではないかという不安を払拭したくて」という目的で、人の話を聞いていたように思います。
アドラー後は目的はシンプルで「自分は~と思ったんだけれど、他の人はどうなんだろう?」という他者への関心・興味が目的になったと感じています。
なので自分が正しいかどうかはあまり問題にならないというか、別に違っていたら違っているで仕方がないと思っているのです。
自己受容しているとこうなるかと思うんですけれど、アドラーを学んでいても自己受容していないとなかなか「評価」から抜けきれない。要は「どう思われているか」が気になっている状態。
「あなたは間違っていません。安心してね。」というお墨付きを他者に求めてしまう。評価を求めてしまうんですよね。
自信のなさから他者の評価を求めがちになるんです。これを求めているうちは苦しいだろうなと思います。
自分が間違っているかもしれない・・と思ったら

とりあえず周りに聞いてみる
アドラーやり続けてよかったなあと思うことの一つに、周りとの関係が良くなったので「もしかしたら私の考え・感覚は違ってる?」と思えるようになって、それをとりあえず周りに聞くことができるようになったことがあると思います。
姑を入院先からデイサービスに送っていったとき、デイのスタッフさんがものすごくテンション高く、あまりになれなれしく「きゃ~〇子さ~ん、会いたかったよ~。私のこと覚えてる?」と言っていきなり姑をハグしたので、びっくりしてしまった。
「ゲッ?いつもこんな感じ??馴れ馴れしすぎじゃない?」とか「親しさを勘違いしてる?」とか「それって高齢者をバカにしてる?」とか感じてしまったのです。
それでたまたま話す機会があったアドラー仲間5~6人と、ご近所さん2~3人に聞いてみました。アドラー仲間はおおむね私と同じような印象を持ったようですが、ご近所さんは「そうだっけ。それがあの人たちのお仕事だから。」と言います。
「ああいう感じで接してもらってうれしいのかしら?」も聞いてみました。
アドラー仲間は「馬鹿にされているようでうれしくない。」がほとんどで、ご近所さんは「うれしいんだと思う。家族には普段怒られたりあんまりいい顔されないからね。」と。
何事も・・・聞いてみるもんです。
ついでに「姑が病院でいうことを聞かないので手に負えないから2週間で病院を追い出された。」話をしたら、「うちなんか5日間で追い出された。」とか「うちは1日で手に負えませんから出てください。」って言われたとか。。
びっくり話は我が家だけではなかったな。。と思わず笑ってしまいました。。
「争わない」が大前提

すべては自己決定
争わない・勇気をくじかない
「自分は争わない」という自己決定が最初にあると、他者も変わっていくんだなと思います。
アドラーを学んでいる方でよくあるのは、自分はアドラーを学んで「勇気づけ」を実践しているけど、周りはそうじゃないから。。という「できない」という話。
これでは言い訳になってしまいますよね。
周りは争いたがる、勇気をくじくから、自分も争うし、勇気をくじいてしまう、という感じの話。。
これだとまだ原因論で生きていることになる。他者がどうだからこうだから私はできない。
目的論で生きるということは「他者がどうであろうと、私は争わない、勇気づけする」という目的に向かって生きることになる。
でやり続けているとこちらが争わないし、勇気をくじかないので、相手もそうなっていくんです。自然にそうなっていきます。自分だけが争いたがったり勇気をくじきたがったりすることが空回りして馬鹿馬鹿しくなっていくことが多いんです。
だから最初にこちらの決定ありき、です。それで終始一貫してやる。そうするとね、なんとなくよくなっていくんです。
最近母がとてもこちらの意図を理解してくれるようになって、「~したらどうなの?」という提案をすると最初は抵抗するようなことを言ってもあとで聞くとそうしている。。
私は提案するだけで無理強いはしませんから、あとは本人が決めればいいし、結果を引き受けてもらうだけと思っています。
で、結果を引き受けていろいろひどい体験・結末を引き受ける羽目になってしまった。
そういうことになるかなと思います。。
そのうちに、お姉ちゃんの言うことをやってみたらいろいろうまくいくみたい。。そんな風に感じてくれるようになったのかもしれません。
これは母の自己決定。最近自立へ向かって自分のやれることはやる、ってスタンスも頼もしく感じています。
問題は電話料金。(笑)ついつい話が盛り上がり・・(@@)えらいこった。。
「自分のことを後回しにする」という自分の課題

自分を後回しにして大事になる癖
私にはどうも「自分のことを後回しにする」行動パターンがあります。「自分のことを先延ばしにする」と言い換えてもいいかもしれません。
それで結構大きな事態になったりもしています。特に体のことでは、主人や周りの人にとても心配をかけることになったりもしています。
先月あたりから2年前受けたオペの傷口から粘液が出て糸が見えるようになっていました。2回手術をして退院時には痰取の穴まであけたのですからかなり深く傷になっていましたが、順調に傷跡は消えてきていたのでそのうち治るだろうと思っていました。
が、どんどん悪化しているように感じて気になってきました。
連休明けまで待とうかなと思いましたが、「いやいや、大事になる前に行った方がいいでしょう。」と思い直し、通院先に電話しまして、救急扱いで行ってきました。
看護師さんには「発熱患者さんでかなり混んでるので相当待つことになりますよ。」と言われましたが、それもこれも先延ばしにした自分の蒔いた種だから仕方がないと思って行きました。
幸いちょうど混雑がひと段落したころに行ったらしく、すぐに呼ばれました。
先生は出た糸を切っとくねとおっしゃって、この糸がグズグズの原因だからとパチパチ切ってしまいました。
そして来週担当医の予約もとってくださいました。行ってから帰るまで30分ぐらいだったでしょうか。ラッキーでした。
帰宅したらあらあら・・・すっかり傷口は良くなっていきます。また先延ばしの癖が出てしまって、病院側にも連休中に迷惑だったろうし休みに入る前に行っておけばよかったなあと、反省しきりでした。
課題が分かっているのに・・・とも思いましたけど、以前の私ならもっと悪化してから行っていたと思うので、少しは「自分優先」に行動できたことになるかもしれないと思っています。
違和感ありあり「迷惑だ」というフレーズ

協力とは??
いつのころからかはわかりませんけど、アドラー心理学をやり始めてから「迷惑だ。」と言う言葉に違和感を覚えるようになりました。
迷惑だという言葉の響きに「他者批判」「他者排斥」を感じるようになったのかもしれません。
最近になって「協力ということを学んでいない」「協力と言うことを知らない」からそういう言葉が出てくるのかと気が付きました。
もしも家庭で誰かが問題を起こしたとしても「協力的な家庭」が築けていれば、迷惑ではなく「助け合い」と捉えることでしょう。
職場でも同様に「協力的な人間関係」が築けていれば誰かの失敗に目くじらを立てるのではなく「自分が手伝えることはある?」と聞くに違いありません。
それでは「協力とは??」と考えると、誰かや何かのメリットのために動くことではないと私は思います。
お互いに得意なことを受け持っての役割分担と言えばいいかもしれません。我が家は今そんな風にして暮らしています。
苦手なことは得意な方が受け持つ。無理に苦手をやらなくても得意な方に任せておけばいい。
特に夫婦間の凹凸、ご相談を受けていて意外とうまくできているものだと感じることは多いです。
ところが相手が苦手なことを「~すべき」として自分の理想を押し付けたりすることで争いや問題になるケースが結構あるのです。
全く見知らぬ他人に面倒をかけられた‥と言うならともかく家庭内でとか職場内でとか「迷惑」と言うことが出てきたら「協力的なグループになっているのかどうか」見てみればいいと思います。
相手を友だとか仲間だと思っていればそういう言葉は出てこないでしょう。
相手の得意を活かして家庭内・職場内で活躍してもらった方がいいし、苦手は得意な人がフォローすればいいし、そうして協力していくグループになっていれば、「迷惑」なんて言葉は出てこないと思うのですがね。。
2021・5・3 おしゃべり会開催しました。
「無理」とか「無駄」と考えることが自分を追い詰める

楽しくおしゃべりの意味
日曜日に初めてオンラインでのおしゃべり会をやってみました。ご参加は私を含め4名だったのですが、おしゃべりに夢中になっている間にお二人の方が「今から参加大丈夫ですか?」とメールをくださっていたのでした。気が付かなくてごめんなさい。
とにかく日本人といえば・・・「真面目」なので、ご相談を受けていても「遊び」や「無駄」が本当にありません。
「遊び」や「無駄」は意味がないと感じていませんか?遊びや無駄こそ心の余裕につながるともいえる。それがないのでどうしても「キツキツ」になりがちです。
「無意味なことはしない」とか「無駄な時間は過ごさない」とか、ですね。そして何か問題が起きるとすぐに結果を求めたがる。
そんなに生きいそがなくても・・・と思います。アドラー心理学のタスクでいうとセルフタスクにあたるかなと思います。
自分の息抜きがなんだか「落ち着かない」方は「何かしていないとダメ」と感じておられるのではないでしょうか。
2021・5・1-「事例検討会」って最高におもしろい・・

事例検討会って何やってんの?って話だけれど、人に対するあくなき興味の尽きない人たちが、人の悩みについてああだこうだ、どうしたらいい?なんて話を延々としている場‥と言えばいいかしら、と思います。
一応ある程度アドラーの身についた人でないと、話が通じないので、勇気づけリーさんとかに参加は限定しています。
とにかく自分にしか興味のない人は続きません。他者への関心の高い人しか残っていかない。
みんな自分のことに興味があるわけだし、自分のことで精いっぱいだったりするんだけれど、それはそれとして、アドラーの共同体感覚って他者への関心と貢献が一つのバロメーターなので、共同体感覚が持てていれば自分に関係のないことでも好奇心満々に興味をもって取り組める‥って感じですかね。
4月は早期回想分析をやりました。メンバーのおひとりの分析をみんなでやってみました。
やっぱり「どういうわけか同じことを繰り返している」場合にはすっかり過去の記憶にそれが現れます。アドラー先生は見事だとしか言いようがない。
アドラー心理学をやっている人の中には「できなくてもいい」とおっしゃる方がおられるが「できなくて使えない」のと「できるけど使わない」のでは意味が違いますし、私は結構使えると思ってやってます。
今回は分析の後で「私はこういう使い方をしてますよ。」ということもお話ししました。で、受けた人はどうなるか・・・というと「つきものが落ちた。」とか「すっきりした。」とか「すっかり肩の力がぬけて楽になった。」とか。。
自分の謎が解けると、過去の経験から来た苦しさとか呪縛から解放される。。これからどうします?とお聞きすると、大概「ああ、もうたくさんだからおさらばします。」って感じになるんですよね。
取って食わないから(笑)なんだか苦しい‥と言う方には活用してもらえればうれしいですね。リクエストがあれば分析しますし、これからどうする?って話もできますから。多分こういうことやってるの私だけかなと思います。子どもの頃の家族関係と子どもの頃の記憶をお話していただくだけなので1時間ぐらいあれば割と簡単にわかります。(2021・5・1)
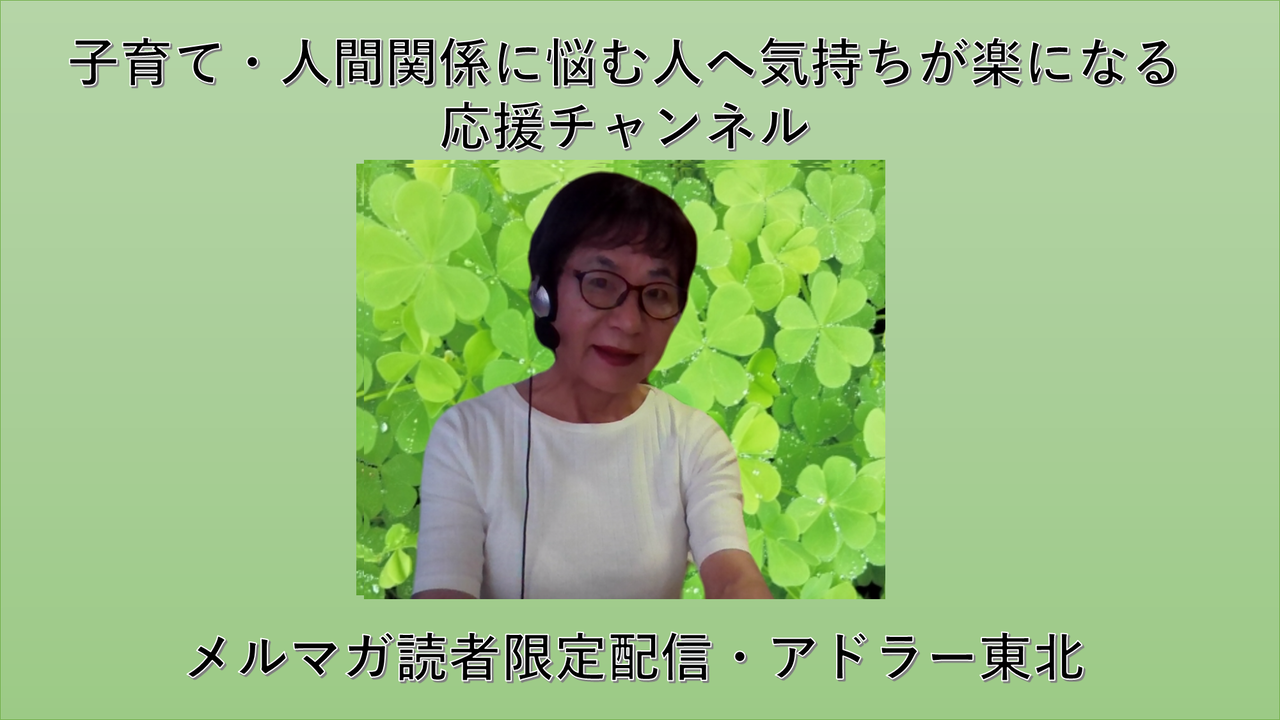
メルマガのご登録を頂いた方にお役に立つ動画の配信をさせていただいております。
ご興味いただけたら
まずはメールマガジンからご購読
無料メルマガのご登録はこちら

メールマガジンはこんな方にお勧め
- 子育ての悩み「仕事との両立」「兄弟平等にしたい」「子どもの将来が不安」「私の子育て合ってる?」「つい子どもにイライラ」
- 職場の上司・同僚・部下との関係に悩んでいる
- 配偶者・親戚・身近な人間関係などに悩んでいる
- アドラー心理学を日常に活かす方法を知りたい方
- 身近な事件や社会問題をアドラー心理学ではどう捉えるのかを知りたい方
- アドラー心理学の基本的な考え方を知りたい方
- アドラー東北(仙台)の講座の様子等を知りたい方
- セミナーや勉強会・役に立つ本・企画の情報を知りたい方
新着情報
ごあいさつ

資格、経歴
日本アドラー心理学協会認定・マスタープラクティショナー
日本支援助言士協会認定・コミュニティカウンセラー
日本ブリーフセラピー協会認定・ブリーフコーチ・エキスパート
ヒューマン・ギルド社認定
SMILEリーダー、ELMリーダー&トレーナー
誠実に一生懸命に丁寧に
15年の臨床経験に基づいて「受講生さんを笑顔にする」をモットーにしております。ご相談はお気軽に。
お客さまの声
すべきことが明確になり、重くのしかかっていた悩みから解放されました。

思春期の子どもとの関係に悩んでいてアドラーの本に出会い受講しました。子どもを支配しようとしていた自分に気づかされました。何から取り組んでいったらいいのか明確になり、重くのしかかっていた悩みから解放されました。

